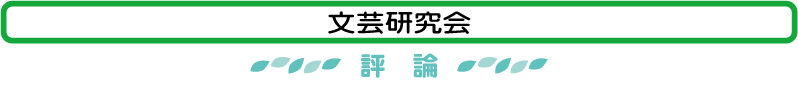|
タイトル
|
作 者
|
投稿日 |
| 魯迅の素顔(3)─ さすらいの果てに ─ | 村木 久美 | 2010.8.31 |
| 魯迅の素顔(2)─ 周家を崩壊させた嫁 ─ | 村木 久美 | 2010.8.4 |
| 魯迅の素顔(1)─ 魯迅と藤野先生 ─ | 村木 久美 | 2010.6.26 |
| 魯迅の素顔(3)─ さすらいの果てに ─ | |
| 村木久美 2010年8月31日 |
|
|
話は、1906年(明治39)3月、魯迅が仙台医専を退学し東京に戻ったところから始まる。 さて、話は魯迅と次弟・作人夫婦との決裂の直後である。 1925年(大正14)3月、ある日突然、魯迅の目の前を春風が通り過ぎた。春風の正体は許広平【きょこうへい】。広平は、魯迅が講師をしていた北京女子師範学校の学生だった。彼女は広州の旧家出身で、生後3日目に父親の決めた婚約に頑強に抵抗し、18年を掛けてこれを解消したというつわものであった。彼女もまた「新しい女性」の一人であったのである。その後上京した広平は、たまたま魯迅の勤務する北京女子師範学校に入学したのだった。当時27歳の彼女は国文科3年に在学中で、また学生自治会委員としても活躍し、非近代的な大学の体質や運営に憤りを感じていたのである。ある日、その憤懣【ふんまん】を日頃学生運動に理解のあった魯迅に対し、手紙を通して訴えてきたのだ。だが、この一通の手紙こそが二人の運命の始まりとなったのである。手紙を受け取った魯迅は、日頃明るく活発な広平に対し、指導者として丁寧な返事を書き送った。この返事がきっかけとなり、魯迅と広平の間には手紙の往来が続いて行くことになる。そして3ヶ月が過ぎた頃には、互いの愛称で手紙を締めくくるという仲にまで進展して行ったのであった。明朗で愛らしく、ジョークを理解し、ウィットに富み、更には負けん気が強く涙もろい広平の中に、魯迅は母親に似たものを感じ取って行ったのかもしれない。17歳も年下の広平であったが、彼女は日々魯迅の心を虜にして行ったのである。自分の人生にはけして訪れないと諦めていた「人を愛する喜び」に、この時魯迅の心は大きく揺れ始めていたに違いない。 1926年(大正15)3月、世に言う3・18事件が起きた。日本軍など8カ国の干渉に抗議する集会が天安門広場で開催され、その場にいた市民・学生のデモ隊列に何と軍警が発砲するという衝撃的な事件であった。この結果死者47名、負傷者50数名という大惨事となったのである。この犠牲者の中には魯迅が将来を嘱望していた学生もいた。しかも、この日は許広平もこのデモ行進に参加する予定だったのである。この事件を耳にした魯迅は、憤激の余り2〜3日は食事も出来ず、口もきけない状態であったという。一連の学生運動を支援してきた魯迅にとって、この事件の衝撃は想像以上に大きく、魯迅の心は深く傷ついていたのだった。この日、広平は魯迅の手伝いをしていたが、その仕事が長引いたためにデモの参加に遅れてしまったのだ。それがからくも広平の命を救ったのかもしれないが、万が一を想像した魯迅の怒りは一層膨張したのかもしれない。 一方正妻・朱安は魯迅が北京を去ってから、妻としても女としても自信を失い、大きな空しさの中で暮らしていたのではないだろうか。しかも「魯迅の北京脱出は教え子との駆け落ちである」という噂話にも、朱安は大いに傷ついたに違いない。これまで朱安は、自分もいつかはきっと夫に愛される日が来るものと、その日をひたすら待ち続けて来たのだった。だが朱安は魯迅が妻の自分に何を求めているかなどと、考える術のない女性でもあった。朱安の抱く妻像とはひたすら夫にかしずくものであり、封建社会の流れに身を任せることを良しとする古いタイプの女性であった。その点において、朱安と広平とは正に対極にいる女性であったのである。さらに朱安の嫁いだ周家は、夫の母親でさえ独学で文字を学ぶという進歩的な家庭であり、そこに嫁いでしまった朱安こそが不幸であったと言わねばならない。 「意外ナコトデ夜中カラ又喘息ガハジメマシタ。ダカラ、十時頃ノ約束ガモウ出来ナイカラ甚ダ済ミマセン。御頼ミ申シマス。電話デ須藤先生ニ頼ンデ下サイ。早速ミテ下サル様ニト」 魯迅は、幼い頃から父の病のため、全く効きもしない高価な薬を買うために質屋通いをしていた。儒教の影響による迷信を強く憎みながら成長した魯迅は、やがて東京に留学し西洋医学を志した。そして1918年(大正7)、魯迅の名で処女作となる「狂人日記」を発表し、その中で歪んだ儒教道徳を厳しく批判したのだった。しかもこの時、中国では初めてとなる口語体での作品を世に送り出したのである。だが皮肉にも、魯迅の憎んだ悪しき因習との闘いは、己の結婚により挫折したのだった。その人生に絶望していた魯迅の心を、谷底から引き揚げたのが若き女子学生・許広平であったのである。 ─ 魯迅の素顔(3)終 ─ [参考文献]
|
|||||||||
| 魯迅の素顔(2)─ 周家を崩壊させた嫁 ─ | |
| 村木久美 2010年8月4日 |
|
|
「中国近代文学の父」と言われる魯迅には2人の弟がいた。次男の名は周 作人【さくじん】、三男は周 建人【けんじん】といい、実は2人の弟は日本人の羽太【はぶと】姉妹との国際結婚だったのである。だがこの事実を知る人は案外少ないだろう。作人の妻は羽太信子、建人の妻は羽太芳子といい、この日本人の嫁は結束の固かった周家の家族を、やがて崩壊に導いてしまうのである。 1906年(明治39)3月、仙台医専を退学し再び東京に戻った魯迅は、本郷区(現文京区)湯島に下宿を定めドイツ語学校に入学した。毎日ドイツ語の原書などを読み耽りニーチェ、バイロン、キルケゴールなどの思想や文芸を吸収し、日本の漱石、鴎外等の作品や評論をも読破した。1908年にかけての魯迅の評論や翻訳量からすると、その読書量は相当なものであったらしい。 東京から気の進まないまま中国に渡った信子は、紹興の言葉を覚えるでも家族に打ち解けようとするでもなく、作人だけを頼り切り、家族との意思疎通は作人の通訳によって図られる始末であった。そして間もなく信子には奇病が現れるようになっていた。イライラが募りまた自分の思う様に行かない時など、信子は突然大声で泣き出し意識を失い倒れた。魯迅の母は大層心配しその度に慌てて医者を呼んだが、医者も首をひねるばかりだったという。 1912年(大正1)5月16日 信子は長男・豊一を出産した。そしてその一週間後に15歳の妹・芳子は、兄・重久と共に紹興へやって来たのだった。 1917年(大正6)4月 作人は北京大学への就職が決まった。これはかねてより魯迅が友人である学長に依頼しており、それが実現したものである。この時魯迅は作人に北京赴任の旅費まで送り、しかも同じ会館に住むことになった作人に対し、南向きの自分の部屋を明け渡し、なんと自分は窓も無く湿気の多い北側の部屋に引っ越しをしたのだった。「体調の良い日は年間一日とて無い」と日記の中で嘆く魯迅にとって、かくも家族は大切なものであったのである。そしてその後も紹興の家族の生活費は、魯迅からの送金で賄われていた事は言うまでもない。 ところでこれより以前、信子は子供達と重久を引き連れ、4月に東京の実家へ里帰りをしていた。日記によるとこの時魯迅は、東京の信子宛に給料の約2倍もの送金をしている。更にその4ヶ月後の8月、帰国した信子達一行は紹興の家には戻らず、北京・八道湾の家が完成する11月まで、北京で家を借りて住んでいたのである。紹興の家を畳むにあたり、信子は嫁としてなすべき事は山程あったにも拘わらず、また魯迅が膨大な借金を抱えようとしているこの時期に、魯迅に更なる多額の出費をさせ、長期の東京への帰省と北京での割高な借家住まいをするとは、とても信子の神経は尋常ではない。まして魯迅が母親の為に建てた新居へ、引越しの手伝いもしなかった信子が、母親よりも先に住み込んでしまうとは、とても日本人として受け入れられるものではない。 それでもとにかく、64歳の母を頂点に北京八道湾での生活が始まった。しかしそれも束の間、転居1年後には作人が肋膜炎を患い入院し、3ヶ月間の転地療養を含めると実に10ヶ月間の闘病生活となったのである。魯迅はこのとき費用捻出の為にまたまた給与の2倍以上の借金をしている。そして多額の借金返済の為か、魯迅は転居半年後から高等師範学校に於いても働き始めたのであった。 ところが、芳子が自ら犠牲を払い北京に残ったにも拘わらず、ある日突然周家は一気に崩壊してしまったのである。その経過を魯迅の日記から見てみよう。 *1923年(大12)7月14日「今晩より自室で食事をすることにし、自ら料理一種を用意する。これは特記すべきことなり」 [ 魯迅先生 作人は「過去のこと」を理由に魯迅との断絶を言い渡している。裏切られた自分は今後一切魯迅とは関わり無く生きて行く、と言っているのである。 *「…西廂房(魯迅の部屋)に入ろうとすると啓孟(作人)およびその妻が突然とび出し、罵倒殴打におよび、更に電話で重久と北京大学の仲間を呼び、その妻、皆に向かいて余の罪状を述べ立てる。口汚ない言葉を弄し、およそ捏造【ねつぞう】もはなはだし。…」 近所に住む友人の話によると、この時作人は怒鳴り声を上げながら、30cmもある銅製の香炉を魯迅に投げつけようとしていたので、慌てて止めたという。また信子は何処かへ電話をしていたと話した。魯迅が八道湾の家を取り返しに来たとでも思ったのだろうか。結局魯迅は大切な本も持ち出せないまま、これ以降一切八道湾宅を訪れる事はなかったのである。 現存する魯迅の日記は25年分(実質24年分)である。今回私は残された日記の最初から12年分を読み返してみた。つまり日本から戻り、北京の文部省勤務初日から、八道湾宅に荷物を取りに出掛けたところ迄である。 最後に、中国では「最初に井戸を掘った人を忘れない」という。一方日本にも「恩返し」の精神が、わが国の文化として脈々と受け継がれて来た。しかし、これまで見てきた魯迅に対する作人と信子の在り様には、人としてのあるべき何かが欠けているように思われてならない。今回取り上げたテーマは、同じ日本人として特に同じ女性として、私にはとても遣り切れないものであった。だが羽太信子は藤野先生と同様、魯迅の生涯に大きく関わった日本人の一人であり、尚且つ魯迅と大きく関わった3人の女性の1人でもあった。まして魯迅の身内として存在した日本人・信子を、素通りする訳には行かなかったのである。 ─ 魯迅の素顔(2)終 ─ [参考文献]
|
|||||||||
| 魯迅の素顔(1)─ 魯迅と藤野先生 ─ | |
| 村木久美 2010年6月26日 |
|
| 私が初めて魯迅【ろじん】の名を知ったのは、現代中国史の講演会であった。それは私が40歳を少し過ぎた頃である。戦後の中学校教科書に魯迅の作品「故郷」が掲載されていたらしいが、私には習った記憶が無かった。それよりも講演の中で、若き日の魯迅が仙台の地で学んでいたという事実の方が私にとっては遥かに大きな衝撃であった。それは私の出身地が福島市であり仙台市はいわば隣である。しかもその地には様々な思い出を残す私だったからである。その様な思いがやがて私を魯迅探しへと向かわせたのであった。 魯迅の資料を求め私は神田の古書店街に出掛け、地域の図書館を調べそして街の書店を回った。魯迅に関する資料はけして多くはなかったが、その資料の中から見えて来たものは、魯迅の中国人民に対する強い熱情と、人間としての愛と悲しみ、そして何より苦悩に満ちた魯迅の人生だったのである。 明治14年(1881)9月25日、魯迅は浙江省紹興府に生まれた。本名は周樹人【しゅう じゅじん】、魯迅の誕生はアヘン戦争から40年後の事であった。 大正15年(1926)10月、魯迅は仙台医専での思い出を作品「藤野先生」に纏めているが、それは魯迅が仙台を離れてから既に20年の歳月が流れていた。その中で魯迅は、先生との出会いを次のように書いている。 この時の魯迅の感激は、実際いかばかりであったろうか。当時の日本に於いて弱国・清国人に対する扱いはかなり酷いものがあり、差別はいたる所にあったのだ。従って、藤野先生の行為は当時の魯迅にとっては信じられないものであり、言葉に尽くせない程の感激を覚えたに違いない。だからこそ魯迅は、感激と共に「ある種の不安」を覚えたのではないだろうか。魯迅はその後に起きた二つの事件のあと医学の道を諦め、藤野先生にも本心を明かす事無く、一年半を過ごした仙台の地を後にするのだった。 ところで魯迅の入学後一年が終了し、やがて成績が発表された。魯迅は142人中68番目で及第したがこの直後に事件は起こった。同級の学生会幹事が魯迅の下宿を突如訪問し、藤野先生が毎週添削しているノートを調べに来たのだ。まもなく魯迅の元に手紙が郵送されて来た。そこには藤野先生が魯迅のノートに印をつけ、あらかじめ試験問題を漏らしたから魯迅は及第したのだ、という内容が匿名で書かれていたのである。当時の級友の証言に依ると、この頃の試験はかなり難しく清国人である魯迅があの順位で、しかも及第するのはおかしいとの流言が事実あったそうである。しかしながら試験の結果魯迅は、藤野先生の解剖学だけは落第点の「丁」だったのである。 第二学年に進級すると細菌学の授業が加わり、細菌の形態はすべて幻灯を使って学習した。幻灯を使用する授業は当時の新式講義方法として注目され、しかもここにはドイツ製の幻灯機が備えてあった。時おり細菌学の授業で時間が余ると、残りの時間は時局幻灯の上映が行なわれていた。二つ目の衝撃はその時に起きたのだった。時局幻灯は折しも日露戦争の勝利場面の映像で、その中に中国人がロシアのスパイを働いたかどで銃殺される場面があった。それをまるで見世物を見る様に取り囲んでいたのは、何と魯迅の同胞である中国人だったのである。この光景は改めて魯迅の感情を揺り動かした。魯迅は中国人特有の、何に対しても「没法子」(仕方がない)と諦めてしまう精神を強く憎んでいたが、それは裏を返せば中国人民を愛して止まない魯迅の熱情でもあったのである。 この様に、試験問題漏洩疑惑での憤り、また時局幻灯で誇りを失くした同胞の姿を目の当たりにした魯迅は、急速に医学への関心が薄れ、中国人民の意識改革に向かって一気に走り出したのだった。 ところで作品「藤野先生」が書かれた意味を考えてみたい。「藤野先生」と名付けられたこのタイトルも又その内容においても、他の魯迅作品とは少し異質に思われてならなかったからである。魯迅は作品のタイトルに実名を使う事は殆んど無く、内容においても風刺や譬えや比喩を用いて書き上げたものが多い。「藤野先生」のように、事実に近い内容を淡々と綴ったこの作品には、書かれていない行間に何があるのだろうか。もしかしたら作品「藤野先生」は、作品の内容を超えたところに魯迅のメッセージが隠されているのかも知れないと私は思った。 ところで49歳の魯迅にまた一つ、運命の出会いが待っていた。 ≪彼の茨を伐り開く使命感と、勇気と敢為に感動し、これはタダモノではない、偉い人だと思うようになった。何よりも微塵のまやかしもない、という意味での強烈な人格に打たれた。いまの中国にはこのような人のいることを、このような人の出てくる中国の現実とともに日本に報せたい、と私は思った。それで「魯迅伝」というのを書き出した。≫ 佐藤春夫は「魯迅伝」に大変感激しこれを出版すべく奔走した。「改造」に断られ「中央公論」にも突き返されたが、それでも「改造」の山本社長に直接読んでくれと持ち込み、ようやく出版に漕ぎ着けたのだった。すると数年後には岩波文庫から佐藤春夫に「魯迅選集」出版の話が持ち込まれたのである。増田は大喜びで早速魯迅に作品選びの相談をしている。魯迅の返事は『内容についてはお任せします。只、「藤野先生」だけは入れて下さい』というものだった。魯迅は増田に『僕が僕の師と仰ぐ人たちの中で、先生こそ最も僕を感激せしめ、僕を鼓舞激励して下さる唯一の人』と語っている。この頃既に藤野先生が仙台に居ない事を知っていた魯迅は、増田に先生や先生の家族の消息についても尋ねている。魯迅が作品「藤野先生」を書いた事もタイトルを先生の名前にした事も、いつか何処かでこの作品が先生や親戚の人の目に触れ、先生の消息が分かるのではないか、又は自分の事が伝わるのではないかと、魯迅は密かに期待していたのではないだろうか。 こうして不思議な運命の糸が繋がり、魯迅の作品が日本で出版される事になった。青春の7年間を日本で過ごし、志が医学から文学に変わったものの、これは藤野先生への何よりの恩返しであると魯迅は思った事だろう。昭和10年(1935)6月に出版された「魯迅選集」には、11編の作品と「魯迅伝」が収められ、その中9編が増田の訳であった。この「魯迅選集」出版によって魯迅はいよいよ先生の消息が分かるのではないかと、どんなに胸が高鳴った事だろう。だが日本で「魯迅選集」が出版されて一年が経過しても、先生の消息については何の反響も無かったのである。その頃病床にあった魯迅は『やはり先生はもう亡くなったのかもしれない』と増田に言い、大変残念がっていたという。だが、先生は生きていたのだった。しかも藤野先生の長男が中学の漢文の先生から『君のお父さんの事が書いてあるから読んでごらん』と、魯迅の本を手渡されていたのである。藤野先生はその時初めて、魯迅が中国で立派な文学者になっていた事を知ったのだった。しかし先生は自ら名乗り出るような人ではなかった為に、魯迅はついに先生に相見えるどころか、何ら消息を知り得ぬままに無念の死を遂げたのであった。 魯迅の死は日本でも大きく報道され、増田も日本評論に「魯迅追憶記」を書いた。それが藤野先生の地元である福井の地方記者の目に止まり、もしや診療所の先生と同一人ではなかろうかと、患者でもある仲間も加えた3人で藤野先生の診療所を訪ねたのである。こうして皮肉にも、魯迅は自らの死を以って藤野先生本人を捜し当てたのだった。 かつて魯迅は日本から帰国後、様々な事情により紹興〜北京〜廈門【あもい】〜広州〜上海と何度も移転を繰り返し、中国国内を移動し続けた。だが、藤野先生から貰った写真だけは生涯離さず自室に掲げ、写真を見ながらいつも自分を叱咤激励していたという。若き日に受けた恩を生涯持ち続け、先生の学問への厳しさと真面目さ、そして人としての優しさを己の糧として生きた魯迅はやはり偉大であった。そして、そのような魯迅を知り得た私もまた幸いである。その後作品「藤野先生」は温かな繋がりのある作品として評価され、中国の教科書に掲載されたのであった。
─ 魯迅の素顔(1)終 ─
[参考文献]
|
|||||||||