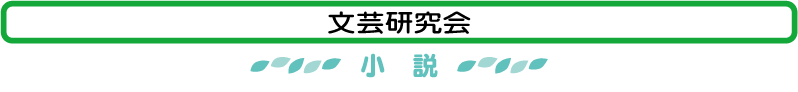| 面影の空に |
|
タイトル
|
作 者
|
投稿日 |
| 面影の空に(7)完 | 後藤 雄二 | 2008.9.10 |
| 面影の空に(6) | 後藤 雄二 | 2008.8.25 |
| 面影の空に(5) | 後藤 雄二 | 2008.8.10 |
| 面影の空に(4) | 後藤 雄二 | 2008.7.25 |
| 面影の空に(3) | 後藤 雄二 | 2008.7.10 |
| 面影の空に(2) | 後藤 雄二 | 2008.6.25 |
| 面影の空に(1) | 後藤 雄二 | 2008.6.15 |
| 面影の空に(7)最終回 | |
| 後藤 雄二 2008年9月10日 |
|
|
翌日の日曜日、五郎は外へ一歩も出ず、一日中、自分の部屋で物思いにふけっていた。ベッドに寝そべってばかりいた。 星空って、 「おお、進か。どした?」 「どした? じゃないよ。このごろ全然、顔を見せに来ないじゃないか。病気にでもなったんじゃないかって心配してたんだぞ」 「いや、元気だよ。だけど、入院しているお前に心配されるとは思いもしなかったなあ」 「ふふふ、ゴロー、おれはもう病人ではないのだ。ははは、この船村進の回復力!」 「何ふざけてんだよ」 「バカ言え! ふざけてなんかないよ。退院するんだよ、明日」 「本当か! 早く言えよ。そんな大事なことを。だから、元気な声だったんだな。しかしよかったなあ。本当は一月だったんだろ?」 「うん。これで正月は家で迎えられるよ」 「そうか。よかった、よかった。これで映画館へも行けるなあ」 「うん。まだしばらくは、禁止されているけど、すぐに観にいけるようになるよ」 「そっか。よかったなあ。また芝居もできるなあ」 「うん。来年こそ劇団に入ってバリバリ活動するよ。ゴロー、ところでお前のほうはどんな調子だい?」 「ああ。しばらく流星になってたよ」 「リュウセイ?」 「流れ星さ」 「何のことだよ」 「こっちの話だよ」 「訳の分からないやつだなあ。勉強のほうはどんな調子かって訊いてるんだよ」 「おう。この間の模試でK大文学部の国文の合格可能性がやっと九十パーセント以上になったんだ」 「・・・それはすごい! ゴローは現役ん時、ほとんどゼロパーセントの世界だったもんなあ」 「それを言うなって」 「古文はどうだい?」 「それが古文はほぼ満点だったよ」 「ウソだろー。信じられないよ。この『下手の横好き』が」 「何とでも言え。文法も完璧だよ」 「恐ろしい話だなあ」 「恐ろしいだろ」 「でもゴロー、あんまり分かりすぎるなよ。文法にいくら詳しくったって、つまらないことだよ。古典っていいなあ、て言ってたお前自身を大事にしろよ」 その言葉に、五郎はハッと胸を突かれた。自分はいつのまにか「愛惜の情」を忘れていた。 「・・・そうだな。その気持ち、忘れないようにするよ。受験のテクニックばかりに走って古文を楽しむのを忘れてたよ。・・・進、ありがとう。本当にありがとう」 「礼なんて言うなよ」 「違うんだ。おれ、何か、大事なことを忘れかけていたよ」 「誰だって忘れたり、気づいたりするものだよ。でもゴロー、よく頑張ったじゃないか。来年は、また腐れ縁で一緒にK大生だ!」 「おう。そういう腐れ縁は、大歓迎だよ。でも進、ホントに退院、よかったなあ。よくさあ、人間って長いこと入院したりすると、人生観が生まれたり、変わったりするって聞くけど、どんな感じだい?」 「そうだな。まだ分かんないな」 「そういうものなのかなあ、やっぱり。で、何か収穫はあったかい?」 「今日のお前、すごいこと訊くんだなあ。収穫か、そんなものあるかなあ・・・。あ、あった、あった」 進が大声を出して笑った。 「びっくりしたなあ。どうしたんだい?」 「収穫あったよ」 「何だい?」 「うん。いまここに持っているんだ」 「何を?」 「うん。写真を持っているんだ」 「写真? 何の写真だい?」 「うん。おれの彼女の」 進は照れくさそうに言った。 五郎の中に、めぐみの曇った顔と、軽い落胆が通り過ぎていった。 「・・・彼女の写真か。知らなかったなあ」 「写真、今日もらったんだ」 「ふうん。で、誰なんだい?」 「ゴローも会ったことあると思うよ。・・・彼女、ゴローには会っている筈だよ」 「誰かな?」 「三田さんの娘さんなんだ。めぐみちゃんっていうんだ」 瞬間、五郎は、息を飲んだ。 (そうか!) 五郎は、努めて平静を装うように、自分に言い聞かせた。ビデオ映画制作研究会では撮影班だったが、頑張れば、演技だって少しはできる。勘のいい進だが、めぐみとの約束は守らねば・・・。だが、五郎は思った。もしかしたら、めぐみは、自分とちょっとした知り合いであることを、もう進に話し終えているかもしれない、と。 「あー、何となく知ってる。物静かな感じの人だろ? 優しそうだったよ」 「うん。優しいんだ。性格は結構明るいよ。三日前、彼女のほうから、告白してくれたんだ。申し訳なかったよ。実はおれもずっと好きだったんだ。・・・うわっ、恥ずかしい」 「いつか、いいなあと思う人がいるって言ってたの、めぐみちゃんのことだったんだな」 「うん。実はそうなんだ」 「よかったなあ。お前の声、すごくいい感じだよ。本当にめぐみちゃんが好きなんだな」 「早く自分が告白すればよかったと後悔しているよ。彼女の勇気に、感謝感激しているんだ。でも、こういうのって、相思相愛って言うんだよな。むふふふ」 「そういうことにしておこう。めぐみちゃんは同い年くらいかい?」 五郎は、自分がよく知っていることを、わざと訊いた。めぐみは、進に何も話していないらしい。そうであるなら、自分は、ひたすら、めぐみとの約束を守り続けるだけだ。 「そう。彼女はS大の一年なんだ」 「そうか・・・。よかったなあ」 「なんだよ、ゴロー。しみじみとした声しちゃってさ。・・・さては、お前、おれを羨ましく思ってんじゃないか?」 めぐみのことを五郎は考えていた。 (めぐみさん、思いを果たしたんだな・・・) 「おれのこと、羨ましいんだろ?」 「・・・うん。少しな」 「おいおい、こういう時は『調子に乗るな』とか言ってくれよ。ゴローらしくもない」 「いや、進、いい人と付き合えて、よかったな。初めて進の見舞いに行った時、お前、散歩中だっただろ? あの日、病室で見かけただけなんだけど、めぐみちゃんは絶対いい人だよ。これでも、おれ、人を見る目あるんだぜ。大事にしてあげろよ」 「ありがとう。大事にするよ」 「めぐみちゃんのお父さんの退院はいつ頃なんだ?」 「実は、三田さんも、あと二、三日で退院されるんだ」 「そうか。それは、よかったなあ」 「うん。めぐみちゃん、三田さんを再婚させようとしてるんだって」 「再婚?」 「彼女、小学生のとき、お母さんを亡くしてるんだ。大学で知り合った、信頼できる女の人がいるんだってさ。詳しいことはまだよく聞いてないけど、三田さんの結婚相手となると、年齢的に大学の先生かな?」 「しお・・・!」 (詩織さんのことだ!) 五郎は、思わず声が出そうになった。こんな自分は演技班には絶対入れない。 「ん? 何か言った? ゴロー」 「ううん、何も言わないよ。・・・えーと、でもさあ、進、めぐみちゃんに出会えたのは、まさに肺結核のおかげだってことだな」 「そんな言い方するなよ」 「うん。ま、お前も、明日退院だから言えるんだけど、せっかく大学に入ったのに肺結核で入院だったろ? しくじったって思う時もあっただろ? だけど、お前、入院してなかったら、めぐみちゃんに会ってないんだぜ」 「そうだなあ」 「しくじったって思ったか?」 「少しはね。でも仕方ないって思ったよ。病気だもん。入院生活は大変だったけど、ホントに仕方なかったもんね」 「お前、何だか、まるーくなったな。優しくなった、と言ったほうがいいのかな。それとも大人になったって言うほうがいいのかな」 「よせよ。まるーくなったなんて。おれはもっともっと荒々しく生きていきたいんだから。でも褒めてくれてるなら、サンキュー」 「うん。もしかしたら、そんなこんなが、進にとっての人生観のなんとか、というやつかもしれないな」 進と電話を切ると、五郎は自分の部屋へ戻った。部屋の窓を開けると、冷たい空気がながれ、オリオン座が見えた。星空は、晴れた夜空。今夜の空は快晴だ。五郎は、しばらく晴れた夜空を眺めていた。気づいたら、また菜摘のことを考えていた。不意に、憲太を思う菜摘に対する強い嫉妬の心が込み上げてきた。自分でも意外だった。 菜摘の中で、憲太のバイオリンの音色はまだまだ鮮明なのかもしれない。でもいつかは、遠い音色になる。菜摘の心も十分に癒され、すべていい思い出になるときが必ず来る。自分はどんなことがあっても、菜摘を幸せにしてみせる。誰にも渡さない。気恥ずかしくて、絶対、人に言えないそんなことを、五郎は決意を吐き出すように呟いていた。 「おい、五郎、入るぞ」 五郎の部屋に、父の大五郎が入って来た。 「ああ、父さん」 「いや、たまには息子の部屋に入ってみたくてな。母さんに聞いたぞ。成績が上がったんだって?」 「うん」 父は、五郎のベッドの上に腰掛けた。 五郎は窓を閉め、父の前に座った。床の上にあぐらをかいている。 「進、明日退院だって」 「そうかい。それはよかったな」 「あいつ、病院で彼女つくったんだって」 「ほう」 「愉快な入院生活だったみたいだよ」 「五郎よ。お前はガールフレンドはいないのか?」 「どうして?」 「いや、若者なんだから、女の子の一人や二人、たまには家に連れて来いよ。受験生だからって、勉強ばかりじゃストレスたまるぞ」 「うん。そのうち、連れて来るよ」 「彼女いるのか?」 「うん。まあね」 「ほほう」 五郎は父の顔を見ながら、得意そうに笑った。そして、朝倉夫婦の深い悲しみを思い、生きて、生きて、生き抜いて、父と母をずっと大切にせねば、とそんな殊勝な気持ちになっているのだった。 (了) |
|
|
|
映画を観終えると、人の流れのままに、五郎は館外へ出た。そして、家に帰るためにM駅へ向かった。その道で、五郎はチケットをくれた初老の男に再び出会った。男は一人ではなく、女を連れていた。 夜も遅かったが、結局、五郎は夫婦と話をすることになった。奥さんは、車を置いた駐車場へ急ぎ、初老の男と五郎が待つ場所へ来た。三人は、奥さんの運転で、距離にしてCDショップから二駅ほど離れた、静かな住宅街に着いた。夫婦の姓は「朝倉」だった。五郎は、それを夫婦の自宅の表札を見て知った。そういえば、CDショップには、「アサクラ屋」という店名がついていたな、と五郎は思った。 |
|
「上野さん、ここから家までどのくらい?」
|
|
翌日、午前九時から始まる講座に出席するため、五郎は予備校への道を歩いていた。校門に入ろうとした時、
|
|
夏休みの予備校は、さまざまな講習に現役高校生も加わり、いつもより賑わっていた。 |
|
五郎は受話器をにぎりしめ、思わずそう呟いた。 船村進から電話をもらった日の翌日、五郎は午後から予備校を抜け出して、見舞いに行った。退屈だというので、書店で面白そうな小説の文庫本を五冊買って、持って行くことにした。受付で病室を聞くと、すぐさまその室へ向かった。国立病院で少々古めかしい雰囲気があり、一部改築工事をやっている。五郎には、工事の音が病室に響くのではないか、と余計な心配が出てきたが、中へ入ると、それほど気にはならなかった。室の前まで行くと、二人部屋らしく、「船村進」の名札の上に、「三田龍之介」という名札が差し込まれていた。 五郎はノックしてドアを開けた。そして、中へ入った。しかし進の姿はなかった。主人のいないベッドが一つあって、その隣に「三田龍之介」という人物らしき華奢な男がベッドに横たわっていた。 「ああ、船村君のお友達ですか?」 三田は、新聞を見ていた眼鏡を外して言った。そして、ベッドの上に起きた。 「はい」 「船村君はちょっと散歩に行っています。もう戻ってくるでしょうから、これに掛けて待っていてくださいますか。船村君、とてもよろこびますよ」 三田は、ベッドの傍の壁に立て掛けてあった、折り畳みのパイプ椅子を五郎に勧めた。 「あ、どうもすみません」 五郎は椅子をひろげ、腰掛けた。 病室は想像していたよりも明るかった。 「・・・元気なんですね。散歩に行っているなんて」 五郎は三田に言った。何も話さずにいるのは失礼なように思えた 「船村君は元気なことは元気なんですが、やはりしっかり静養せねばならんのです。私も彼と同じ病気ですがね、ひたすら身体を休めることが大事なんです」 三田は白髪まじりの頭に手をやりながら言った。 「そうですか。散歩になんか行っちゃって・・・」 「ハハハ、実は散歩だと言いながら、病院を抜け出して、喫茶店にでも行っているじゃないですかね。ただね、この肺結核というやつは、油断して無理すると、取り返しのつかないことになりますよ。肺結核から、二次的に病状が悪化するおそれがありますからね。ま、だけど船村君は若いから早くよくなりますよ。若いっていうのはうらやましいです。彼も初めはおとなしくしておったんですよ。それが少しずつ我慢できなくなってきているんだろうね。出歩いてばかりいますよ。私には真似できません。・・・ひたすらお医者様のおっしゃることを守っていくだけです。それにしても、船村君は病人とは思えませんなあ」 三田は感心するように笑った。 「そうですね。ぼくもお見舞いに来て、本人が留守だなんて、拍子抜けしてしまいます」 「ハハハ、そうですね。だが、彼は要領がいいんだね。わりとよく眠っているし、結構食べるからね。眠っている時など、地震が起きても火事になっても絶対目覚めません、という感じで熟睡していますよ。いい青年だね。全然物事にこだわりがなくてね」 進はなかなか戻って来なかった。五郎は、しばらく三田と話しながら、進が戻るのを待っていた。 ノックの音がして、五郎はドアのほうを見た。大学生風の女性が病室に入って来た。彼女は五郎を見て、軽くおじぎをし、笑顔で三田の傍へ行った。 「ああ、よく来たね」 三田は彼女に言った。 「娘なんですよ」 五郎のほうを見て嬉しそうな顔をした。 「これ、お姉さんから」 三田の娘は、ペーパーバッグに入った荷物を一つ持っていた。 「何?」 「下着かなんかでしょ」 娘は素っ気なく言った。 「あっ、そうだ。船村君は待合室にいるかもしれませんよ。彼は小説を読むのが好きとみえて、待合室で読んでいることがありますから。だが、よく聞いてみると、待合室にいると、この病院に入院している若い女の子たちがたくさんいるとかで、そちらのほうが楽しみなのかもしれませんね」 三田が五郎に教えてくれた。娘はつまらなそうな顔をした。 五郎は待合室に行ってみることにした。ところが、病室を出て十メートルも歩かない場所で、戻って来た進に会った。進は二人の女の子と歩いていた。 「おっ、ゴローじゃないか! 来てくれたのか!」 進は病人のような恰好ではなく、TシャツとGパンにスニーカーを履いていた。女の子たちは高校生風で、パジャマの上にジャケットのようなものを着ていた。 「それじゃ船村さん、あたしたちはここで」 「また、お芝居の話、聞かせてくださいね」 「ああ、二人とも注射で泣くんじゃないぞ」 女の子たちは、行きかけて、振り向きざまに二人してアカンベーをした。それからキャッキャッと話しながら歩いて行った。何となく、学校のような病院だと五郎には思えた。進は手に小説の文庫本を一冊持っていた。 「楽しそうな入院生活だな」 五郎は皮肉っぽく言った。 「そうかあ? つまんない毎日だよ」 「何だい、あの子たちは」 「さっき初めて会ったんだ、待合室で。二人とも高校生だって」 「そうか。芝居の話なんか、してたのか?」 「ああ」 進も高校時代、ビデオ映画制作研究会に入っていた。五郎は撮影班の一員だったが、進は演技班にいて、よく主役を演じていた。 「だけど、お前、いつもそんな恰好してるのか?」 「いや、散歩に行ってたんだ。そのあと待合室で小説読んだり、さっきの子たちと話したりしていたんだ。ゴローが来るって分かってたら、じっと待ってたさ。お前、昨日の電話で今日来るなんて一言も言ってなかったじゃないか」 「それは悪かった。単なる気まぐれで来たんだよ」 「・・・ありがとう。おれも本当言うと、お前が来てくれる気がしていたんだ。でもよく考えると、お前、学校があるだろ? だから日曜日ぐらいかなと思って、即スニーカーで散歩さ。だけど、ゴロー、予備校は?」 「うん。サボった」 「ホントか?」 「本当」 「へえ、お前、成長したなあ。このバカ真面目の撮影監督さんが。偉い、偉い」 「一言多いよ」 そう言いながら、五郎は元気そうな進の顔を見て、安心していた。 進はせっかく五郎が見舞いに来てくれたのだから、このまま病院の外へ出てみようか、と五郎に言って歩き始めた。五郎は一向に構わなかったが、そんな進を見ていて、 (本当に、じっとしてなくていいのだろうか?) と今度は心配になってきた。 「ゴロー、映画、観に行ってる?」 「うん。安い名画座ばかりだけど、日曜日に行ったりしているよ」 「そうか。いいなあ。で、最近何を観た?」 「この間。『カッコーの巣の上で』という古い映画を観たよ。何かすごい衝撃を受けたよ」 「精神病院が舞台だったよね」 「ああ。観たことあるの?」 「あるよ。ゴロー、いい映画観てるね」 高校時代、五郎と進は二人でよく映画を観に行った。二人とも映画が大好きで、映画と名のつくものなら、何でも観たかった。いつか、調子に乗って、ロードショーを三館ハシゴしたこともあった。しかし、高校を卒業してからは、五郎と進はほとんど会わなくなった。進が大学に入学し、五郎が予備校に通うようになってからは、ぷっつり会うことがなくなっていた。 二人は、進が時々行くらしい、LEOという喫茶店に向かって歩いていた。明るく自由な感じでいる進だが、入院生活では様々に抑制を強いられているようだった。歩き始めてから、やけに饒舌なのだ。 二人はLEOに入った。新しくきれいな店だ。 「勉強の調子はどうだい?」 「うん。何とかやっているよ」 「古文の成績、少しはよくなったか?」 「相変わらず、かな」 五郎は苦笑した。 「そうだろうな」 「何だい、その言い方。こういうときは励ますものだろ?」 「ゴローに古典文法は無理。めちゃくちゃだもん。せいぜい英語で稼ぐんだな。お前、英語はましだから」 「冷たいやつだなあ」 「違うよ。こういう一見、突き放したような言い方をして、ゴローをよい方向へ導いてやってるわけさ。感謝しろよ。親友だからこそさ」 「もっと心温まる親友がほしいよ」 そう言いながら、五郎は、 (こんな会話、久しぶりだな) と思った。心地よい気分を味わっている自分に気がついた。予備校には進のような親友はいない。 「入院した日、診察で、先生がこう訊いたんだ。『君の趣味は何だね』って。で、『映画観ることです』って言ったんだ。でもそのあとが悪かった。『そうか、映画が好き、か。映画がねえ』だってさ。『仮に入院中に外泊許可が出ても、映画館はダメだよ。退院してもしばらくはおとなしくしてなきゃいけない』って先生に釘を刺されちゃったよ。ほら、映画館ってよく考えると空気のきれいな場所じゃないだろ。時々タバコ吸う不届き者もいるしね。・・・入院生活スタートにして、大ショックだったよ。そんなに大変な病気になったのかな、と不安にもなったよ。だけどもう二ヶ月めだろ、たった一日でも病院の中じゃ長く感じられるんだ。毎日ベッドの上にいると、重病人になっていくようで、本当はすごく恐かったんだ。『カッコーの巣の上で』じゃないけれど、医者の言いなりになって、病院の中に閉じ込められているような毎日が苦しくなっていったんだ」 進は、ホットミルクを飲みながら、訴えるように言った。 「何だい、被害妄想的だなあ、進。患者さんたちは厳しく管理されているわけでもなさそうだし、それは単なるわがままだよ。入院は病気を治すためのことなんだから」 五郎は、アイスティーを一口飲んで、言った。 「お前だって、入院生活を送ってみたら、分かることさ。好きな映画も観に行けない生活なんだぜ。もちろん、おれだって死ぬのは嫌だから、医者の言うことはちゃんと聞いているよ。だけど普通にしていたいんだ」 「だからTシャツにGパンでスニーカーってことか? 気持ちは分かるけど、病状が悪化しても知らないぞ。それに早く治さないと、来年も大学を休学なんてことになるぞ。それと、お前、劇団に入って芝居に磨きをかけるって、前に言ってたけど、それだって夢の夢になっちゃうぞ」 「ああ、分かってるさ。言ったろ。医者の言うことはちゃんと聞いているって。でも自分では本当に元気なんだぜ」 「それはよく分かるけどさ」 「心配するなよ」 「うん。分かったよ」 五郎は苦笑加減に言った。 「映画の話でもしてくれよ」 「・・・お前、本当に映画、観たいんだな」 「ああ、観たい。DVDもいいけど、やっぱり映画館だよ。コメディーが観たいなあ。あの爆笑のどよめき。思い出しただけでもワクワクしちゃうよ」 「進・・・」 五郎は、このまま進を連れ出して、思う存分、映画を観せてやりたい衝動に駆られた。しかし、そんな映画のような大胆なことは、決して五郎には出来るものではなかった。やはり進の身体が心配だ。いま病院を抜け出して話をしている最中でさえも、五郎は進の身体が気になって仕方がない。 「・・・まあ、我慢することだな、映画館は。そんなことより、模範的な患者になって早く退院することだよ」 「努力するよ」 「バカに神妙だな」 「たまには、ゴローの言うことも聞かなきゃな・・・。それより、お前、彼女は出来たのかい?」 瞬間、菜摘の顔が浮かんだ。五郎は進にも誰にも、菜摘のことを話したことがない。 「突然何の話だよ。変なこと訊く奴だなあ」 「ま、ゴローには彼女は出来ないな。女性に対して、内気なゴローちゃんだもん」 「うるさいなあ。いまのおれは勉強一筋だよ。そんな暇はないよ。あっ、そうかあ。お前、彼女出来たんだな」 「まあね。相変わらずおれはモテモテだよ」 「その言い方は、彼女いないってことだな」 五郎は笑って言った。 「お前はとことんひねくれてるなあ」 「お互い様さ」 「・・・いいなあ、と思う人がいるんだ。あれっ、おれ何でこんな話、ゴローにしてるんだろ。もうやめとこう、この話は」 「聞きたいなあ」 「いいよ。お前、もう帰れよ。勉強一筋なんだろ?」 「言いかけたことは聞かせろよ」 「恥ずかしいから、いいよ」 進は本当に照れていた。 「・・・じゃ、帰るとするか。あっ、そうだ。本を持って来てたんだ」 五郎はバッグの中から、予備校の近くの書店で買った五冊の文庫本を取り出して、進に手渡した。 「おっ、サンキュー。あれっ、これほとんど読んじゃったよ。お前が選んだのか?」 「そうだけど」 「あーあ、お前とおれの趣味は同じか。あー嫌だ」 「嫌ならいいよ。持って帰って読むから」 五郎は膨れっ面をしながら、進の手から文庫本を取り上げようとした。 「あ、ゴメンゴメン。二冊だけもらっとく。読んでない本だから。これ、読みたかったんだ。・・・おいおい、そんな嫌そうな顔するなよ。心の中では感謝してるんだから。あ、そうだ。ゴロー、これ持って行かないか? おれが読んだやつだけど、もう読んじゃったから」 進は、待合室で読んでいた小説を五郎に差し出した。 「読んだやつでゴメン。けっこう面白かったよ」 「そうか。じゃ読ませてもらうよ」 「うん。この三冊もよかったぜ」 進は五郎が持って来た、残りの三冊を差し出して笑った。 「ああ、読むよ」 二人は、LEOで一時間近く話した。そして、時々病院へ進の顔を見に行くことを約束して、五郎は帰途についた。 |
|
大槻五郎の家の前には、コンビニと郵便局が並んでいる。五郎の母などは、それをとても便利だと喜んでいる。しかし、いまの五郎はコンビニはともかく、家の前の郵便局をまず利用しない。郵便局へ行く必要のある時は必ず上野菜摘のいる郵便局へ行く。いや、無理に用事を作ってでも、五郎はあこがれの菜摘が勤める郵便局へ足を運んでいる。 |