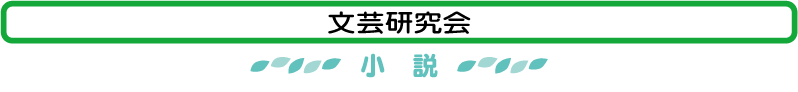| 私淑の人 |
|
タイトル
|
作 者
|
投稿日 |
| 私淑の人(7)完 | 後藤 雄二 | 2009.10.1 |
| 私淑の人(6) | 後藤 雄二 | 2009.9.1 |
| 私淑の人(5) | 後藤 雄二 | 2009.8.8 |
| 私淑の人(4) | 後藤 雄二 | 2009.7.11 |
| 私淑の人(3) | 後藤 雄二 | 2009.6.9 |
| 私淑の人(2) | 後藤 雄二 | 2009.5.15 |
| 私淑の人(1) | 後藤 雄二 | 2009.4.1 |
| 私淑の人(7)最終回 | |
| 後藤 雄二 2009年10月1日 |
|
|
崩れかけた塀の内の大きな一本の百日紅、これがわが家の目印なのであるが、老いて虫にやられた為か、最近では花はもう殆ど咲かない。初めて京都に移ってこの家に入ったのが昭和二十六年の五月だったからざっと三十年前のことになるが、その頃は毎年夏になると純白の花が溢れ咲き、それはもう清冽な泉が空に噴き上げていると思うばかりであった。 これは二回生の夏に読んだ「星に想う」という題の吉沢先生の随想だ。新平はそれを思い出していた。しかし、さっと通っただけなので、百日紅の木があるのかどうかよく分からなかった。先生が昔、吸い込まれるように銀河を見上げ、時によろめいたのはあの家の前なのだな、と考えていると、新平は笑みがこぼれた。 三月初旬、大学で卒論の口頭試問があった。卒業試験だ。国文学科の卒業予定者は二十四名。そのうち、新平が知っている人は、純と節子と光村知子の三名だけだった。 口頭試問も終わった。新平は少々気が抜けたような、それとはまた別に充実感を抱くような状態で帰宅した。新平宛の郵便物が届いていた。それは三カ月ほど前、新平が履歴書を送った映画会社からの封書だった。大学を卒業することが出来たら、東京へ行こうと新平は決めていた。東京で働いて、小説の勉強をしたいと思っていた。ものは試しで、東京の映画会社に履歴書を送った。映画への思いを文章にしたものも同封した。その返事が届いたのだった。書面には、 翌日の朝、新平はとなり町へ出かけるかのように、家族と別れ、家を出た。弟がバス停まで見送ってくれた。大きなバッグひとつだけの旅立ちだ。 (了) |
| 私淑の人(6) | |
| 後藤 雄二 2009年9月1日 |
|
|
新平は書のことなど何も知らなかった。沢山の作品を説明してもらったが、新平は調和体の作品はどれを見ても気に入った。ふとその中に目を見張る作品があった。「吉沢一郎のうた」と題した調和体の書だ。先生の歌がこう書かれてあった。 身に沁みて淋しと思ひ寝ねしかど 「なんとなく、汚い歌でしょう?」 新平は卒論の題目を「木山捷平の研究」とした。吉沢先生は近世文学の教授だったが、希望する指導教授の欄に新平は「吉沢一郎先生」と書いて提出した。ダメでもともとだと思っていたら、二月のある日、吉沢先生が卒論の指導教授に決定した旨の通知が届いた。新平は最高に嬉しかった。 六月の教育実習が済み、夏が来ると、四回生の夏期スクーリングが始まった。教育実習には、三人それぞれ母校の高校へ行った。新平と節子は教師になろうとは考えていないが、教職科目も勉強しておきたかった。純は七月の京都府教員採用試験を受験して、スクーリングに参加した。 この夏のスクーリングは、昨年ほどの新鮮さが新平には感じられなかった。もしかしたら、新平は酸いも甘いも知りつくしているような顔をしているのかもしれない。 わが側に花瓶の花を素描する 「家内は私のことを若い若いと言うんだ。だからどこへ行っても年齢は白状しないように、と言われているんだよ」 四回生の夏のスクーリングが終わると、新平はとにかく卒論の草稿を書きはじめた。純は教員採用試験の一次にパスした。その通知が届いた日に、新平の小説が載っている文芸研究機関内発行の雑誌が送られてきた。新平は二十冊注文した。節子は、二月の大学院入試の受験勉強に励んでいた。 |
|
吉沢先生とは一時間も話した。 秋になった。この秋には洛北大学の公開講座がある。今回は講師六人のうち四人が国文学科の先生だ。吉沢先生もそのひとりだ。 五回目の講座は和歌文学の先生の講義だった。新平と純と節子は、毎回出席している。 十一月の大学祭に新平と純と節子は初めて出かけた。吉沢先生の研究室でココアをごちそうになったとき、先生は新平に大学祭のパンフレットをくれた。三人でそのパンフレットを見ていた。模擬店の案内のページの「国文学科有志」とあるところには、赤のボールペンでしるしがつけてあった。吉沢先生がしるしたのだろう。いい先生なんだな、と新平は思った。 |
|
新平たちは、ダンスが上手くて首にレイをかけられたわけでは決してなかった。赤ん坊を抱いたこの一回生の女性のことがほほえましくて、新平たちにレイをかけてくれたのだろう。 後半の講義と試験が済むとスクーリングはおわった。学生たちはそれぞれの職場に戻る。 アルバイトはたまたま二日間休みだった。翌日、新平はやけに早起きだった 人物であれ作物であれ、 新平の心の中にすでに刻みこまれている先生の言葉だ。最後に先生の名前が書いてある。その色紙を見て、新平の身体の中は感激でひどくつっぱったような状態になった。 |
|
新平は、講義をする先生をみていて、先生は西鶴のことが好きで好きでたまらないんだな、とつくづく思った。そして先生のことがとても羨ましくなった。西鶴のことをあれほど情熱をこめて語れるなんて、と思った。 前半の講義と試験が済み、スクーリングに慣れてきた土曜日のことであった。授業は午前中でおわった。午後からは四回生の代表が卒論の研究発表をする会が催された。国語学、上代、近代の三人の四回生が研究の成果を披露した。 新平と純と節子の三人が夏期スクーリングに参加した年は、洛北大学に通信制がおかれて三十周年の節目であった。 |
|
二回生の後期日曜スクーリングは、英語二科目とフランス語二科目の計四科目だった。純と節子は、四科目ともストレートに合格した。しかし、新平は英語一科目しか合格できず、残りの三科目は再試を受けて何とか単位をとることができた。 三回生のスクーリングは夏期を選んだ。それは昨年の夏期スクーリングに一日だけ参加した新平がそのときに決めていたことであった。二回生のための卒論指導会が一日だけあったのだ。純と節子は参加しなかった。 |
|
新平が木山捷平を読もうという気持ちになったのは、ひょっとしたら単なる偶然なのかもしれなかった。新平は二十一歳になっていたが、それまで多くの小説を読んできたわけではなかった。いくつかの小説は読んだには読んだが、それらは大した感動を新平に与えてくれたわけではない。そのなかにはすぐれているとされている作家の作品もあった。しかし傾倒できる作家に出会うことはなかった。それは新平がひとりの人間として、まだまだ若かったことにも原因があったのだろう。 二回生の秋から冬にかけて、新平は木山捷平のいくつかの作品を読むことができた。 |