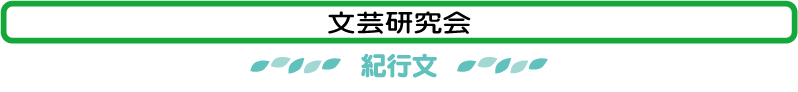| タイトル | 作 者 | 投稿日 |
| ブリスベン滞在経験(8)<最終回> | 佐藤ひろ子 | 2011.6.8 |
| ブリスベン滞在経験(7) | 佐藤ひろ子 | 2011.6.8 |
| ブリスベン滞在経験(6) | 佐藤ひろ子 | 2011.6.8 |
| ブリスベン滞在経験(5) | 佐藤ひろ子 | 2011.6.8 |
| ブリスベン滞在経験(4) | 佐藤ひろ子 | 2011.5.25 |
| ブリスベン滞在経験(3) | 佐藤ひろ子 | 2011.5.25 |
| ブリスベン滞在経験(2) | 佐藤ひろ子 | 2011.5.25 | 地を走る"はやぶさ"初乗記 | 大木陸夫 | 2011.6.2 |
| ブリスベン滞在経験(1) | 佐藤ひろ子 | 2011.5.25 |
| ミレー館を訪ねて | 吉原 司郎 | 2010.2.7 |
| 『出雲国風土記』を訪ねる旅(4) | 大木 陸夫 | 2007.8.20 |
| 『出雲国風土記』を訪ねる旅(3) | 大木 陸夫 | 2007.8.9 |
| 『出雲国風土記』を訪ねる旅(2) | 大木 陸夫 | 2007.7.4 |
| 『出雲国風土記』を訪ねる旅(1) | 大木 陸夫 | 2007.6.29 |
| 利尻とウニ | 今泉 みゆき | 2007.5.25 |
| ブリスベン滞在経験(8) | |
| 佐藤ひろ子 2011年6月8日 |
|
|
14) Zoos オーストラリアでは動物園の入場料が日本と比べると、とても高いです。 マディーはダンスの好きな、オシャマな女の子です。 次の土曜日、お弁当・おやつを持ってピクニック気分で動物園に出掛けました。
オーストラリアはどこの動物園でも、10ドルぐらいの料金でコアラを抱いて記念写真を撮ることが出来ますが、ここでは、抱けません。しかし、低いユーカリの木にしがみついて居るコアラを無料で触ることが出来ました。こんなことは他ではありません。 ショウの合間にお昼を食べたり、おやつを食べたり、一日中ここで過ごしました。 園内はきれいに清掃され、飼育員は皆かなりの知識を持っており、丁寧に動物の世話をしていたのが印象的でした。 15) Halloween
こちらでハロウィーンを祝う習慣は、アメリカの様にメジャーでないそうですが、楽しいことの好きなシャロンはご近所様と計画しておりました。 ☆ Brisbane ブリスベンの街には黒い人、白い人、黄色い人と様々な人が住んでいます。 こんなに多くの移民・難民を受け入れて大丈夫なのかと思いますが、コミニティーセンターに通ってくる人には定住の為のトレーニングも有りますし、各種年金も出て、特に仕事が無くても困っているようには見えませんでした。 それでも最近は市民としてふさわしいかどうかを審査するために、2007年より市民権テストが導入されたそうです。 また永住権(こちらは、選挙権がありません。)も、オーストラリアに役に立つ人かどうかの立場から、専門的な技術を持っている人に多くのポイントが与えられ、次いで年齢、英語が話せるかなどでポイントが課せられ、合計で120ポイントの条件を満たさないとビザの申請が出来なくなったそうです。インターネットでユーチューブ・ブリスベンを検索しますと、もっといろいろなブリスベンの情報が動画で得られますので、試してみて下さい。
☆ In conclusion ☆ 若い頃から待ち望んでいた長期海外滞在でしたが、ここで学んだことは、当たり前の事なのですが、「どんな国に住んでも、自分の国の歴史や文化を理解しておく」 昔から、なんとなく、との漠然とした思いで海外生活を実行した私は、せっかくのこのチャンスを半分以上無駄に過ごしてしまったと、今は後悔しています。 とは言え、この経験から得たものもありました。 そのひとつは、"NVGほどがや"(日本語ボランティアグループ)に所属し、日本語指導の勉強をさせて頂きながら、教室で外国人に日本語を教え始めました。 放送大学に入学して2年が経ちます。ようやく学ぶ目的が見えてきました。 ☆☆☆ 最後に ☆☆☆ 今回のテーマ「ブリスベン滞在経験」の副題に「A present from my husband」とつけさせていただきました。理由は、夫が亡くなる前の月に、病床の彼が私にあるプレゼントをくれました。 彼の貯金通帳です。 共働きだった私達は、生活に必要な経費をお互いに出し合い、残りの分は各自に貯金をしておりました。 どうして?と不思議がる私にニコニコしながら、これまでの私への御褒美だというのです。 そして、「これが僕に出来る、君への最後のプレゼント。このお金と僕の退職金で君の大好きな海外旅行に、世界一周の旅をして」と。 そう言う訳で、このブリスベン滞在も、彼からのプレゼントの一つでした。 夫は最後のプレゼントと言いましたが、彼からの旅のプレゼントはまだまだ続いております。 | ||||||||||||||||||
|
長い間、私の拙い文章を最後まで読んでいただきまして、本当に有難うございました。 (了) |
||||||||||||||||||
| ブリスベン滞在経験(7) | |
| 佐藤ひろ子 2011年6月8日 |
|
|
12) Their children デイビス家の3人の子ども達は、10歳の男の子レンジー、9歳と7歳の女の子ケイトとマディーです。 デイビス家は表通りに面して前庭、母屋(二階建て)、裏庭(デッキになりましたが)、プール、そしておばあちゃんの家と庭の縦長の作りです。 サムはあまり散歩に連れて行ってもらえず、前庭からグランマの庭まで毎日フラフラとしていますので、前庭にも、通路にも、グランマの庭にも糞をします。
シャロンは「雨の前兆だから」と驚く様子も有りません。その内にいなくなると言いました。 皆、何でも、気にしないのです。蚊やアリに刺されて大変だったのは私だけの様でした。 ハエ取りは日本と違いランタン(手さげランプ)の形をしており、中に少し水を入れると魚の腐ったように臭いが発生し、ハエを誘います。 中に入ったハエは水におぼれたり、一度入ったら出てこられない仕組みになっていて、度々水を入れ、(大型のジャムの瓶ぐらいの大きさ)瓶口まで一杯になるまで使います。 日本の昔の天井から吊るすハエ取りも私には不気味でしたが、これまた不気味で、でもここで生活するには無くてはならないものでした。 子供達は活発で(近所の子供も)、家・庭は裸足で歩きます。普段、隣近所に行くのも裸足です。怪我をしないかと心配でした。ある日、マディーがガラスの小さな破片を足に刺し泣いて帰って来たことがありました。(やっぱりねぇ〜。怪我しない訳ないよねぇ〜!) オーストラリア人の多くは裸足で居る人が多いそうです。 ブリスベンではすごく太くて大きいのに地面からすぐに登れる形の木が多く、子供たちの恰好の遊び場になります。 デイビス家では週に3,4回はレンジーとケイトが学校のお弁当を作り、残りの日を母親のシャロンが作っていました。 ある日、隣の家に行くから飲み物を持って一緒に来いとチャックが言うのでついて行くと、近所の大人達がリビングに集まっており、小劇場の様に椅子を並べて座っていました。 子供達は家で仕事の役割分担はあるのですが、食器をしまったり、テーブルの用意をしたり、生ごみを堆肥作りの箱に捨てに行ったり、でしたね。 宿題のある時は朝食後にしていました。 13) Their elementary schooly 子供達の通う州立Sun Smart schoolは母親シャロンのレストランの近くにあり、家から車で7,8分の所にありました。 小学校は1年から7年生まで。8年生から12年生まではハイスクールになります。 デイビス夫人に「小学校の授業が見てみたい」と話したところ、すぐに「いいですよ」の返事をいただきました。 州立のこの小学校は日本の様に教科書はなく、教師が各々授業計画を立て教材を用意します。 この日は、3人の子供のクラスを30分位ずつ見学させてもらいました。
ストローを使い仮説を立てて、そのストローをどの様に組み立てたら頑丈な橋が出来るのかと、グループ毎にお互いの考えを述べあい、ノートしながら橋作りを進めていました。 重りを載せてどの程度まで耐えられたか、つぶれると何が原因だと思うか等検討させる物理の授業です。 ブリスベンには幾つ橋があり、何故橋が必要だったのかと、社会科の授業にもなります。 1年生のクラスでは5人位に一人の先生が付き、グループで勉強していました。 一つのグループはパソコンの練習です。 この小学校は朝の9時から始まります。 その後また一時間の授業があり、ランチタイムです。 クラブ活動は基本的に週一回で、朝の7時半から希望者だけが受けます。 オーストラリアでは(イギリスもそうでした)、12歳までは保護者が学校への送り迎えをする義務があります。 オーストラリアでは5年生から外国語の授業があり、この学校では日本語でした。 ここでは私の滞在中に洲が主催する日本語スピーチコンテストがあり、校長先生からそのお手伝い依頼と、コンテストへの招待を受けました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今回はここまでです。次回が最終回となります。おたのしみに |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリスベン滞在経験(6) | |
| 佐藤ひろ子 2011年6月8日 |
|
|
11 ) Homestay with an Australian family 日本に戻る少し前、ゲイの彼らの生活はやっぱり普通のオーストラリアの生活と違うなと感じた私は、コミセンで知り合った千織さんにどこか私を受け入れてくれるオーストラリア人の家庭を知っているか尋ねておりました。
私はこの連絡先にメールでコンタクトをして、ナンダから電車で約15分のサンドゲイト(Sandgate)の、子ども三人、おばあちゃん一人、犬一匹の家庭、デイヴィス家にホームステイすることが決まったのです。
2度目のステイの1週間後、デキソン・ヨシエさんがデイビス家に案内してくれる為、私をB宅に迎えに来てくれました。 私を部屋に案内し、奥様と面会した後、ご主人のチャックが子供たちを含め私のランチを作り始めました。 私に与えられた部屋は、ご主人チャックの母親が使っている離れ家でした。 翌朝起きてキッチンに行きますと、だいたい皆はトーストとミルクかコーヒー・紅茶での朝食でした。
彼は休み中、母屋とプールの間の15、6畳位の土地をウッドデッキにする大工仕事をしておりました。 こちらでは家庭を持つ男性の多くが大工仕事をよくやります。 プールを作るため、大きな穴が掘られていました。 「どこで勉強したのですか」と聞けば、「勉強なんかしないよ」と大笑いです。 後でオーストラリアに詳しい日本人にこの話をしましたら、オーストラリアでも大工さんは居るけど技術は素人に毛が生えた程度の人が多く、また工賃はとても高いのだそうです。 ホームステイして5,6日後、デイビス家はいつもの生活に戻りました。 ホームステイをして2週間もしない内、朝起きてキッチンに行くとチャックが左腕に包帯を巻き腕を首から吊っていました。 デイビス家では毎週火曜日の夜は夕食前に全員でスイミングプールに泳ぎに行き、そちらでお仲間と食事をして午後9時頃帰って来ました。 という訳で、その後片手で料理をするチャックのお手伝いを、申し出た訳でも無いのですが私がする様になってしまったのです。
このステイで、オーストラリア人の食事は質素だとわかりました。 火曜日は全員でスイミングプールに行くため、その日の私の夕食は冷蔵庫の物になります。 BとDも朝はトーストかシリアルとミルクまたは紅茶で、二人とも私が起きる6時半頃には出掛けておりました。 しばらくして私は、美味しいステーキやDの作るラムチョップが恋しくて、午前中が英会話クラス、午後がガーデニングクラスのある木曜日はナンダのBの家に泊まって翌日サンドゲイトのデイビス家に帰る様になりました。 デイビス家から歩いて5分もするときれいなビーチに着きます。 海岸線に沿って沢山の公園や、バーベキューの設備があります。(無料です) 大変遠浅の為、潮の満ち引きでガラリと風景が変わります。 ショーンクリフからサンドゲイトまでは歩いて約25分。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今回はここまでです。次回もおたのしみに |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリスベン滞在経験(5) | |
| 佐藤ひろ子 2011年6月8日 |
|
|
My second stay in Brisbane ( from September 12th to December 7th ) 10 ) An unexpected incident, again ! このテーマの前に第二回目のブリスベン訪問の日の国民的なイベントを紹介したいと思います。 2度目訪問当日がブリスベンリバーフェステの日であるとBから連絡があり、その日はそのブリスベンリバーサイドにホテルを予約し見学することになりました。
花火大会のオープニングは6機の戦闘機のアクロバットで始まりました。みんなの大歓声。
10) のテーマに戻ります。 予期せぬ事件が、また起こりました。
今回は歯です。
「歯の治療は、保険に含まれておりません」の声に、またもやガ〜〜ン! 海外での病院の治療費はものすごく高いとのイメージいっぱいの私は、必死で事情説明をしました。
Dの掛かり付けの歯医者に予約してもらい、二日後に治療を受けました。
面白かったのはこれからです。
日本では絶対にありえない事です!
| ||||
|
今回はここまでです。次回もおたのしみに |
||||
| ブリスベン滞在経験(4) | |
| 佐藤ひろ子 2011年5月25日 |
|
|
7) Nundah Community Center 私は毎週火曜日と木曜日の午前中10時から12時まで、インターネットで調べておいたナンダコミニュケーションセンターの英会話クラスに参加しました。
日本の様な日本語ボランティア教室とは違い、系統立てて英語を教えるというのではなく、集まったボランティアの先生がその日教室に訪れる学習者を相手に当番で時間を決め、当番になった先生が自分の好きな様に好きなことを教えるといった雰囲気でした。 先生が多い時は、ほとんど英語が話せない・書けない人のクラスと普通に話が通じるクラスとに分け、先生のつくったテキストでの授業がありましたが、4回に1回ぐらいでしたね。
11時になると約10分間のティータイムです。
ガーデニングクラス
ガーデニングクラスは募集をしたばかりでメンバーはボランティアを入れて5、6人でした。
ナンダコミュニティーセンターは英会話やガーデニングの他に、子育て支援事業、パソコン教育、移民者の就職研修指導、アート教室・各レクチャー等も行っており、このような内容でその他のどのコミニュティーセンターでも行われているようです。
エコの話.雨水タンク 昨年から今年にかけてブリスベンは大洪水災害に見舞われましたが、その前までは干ばつでした。特に私が行った前の年2006年、2007年は公園の池の水が干上がり池の魚を別の場所に移したり、田んぼが乾いて穀物が出来なかったりで大変だったそうです。
8)Library コミセン(コミニティーセンター)に行かない時は、ナンダにもありますがそれ以外の各地域にある図書館にも足を運びました。
またどの図書館にも毎日の様に、年齢別で子どもの為のストーリー・タイムがあります。 やはりバスで15分ぐらいの所にあるハミルトンの図書館でも、有閑マダムが外国人の為に英語タイムを設けておりました。 9)Beaches and stars in the sky オーストラリア大陸は海岸線が5万キロに及び、その沿岸に一万以上のビーチがあるそうです。そしてこの国の人口の約85%が海岸線から50km以内に住んでいるというのです。 ブリスベンの人達はビーチがあるのが当たり前で、毎日の生活に浸透しています。 オーストラリアと言ったら、星は南十字星ですよね! 短歌の先生に指導を受けて、南の国の感動を歌にしてみました。
オーストラリアの国旗の星は、南十字星をかたどっています。 | ||||||||||||||||||||
|
では、次回もおたのしみに |
||||||||||||||||||||
| ブリスベン滞在経験(3) | |
| 佐藤ひろ子 2011年5月25日 |
|
|
6) The life I longed for in Brisbane, not as a "tourist" and the reality こうして、ただのツーリストでない待望のブリスベンでの生活が始まりましたが、その現実は楽しいものばかりではありませんでした。 例えば掃除・・ 掃除機は小型耕耘機の様に馬鹿でかく、小回りが利きません。 例えば洗濯・・ 大男二人の 山のような洗濯物。(本当に山になっていました) ゆえに、パンツ・靴下・シャツ・ズボン等彼らの衣類の数は半端じゃありません。 例えば料理・・ 毎回毎回、日本食のリクエスト。 黙って洗濯物をたたんだり、料理を作っていると私を「シューフー」「シューフー」とニコニコしながら言います。 結局、私も居候のような立場でもありますので週に3回は彼、2回が私、土日がBの夕食当番という事でお互いに納得と相成りましたが、Bはレストランからのテイクアウトとピザの配達を頼むことが多かったですね。 例えば後片付け・・ 全自動食器洗い。 オーストラリアのアリの多さは皆さんには想像出来ないと思います。
猫のザールはネズミ、カナヘビ、ポッサムの子どものようなものを捕まえては得意げに家に持って帰ります。 ごみの回収は週に一度。 家の外に大型の生ごみ用とリサイクル用のコンテナーが各家に配布されています。 上記の状態なので当たり前と言えば、当たり前ですが、彼らの家の生ごみコンテナーの中には蛆が湧いていました。 吐き気を抑えて殺虫剤を振り撒き、一晩おいて洗浄しました。 Bに言うと、いつも夏になるとそんなことがあり、業者に頼んで洗浄してもらっていたそうです。 家の中の掃除も階段から二階の絨毯のクリーニングを含めて、私が下見に行った9月とステイが決まった4月に業者に頼んで綺麗にしたそうです。 そんなことって、あり・・・・・・? 例えば・・・3人の会話 Riceはロースと聞こえます。 意味不明でスペルを聞けば・・・ 人の事は言えません。私の英語も日本語英語の発音でなかなかオーストラリア人(地元の)にわかってもらえませんでした。 AもBも、「Dの英語は現地訛りが強いので自分たちにもまだ解らないことがあるからHIROKOは気にしなくてもいい」と慰めてくれましたが、「言われたことが解らない、言ってることが解ってもらえない」と自信喪失になり、失語症状態も現れ泣いたこともありました。 でも、やはり言葉も習うより慣れろで、2回目のステイの時はお互いの努力もあってか楽しく生活が出来るようになりました。 | ||||
| 第3回はここまでです。次回もおたのしみに | ||||
| ブリスベン滞在経験(2) | |
| 佐藤ひろ子 2011年5月25日 |
|
|
4)The night before my departure 出発前夜の出来事です。
翌朝、病院に行ってレントゲンを撮ると10番目と11番目の2本の肋骨が折れていることが判りました。
家に戻りその事をAに話すと「じゃ、行けるのね!」と喜びの表情!
ジェットスターというのは、JALやカンタスと違ってすごく安いチケットが買える航空会社です。
その上機内でのサービス(飲み物、食べ物、ビデオ、旅行ケースの持ち込み条件)などを自分で選ぶことが出来るため、それがチケット代に跳ね返りより安い選択が出来ます。
でも買ってしまったチケットは、払い戻しが効きません。 痛み止めを飲み、コルセットもしてしばらく横になっていた私は真夜中の痛みも少し和らいでいて、結局断れない性格があだになり、パスポートなど貴重品を入れた小さな肩掛けバックのみ持って、その夜の便で予定通りJを連れてブリスベンに行くことになりました。
旅行カバンはA家族とJが成田まで運び、ブリスベンでは空港のスタッフにお願いして手伝ってもらいました。 (Aは日本に来た時、まだ日本人の恋人Tと結婚していませんでした。 5)Welcome dinner with my friends 私の友達、Bはゲイです。 私とBが知り合うきっかけとなったのは「おばさん英会話」です。 月に一回「外国のお惣菜」と称して日曜日に料理好きな親しい知人達と、息子の家庭教師だった横浜国大の大学院生を通して留学に来ている各国の外国人を紹介してもらい料理教室を我が家で開催していた時です。 それから生徒探しのビラを作り、団地のポストに配りました。 英会話を続けたい私は引っ越した後も、次に来るAETをキャシーに紹介してもらい、今度は土曜日の午後1時から3時までの2時間、新しく友人仲間を募って始めました。 話を元に戻します。 Dは食べることが大好きな大男で、大食いです。
| ||||||||||
| 第二回はここまでです。次回からはブリスベンでの生活が始まります。 | ||||||||||
| 地を走る"はやぶさ"初乗記 | |
| 大木陸夫 2011年6月2日 |
|
面接授業 「縄文文化の扉を開く」 青森学習センター この面接授業を受けたい理由の一つは、三内丸山遺跡の発掘、調査、保存と展示などに関わってこられた岡田康博先生の講義だということです。三内丸山遺跡は国特別史跡です。特別史跡とは、「史跡のうち学術上の価値が特に高く、わが国文化の象徴たるもの」つまり、特に重要なものとみなされ、日本文化の象徴と評価されるものが特別史跡です。縄文時代の国特別史跡は、三内丸山遺跡、秋田県の大湯環状列石遺跡、長野県の尖石・与助尾根遺跡の三ヶ所です。三内丸山遺跡現地での授業は以前から受けたいと考えていました。もう一つの理由がはやぶさに乗車することでした。私は東北新幹線の新青森までの開通を機会に面接授業の科目登録申請をしました。 | |||||||||||||||||||
はやぶさ501号 東京発(08:44)10号車 6番A席[グランクラス] 新青森着12:49
5月13日、はやぶさ501号は東京駅を定刻に発車しました。東北新幹線は2011年3月5日に新青森駅まで開通しましたが、一週間後の11日に東日本を襲った大地震で駅舎などに損壊があり運行出来なくなってしまいました。4月29日から、はやぶさは一日一往復だけの営業で再開されました。 はやぶさグランクラスはJRでは初めてのいわば新幹線のファーストクラスです。シートは3席6列、私は1席側に座った。座席はリクライニングで最大45度まで倒すことができ、後部座席には影響しないもので、自在に角度を変えられる読書灯、アテンダントコールボタンがあり、テーブルは肘掛部分から引き上げ二段階に広げられるものでした。スリッパも用意されています。
時速300キロは体験できませんでしたが、はやぶさは快調に走り、新青森駅には定刻に到着しました。新青森駅は青森市西部にあって、周辺はまだ建物はなくレンタカーの店が目につくだけです。駅中のお店やレストランの様子などを見てから、ニコニコレンタカーのあるイェローハットの看板目指して駅前開発地の中の道を10分ほど歩いて行きました。ニコニコレンタカーは、最近横浜市営地下鉄の車内広告で料金が2525円と出ていたのでネットで検索し予約したものです。会員登録すると6時間2100円で借りることができました。 小牧野遺跡(ストーンサークル) 青森に来たら必ず訪れる場所があります。小牧野遺跡です。レンタカーで行くことにしました。市街地にある森林博物館にこの遺跡からの発掘遺物の展示があるので、まず立寄りました。土器、石器、土偶はもちろんですが、三角型岩版というものがあります。それは、泥岩や凝灰岩を用いて、表面は亀甲状等の模様が彫られており、裏面は平滑だという。岩版が出土する遺跡は環状列石(ストーンサークル)の場合が多いとある。小牧野遺跡はまさに環状列石の遺跡です。森林博物館に隣接している青森市教育委員会文化財課を訪ね、資料などを頂くことができました。
そして、14日、15日の面接授業が三内丸山遺跡縄文時遊館で行われました。 (完)
|
| ブリスベン滞在経験(1) | |
| 佐藤ひろ子 2011年5月25日 |
|
|
My stay in Brisbane (A present from my husband) Introduction The year in 2009 was special for me, because I went overseas on a few trips.
イントロダクションです。 2009年は私にとって特別な年でした。
My stay in Brisbane 1)Why Brisbane, not other countries ? オーストラリアにはそれまでに何度か行ったことがありましたが、この憧れの海外生活の始まりのきっかけは2008年の1月、親しいアメリカ人Aが我が家に泊まりに来ていた時です。
我が家にはミミという13年前に息子が拾ってきた猫がおります。
そのAが2007年の夏に我が家に来た時、「HIROKO、私は来年1月から日本に来て住むつもりだから、ここに住んで、ミミの面倒をみてあげる。だからひろ子はその1年間、どこでも好きな所に行って来ればいいよ。その代り家賃はなしでいいかな?」という話を持ち出し、私も「家賃はいらないけど日本で仕事が見つかったら、自分たちで使う公共料金くらいは払ってね。」と交渉が成立して、私の海外旅行計画は始まりました。 海外生活は英語圏でと決めていましたので、選択は知り合いのいるイギリスのロンドン、アメリカのシカゴ、そしてオーストラリアのブリスベンとなりました。 イギリスは以前に1週間程ですがストラットホードの田舎にホームステイをしたことがありましたし、ロンドンの郊外の知人の家に泊めてもらったことも有ります。シカゴも友人宅にお邪魔して、どちらも車がなければ快適な生活が出来ないことを認識していましたので、知っている道と自分の車でなければ運転出来ない私は、結局、駅の近くに引っ越したという車なしで生活できるAの前夫のBが住むブリスベンに白羽の矢を当てました。 2)Visit before living there in 2008.September. それで2008年の9月、本当にそこで私が生活できるかどうか下見に行きました。
世界地図がありましたらオーストラリアの地図を見て下さい。 オーストラリアはご存じのように日本と反対側の南半球にあります。
オーストラリアの歴史などは皆さんの方が詳しいと思いますが、1770年にイギリスの海軍士官で海洋探検家、海図製作者のキャプテン・ジェームス・クックがブリスベンの下の方にあるボタニー湾に到着しこの国をイギリスの領土としました。
オーストラリアは6つの州と、特別区からなる連邦国で、首都は特別区にあるキャンベラです。(この特別区は、1901年にオーストラリア連邦が結成された際、シドニーとメルボルンがどちらもお互いが首都になることを譲らなかったため、1911年に特別区を制定しキャンベラを首都としたとの事です。)
クイーンズランドの気候は熱帯、亜熱帯に属し年間を通してとても住みやすい所です。
下見にナンダのB宅に行っている間、ブリスベンに戻っていたAは私が生活に困った時に相談できる相手を沢山紹介してくれました。
3)The first my stay in Brisbane ( from 2009.April 9th to July 7th ) ブリスベン滞在は、観光ビザで行きました。
今回は、ここで一旦筆を置きます。次回はいよいよ出発前夜の4月9日から始まります。お楽しみに‥ | ||||||||||||
| ミレー館を訪ねて | |
| 吉原 司郎 2010年2月7日 |
|
小生は一息ついたところで、帰郷する機会がありましたので山梨県立美術館に出向き、‘ミレーの絵画’を鑑賞してきました。本物を鑑賞できるワクワク感! 胸の高鳴りはひさしぶりのことでした。『落ち穂拾い』、『鶏に餌をやる女』、『種をまく人』など多くの農民画に感動しました。 美術館の対面に文学館があります。たまたま、2月2日は幸運にも飯田蛇笏・龍太記念室のオープンの日でありました。最近誘われて俳句の会に入り、同郷出身の俳人の誼みもあり、蛇笏の作風に共感しておりましたのでラッキーでした。さっそく、句集を買い求めてきました。 その他、山梨にゆかりの文学者の作品や生い立ちを紹介しておりました。機会があればぜひ訪れることをお勧めいたします。
|
||||
| 『出雲国風土記』を訪ねる旅(4) | |
| 大木 陸夫 2007年8月20日 |
|
次に国史跡出雲国府跡とその周辺を歩いた。出雲国府跡の発掘は昭和43年から行われ、後殿や後方の官衙群が発掘されていて史跡公園となっています。正殿や脇殿は民有地の関係から発掘はされていません。遺跡の北側は農地が広がっていてその向こうに意宇郡の神名樋山【かむなびやま】、茶臼山があり、北東方には国分寺、国分尼寺跡があります。私たちは国庁から農道を国分寺に向かう。300メートルほど行くと、十字街【ちまた】に着く。ここは山陰道が東西方向に走り国庁や国分寺に通ずる南北方向の道との交差点である。ここも発掘調査されていて、道状遺構が確認された。『出雲国風土記』巻末記には、「国の東の堺より西のかたに去ること廾里一百八十歩にして、野城の橋に至る。(中略・橋の寸法)・・・又、西のかた廾一里にして国の廳、意宇の郡家の北の十字の街に至り・・・」とある。十字街は石見方面へ通じる正西道と、隠岐国へと向かう北に抂【まが】れる道・抂北道とに分かれる所である。それぞれの道は異郷に通じており、異郷から来た人が出会う場所である。チマタには市が立ち人々で賑わう。しかし、夕暮れは死者と交信する場所となる。柿本人麻呂は大和の軽のチマタに佇み、亡き妻の声が聞こえないかと耳を澄まし、道行く人の中に面影を探し求め、ついには妻の名を呼んで袖を振っている(「泣血哀慟歌」)。チマタは異界に通ずる道でもあったのだろう。 十字街を直進して茶臼山の麓を通る道に突き当たる。民家が並ぶ。これを東に少し行くと出雲国分寺跡にでる。南門、中門、塔、金堂、講堂などの伽藍が基壇と礎石で復元されている。 真名井神社は茶臼山の麓にある。 この地域は出雲国の中心地だったので、山代郷正倉や古墳群がたくさんあります。私たちは八雲立つ風土記の丘資料館館長さんのガイドで岡田山一号墳を見学した。横穴式石室をもち、太刀や鏡、馬具が発見されています。石室は割石と自然石で築かれ、内部に家形石棺が安置してあります。 国史跡田和山遺跡。弥生時代の環濠を持つ遺跡です。高さ48mほどの山に三重の環濠が廻らしてあります。横浜市の大塚遺跡や吉野ヶ里遺跡などは、環濠の内側に住居がありますが、田和山遺跡は三重の環濠の内側には、住居はありません。山頂部のあまり広くないところに、食糧庫か武器庫か分かっていませんが5本柱の遺構と9本柱の遺構があり、山頂部を取り巻くように柱列が、山の中腹部に三重の濠が廻らしてあります。濠の中には武器と思われるつぶて石や石鏃が、祭祀に用いられたと思われる石剣や分銅型土製品などが出土しています。 『出雲国風土記』に宍道郷の地名起源譚が出てきます。「宍道の郷 郡家の正西卅七里なり。天の下造らしし大神の命の追い給ひし猪の像、南の山に二つあり。(中略・山の寸法が書かれている)猪を追ひし犬の像は長さ一丈、高さ四尺、周り一丈九尺なり。其の形、石と爲りて猪・犬に異なることなし。今に至るまで猶あり。故、宍道【ししぢ】といふ。」 加茂岩倉遺跡は、1996年10月農道整備の工事中に偶然発見されたもので、その場の作業員は銅鐸のことをバケツがころがっていたように思ったそうです。県と町の教育委員会は知らせを受け、現場に駆けつけ、作業の中止と現状の変更のないようにお願いしたそうです。 荒神谷遺跡は、銅剣358本と銅矛16本、銅鐸6個が出土した全国最多出土の青銅器埋納遺跡です。加茂岩倉遺跡とは山々をはさんで直線距離3.3kmという近い所にあります。1984年7月、こちらも農道建設予定地の試掘調査をしていたところ、大量の銅剣が発見されました。そこは、私が見てよくこんな場所を掘ってみようかと思うようなところです。実は、荒神谷博物館から遺跡までのハス池に沿う道の傍らで、調査員が須恵器の土器片を拾ったことがきっかけで入り込んだ谷の斜面を掘ったそうです。専門家はちがうなぁと、感心しました。加茂岩倉遺跡と荒神谷遺跡からの遺物は、古代出雲歴史博物館に展示されていてで初日にそれを見て大きな衝撃を受けたことを書きました。 この旅の最後の見学地は西谷墳墓群史跡公園です。弥生時代の終わりから古墳時代にかけての墓地として使用された遺跡です。中国地方に多く分布する大型の四隅突出型墳丘墓が6基ありました。 弥生時代から古墳時代、そして古代に至る人々の暮らしと精神文化の一端を見たにすぎないでしょうが、奈良時代に書かれた「風土記」という文書をとおして、これだけの歴史と文化、そして、地理に触れられたことは、大変貴重な体験でした。(完) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 『出雲国風土記』を訪ねる旅(3) | |
| 大木 陸夫 2007年8月9日 |
|
東西60km程の島根半島を、一つの綱は三瓶山にかけ、もう一方は大山にかけ国引きをした。その綱が夜見の嶋(弓ヶ浜)だといってます。 美保神社は半島を内側に回り込んだ所にありました。出雲大社の神が大黒様、美保神社の神は、ゑびす様です。由緒の文面には、「釣り棹を手に鯛を抱かれ福徳円満の神影で漁業の祖神、海上の守護神、産業福祉の道をお拓きになった御神様・・・」となってます。 本殿の造りは大社造りの二殿連棟という特殊な形式で、美保造りとか比翼大社造りなどと呼ばれています。本殿は国の重要文化財です。『出雲国風土記』には「美保の濱 廣さ一百六十歩なり。西に神の社あり。北に百姓の家あり。志毘魚を捕る。」とでてきます。 島根半島と弓ヶ浜半島を結ぶのが境水道大橋である。橋の下を隠岐の島航路の船が白い航跡を残して通っていた。渡ったところが境港市(伯耆国)である。このコースは運転手さんのサービスの立ち寄りで、水木しげるロードにバスを止めてくれた。 「朝酌促戸【あさくみのせと】の渡り 東に通道あり、西に平原あり、中央は渡なり。・・・(中略)(筌【せん】(竹で作った漁具)を使っての漁の模様や、丸干しにすることなどが書かれている)・・濱譟がしく【さわがしく】にぎわい、市人四【よも】より集ひて、自然に【おのづからに】いちくら(店)をなせり。」とある。出雲国から隠岐国へと向かう官道が通る場所で、渡し船が置かれていた所である。「朝酌の渡り 廣さ八十歩ばかりなり。国庁より海の邊に通ふ道なり」とある。渡し船は今でも人々の暮らしの中にあった。ちょうど学校帰りの女子学生が自転車と一緒に渡って行った。そこは、古代に市が立ち、人が寄り合い、客寄せの声や値切りの交渉など、暮らしの声が聞こえてきそうであった。 熊野大社。『出雲国風土記』に、大社とあるのは杵築大社(出雲大社)とこの熊野大社の二社だけである。出雲国造が、すなわち、出雲大社の宮司さんが代替わりして国造(宮司)となるときには、先ず、ここ熊野大社で霊継【ひつぎ】をして、初めて神性国造としてその職を襲うことができるという。古来、連綿と代替わりのときに参拝し、神器のヒキリウス、ヒキリキネで神聖な火をキリ出して斎食を調整して、熊野大神と相嘗(共に食す)することにより新国造、神性国造となるそうです。写真はそのヒキリウスとヒキリキネの神事が行われる鑽火【さんか】殿です。また、毎年10月15日に出雲大社の宮司さんが、自らが出雲大社の祭事に使用するヒキリウスとヒキリキネをこの熊野大社から拝受するという神事があるのですが、このときに亀太夫という云わば一般人が、国の長官でもある宮司さんが持参したお餅を、「色が悪い」「ひびがある」「つぶつぶがある」などと出来栄えに苦情を言う場面があるそうです。そのやり取りの後、宮司さんは神舞を奉納、神器を授かることができるといいます。厳粛であるべき神事の中に俗な情景を組み入れることで一般大衆の心をつかんでいるのでしょうね。 椿の葉っぱと『出雲国風土記』と関係があるの? 実はここの椿の木は根元が二本で中程が合体して一本に、そしてまた、二本に分れているというものです。ここは、八重垣神社です。「出雲八重垣、祈願をこめて、末は連理の玉椿」連理の玉椿は夫婦椿ともいうのです。写真は椿の葉っぱのアップですが、資生堂花椿会の椿のマークのモデルはこの椿だと聞きました。また、「早く出雲の八重垣様に、縁の結びが願いたい。」と出雲の古い民謡に謡われているそうですが、境内には鏡の池があり、その水面に銭を載せた紙を浮かべ、その沈んでいく速さで恋の成就、待ち人がいつ現れるかなどを占うといいます。『出雲国風土記』には佐久佐神社とでてきます。 *ここで訂正があります。前回の(2)の文中に?が二か所出てきていますが、最初のは「?(フグ)は魚ヘンに台を書いた字」、二つ目は、秋鹿郡の神奈火山の「始終?歩は、始終を削除して?は四十の意味の横棒に縦棒を四本書いた字」です。 |
||||||||||||||||||||
| 『出雲国風土記』を訪ねる旅(2) | |
| 大木 陸夫 2007年7月4日 |
|
次に訪れたのが、日御碕神社。『出雲国風土記』には美佐伎社とある。徳川家光が寄進した楼門が国の重要文化財に指定されていて、朱塗りの社殿が鮮やかである。神社から海沿いの遊歩道を出雲日御碕灯台へ向かった。ここで灯台の写真を見てもらいたい。この灯台の高さが地上43m65cmということで、石積みの灯台としては日本一の高さである。そこで古代出雲大社の高さが48mだったことを思い出して欲しい、この灯台を数メートル超える高さだったのである。木造でこのような高さの社が建てられていたのである。私は、螺旋階段を途中休みながら登り、島根半島の西端の絶壁の景観を堪能したのは言うまでもない。写真は燈光会より提供して頂きました。 青木遺跡。所在地は一畑電車おおてら駅北東300m位の出雲市東林木町。国道431号バイパス工事現場の発掘で、弥生時代の四隅突出型墳丘墓や井戸、掘立柱建物跡などが見つかっている。木簡や墨書土器、神像も発掘されている。建物のうち一棟は、9本柱で中心の柱が太く、深く埋められていたことなどから、大社造りの神社の可能性があり、神を祀る儀礼があったことを窺い知ることができて貴重である。写真は埋め戻された遺構の上に復元された青木遺跡である。 一日目の見学はここまでで、宍道湖の北岸を松江市内のホテルに向かって進んだ。 この夜は居酒屋さんで懇親会をした。そこで宍道湖七珍のうち、スズキ、テナガエビ(本当はモロゲエビですが漁獲が少なく出回らないといいう)、アマサギ、コイ、シジミを食べた。七珍には他にシラウオとウナギが加わる。 5月29日は佐太神社から旅の続きが始まった。『出雲国風土記』秋鹿郡に、「神名火山【かむなびやま】郡家の東北のかた九里始終?歩なり。高さ二百卅丈、周り一十四里なり。謂ゆる佐太の大神の社は、即ち彼の山下なり。」とある。『出雲国風土記』には神名火山が四座出てくる。カムナビは神隠り【かんなばり】の意であるが神名樋、神奈備、神名備、甘南備、甘嘗備、賀武奈備、賀茂那備など多様な表記がされる。 「加賀の神埼 即ち窟あり。高さ一十丈ばかり、周り五百二歩ばかりなり。東と西と北とに通ふ。」と出てくる、加賀の潜戸【くけど】は、佐太の大神が産まれた場所だという。そこは地殻変動による断層と浸食作用が加わってできた、と今風に解説してしまっては神話の国めぐりではなくなってしまうが、陸と海とに二つの大きな洞窟があって、遊覧船で巡ることができる。船は先ず新潜戸に私たちを案内した。東から西北に開いた洞窟を波に負けないように少し加速して潜り抜けた。神話では枳佐加比賣命【きさかひめのみこと】が大神を産もうとするとき弓を射た。行き詰まりの岩窟が神力によって向こう側まで抜け通って明るくなったというのである。当時の人はここを船で通るときには大声をとどろかせて、恐怖心を振り払ったという。旧潜戸は陸にある。船をおりて岩肌づたいの道を洞窟に入っていった。賽の河原のように小石が積まれていた。無数にあった。そこは、幼くして死んだ子供たちの集まる場所と信じられ、不幸にして愛児を亡くした親たちが遺品を持って訪れるという。ランドセル、人形、運動靴など所狭しとあるのが物悲しく観光気分では見続けられなかった。 |
||||||||||||||||||||||||
| 『出雲国風土記』を訪ねる旅(1) | |
| 大木 陸夫 2007年6月29日 |
|
|
この旅は横浜市歴史博物館で『続日本紀』和銅六年(713)五月甲子条に出てくる、“風土記”編纂の記事の『出雲国風土記』の特別講義を受けたことがきっかけであった。 5月28日(月)7:20、旅のスタートは羽田空港のロビーに集合することで始まった。
出雲大社は神話の夢舞台である。松並木の表参道から銅鳥居をくぐって社殿に向かった。私たちは千家【せんげ】権宮司さんから出迎えのご挨拶を頂いた。私は見学のつもりでこれを書いているが、実は「お庭ふみ」という宗教的な行いなので、装束を着け、お祓いを受けて社殿のご案内となった。八足門から瑞垣の内へ入ると荘厳な御本殿が目近なものになった。本殿は来年から平成の大修理が始まります。大社では「平成の大遷宮」といっています。現在の本殿は延享元年(1744年)に造営され、三度のの葺き替えと修理がされてきた。今回の大修理でも桧皮屋根の葺き替えや建物の修理がされるという。ご案内によると、桧皮の屋根には小鳥が巣をつくり穴があいているそうだ。実際、私たちも小鳥が出入りするのを目撃した。案内の神官の少しユーモアを交えた話ぶりが、荘厳な雰囲気に少々緊張気味だった私たちをリラックスさせてくれた。国宝建造物である本殿の修理をするためには、法律が必要だそうだ。年内には国会で決定する予定だという。着工すると五年程工事用の覆い屋根がかかる。この「平成の大遷宮」で、社殿がどのようにヨミガエリするのか楽しみな気持ちになった。
島根県立古代出雲歴史博物館が次の見学地である。今年3月10日に開館したばかりの博物館で、ここには上述の三本柱や、後述する荒神谷遺跡や、加茂岩倉遺跡出土の弥生時代の青銅器など国宝、重要文化財が展示されている。強烈なインパクトを持って出迎えてくれたのが、大きな壁面を埋め尽くした、荒神谷遺跡出土の銅剣380本の展示である。誰もが感嘆の声を上げていた。平安時代の出雲大社本殿の1/10復元模型や玉作、たたら製鉄などの展示があった。そして、出口から国道に続くアプローチは、古代出雲大社の一丁の長さの階をイメージして作ったというもので、その長さを実感させてくれていた。 昼食は、出雲そばを出雲流に食べる割子そばであった。 稲佐の浜へ出た。ここは国譲り神話の舞台であり、また、旧暦十月に全国から神々がここに上陸し、神迎の神事が行われる場所である。正面に弁天島、長く続く砂浜を左に見ていくとその奥に三瓶山も見ることができた。『出雲風土記』の「三身の綱うちかけて、霜つづらくるやくるやに、河船のもそろもそろに、国来々々と引き来縫へる国は・・」の綱の一本を掛けたのが三瓶山であり、もう一本を大山に掛けて国引きをしたという。そんな情景を思い描きながら見ていたら、古代日本人の自然の見方や、想像の豊かさ、作話の巧みさなど興味深く、この後の旅への期待が大きくなっていった。 |
||||||||
| 利尻とウニ | |
| 今泉 みゆき 2007年5月25日 |
|
|
<この作品は作者が所属していた山岳会の文集に「山と食べ物」というお題を受けて書いたものの転載であることをお断りします。> 「海と山、どっちが好きか」と聞かれれば、ちょっと考えて「山」と答える私だが、「海の食べ物と山の食べ物、どっちが好きか」となると、これはもう間髪を入れず、「海!」となってしまうのだ。 ■ことのはじまり〜チャリ旅 それは1998年のこと。その夏私は稼ぎの良かった派遣の仕事を突然リストラされてしまった。普通なら失職して落ち込むところだろうが、そこは私、これは長期休暇の良いチャンスとばかりに以前からやりたかった北海道のチャリ旅に出かけた。テーマは「行き当たりばったりのビンボー旅」。そのテーマ通りに、宿泊はテント、食事は勿論自炊で、ご飯と味噌汁、それに缶詰やレトルトのおかず1品という貧しい生活を送っていた。特別に好きなわけでもないのに、安くて栄養があるからと、納豆をよく食べていた。贅沢と言えば温泉あがりの1本の缶ビール。いや、違う、正しくは発泡酒。それがささやかな食の幸せだった。 ■うれしい出逢い それから3年後の2001年6月、私は再び利尻にいた。この時の目的は利尻山の登山コースを確認すること。つまりガイドの下見だった。チャリ旅の時は重い思いをして登山靴を運び4日間も滞在していながら結局登らずじまいだったのだ。 2日目の6月15日。素晴らしい登山日和の天気となった。 ■そして再び 下見を無事に終えた私は、翌月にはJTBの登山ツアーのガイドとして再び利尻を訪れることができた。これは勿論全食事付き。利尻の宿の食事いえば、必ずウニは付いてくる。前年に行ったガイドから、海産物をたらふく食べたと聞いていたこともあり、食事にはかなり期待をしていた。 しかし、ここで終わってしまっては尻つぼみではないか。 さんざっぱらビールを仰いだが、そこはもちろんプロ。翌日に残すことはなく、朝の4時には宿を出て、しっかり仕事をこなしたのは言うまでもない。 そうそうすっかり忘れていた。「ウニを取りに行こう」の少年は、翌朝再び私のテントを訪ねてきた。そして隣に幕営していたライダーのにいちゃんと共に岩場に出てウニ探しをした。これも「海賊」行為なのかなとちらっと思ったが、漁師の息子から誘われたのだから問題ないだろう。それに真剣さがなかった私は結局一個も見つけられなかった。それに対して真剣だった少年は長い昆布をたぐり上げ、昆布に付いた小さなウニを見つけてくれた。食べてしまうには可哀想なサイズだったが、少年の折角の好意を無駄にしてはいけないので、ナイフで割って食べた。あまりに身が少なかったため美味しいも何も判らなかったが、ウニにからんだ海水のしょっぱさは、子供相手に真剣にならなかった私の、楽しいながらちょっとしょっぱい思い出となった。 北海道内で好きな場所というのはいくつもあるが、利尻は大雪、知床と並んでトップクラスに入る。それは決してウニの思い出のためではない。たとえウニが食べられなくても、また足を運びたい場所だ。 |