|
タイトル
|
投稿日 |
| 「舞の能楽解説」第五話 能の作り物について | 2008.1.30 |
| 「舞の能楽解説」第四話 能の種類について | 2007.11.27 |
| 「舞の文楽・歌舞伎解説」松羽目物【まつばめもの】 | 2007.7.14 |
| 「舞の能楽解説」第三話 能面について | 2007.7.14 |
| 「舞の能楽解説」第二話 能楽を演じる人々 | 2007.6.22 |
| 「舞の能楽解説」第一話 私って誰 | 2007.6.22 |
| 能楽堂の舞台と座席について | 2007.4 |
| 「舞の能楽解説」第五話 能の作り物について |
||||||||||
|
今回は、能舞台に登場する簡単なセット(「作り物」と呼びます。)についてお話したいと思います。能の舞台では文楽・歌舞伎やその他の演劇のように大道具というのがありません。大掛かりな舞台装置がない代わりに演じるほうも観客もちょっとしたものをそれに見立てて演じたり鑑賞したりするお約束になっているのです。例えば《船弁慶》で使用する船、《隅田川》で子方(梅若)が入っている塚や《井筒》で使う井戸などが代表例でしょう。 写真1の「船」は骨格だけを竹で作り白布(ボウジという木綿の布)を巻いただけの最もシンプルな「作り物」といって良いでしょう《船弁慶》や《竹生島【ちくぶじま】》に使われます。その他の作り物も同様ですが写真のような「船」の基本形のみでなく、演目によってバリエーションを付けます、例えば《俊寛》では纜【ともづな】をつけ、《江口》や《住吉詣》などでは上に屋形をつけた「御所船」にする。
写真2の「車」は《熊野【ゆや】》などの「物見車」です、牛車(牛車ですがもちろん牛は出ません。)を簡素化したもので、竹で骨格だけを作り色入りの布を巻いてあります。これに花を付け「花見車」として使用することもあります。そのほか「土車」・「汐汲車」・「椅子車」などがあります。
写真3の「立木台」は樹木を舞台に出すときに支える台で、角台と丸台があります。(流儀によって使用するものが違う、観世流と宝生流は角台が多い。)写真は《羽衣》で使用する松です。立木が曲によってかわってきます例えば《胡蝶》の梅・《綾鼓【あやのつづみ】》の桂などがあります。
写真4は、《邯鄲【かんたん】》などに使われる「一畳台」です。(写真は舞台上で一畳台の上に四本の柱と屋根を組み立てる「引立大宮」(「大屋台」とも)です。)
写真5は、《半蔀【はじとみ】》専用の作り物で、「藁屋」という質素な住まいを表す作り物の一種です。夕顔の花と蔦がからまり、瓢箪もつきます。
これらの「作り物」は、昔は「作り物師」という専門の役でしたが、現在は第二話でもご紹介したとおり「シテ方」の能楽師よって作られています。 (今回紹介させて頂いた「作り物」の写真は、社団法人能楽協会のホームページに掲載されている写真の転載許諾を頂き掲載しております。) では、またお会いしましょう。 |
||||||||||
| 「舞の能楽解説」第四話 能の種類について |
|
皆さんお元気ですか?大変ご無沙汰しておりました、「神奈川放友会」の公羽【こうう】舞【まい】で〜す。 「初番目物」 「二番目物」 軍体の能姿。仮令、源平の名将の人体の本説ならば、ことにことに平家の物語のまゝに書くべし。(世阿弥『三道』) 「三番目物」 「四番目物」 「五番目物」 能の間に狂言が入りますので、「《翁》付き五番立て」を現在のスピードで演じたら10時間から12時間もかかってしまい、一日で観るのは大変ですよね。 では、またお会いしましょう。 (*δ。δ) |
| 「舞の文楽・歌舞伎解説」 松羽目物【まつばめもの】 |
|
こんにちは、「神奈川放友会」の公羽【こうう】舞【まい】で〜す。 《勧進帳》はまだ能楽(当時は猿楽と呼ばれていました。)が幕府の式楽であった時代に作られましたが、そのほかは明治時代以降にたくさん作られました。それに貢献したのが狂言の「鷺流」です。『能楽解説』の「第二話」で紹介したとおり現行の狂言方の流儀は「大蔵流」と「和泉流」の二流ですが、大正時代までは「鷺流」という流儀がありました。能楽界は明治初期、武家の保護がなくなり大変に困窮しました、「鷺流」はその対策として歌舞伎界との一体化(吾妻能狂言:能と歌舞伎の折衷演劇)を画策しました、しかしそれに失敗すると今度は復興した能楽界から排除されることとなり、大正年間に廃絶していました。現在は山口や佐渡で流儀を継承する人々により演じられ続けています。 前記の「岡村柿紅」も「鷺流」に通じていました。「松羽目物」が数多く作られ、またその演出に影響を与えたことは、歌舞伎界の繁栄に「鷺流」が貢献したことのあかしではないかと思います。 私は「文楽・歌舞伎」も大好きなので、こちらの解説もしていきたいと思っています。よろしくお願いします。 |
| 「舞の能楽解説」第三話 能面について |
||||||||||||||||||||||||
|
こんにちは、「神奈川放友会」の公羽【こうう】舞【まい】で〜す。(私のことを知らない人は、第一話から読んでくださいね。) 「公羽家」には平安時代の作と伝えられる「翁面」(白式尉)があります、「弥勒」という名人の作です。舞台ではつけられませんが、親にも内緒で稽古場においてつけてみるとあっと驚くことが起きたのです。その話はおいおい別な場所でお話したいと思います。(放友会月例会の後で「玄や」あたりが良いかな?) 「面【おもて】」の素材は稀に桐や楠を用いることがありますが、加工がし易いこともあって現在では檜が多く使われています。面を製作することを「面を打つ」といい、決して彫るとはいいません。面を「かぶる」とはいわず、「つける」あるいは「かける」というのと何処か通じるものがあります。そのくらい能楽師にとっては大切な道具といえるでしょう。
異相の面の代表は、皆さんもよくご存知の「般若【はんにゃ】」<写真1>でしょう、激しい怒りと強い悲しみが混在する面です。 狂言面の中には「猿」や「狐」といった動物の面などがあり、能面より自由な発想で狂言面が作られていたこと感じられます。 面の種類は数え方によって250ほど種類があるといわれています。その中でも、能面の美を最大に誇るのが「女体」(老若さまざまな「女面」。)です。先の「般若」とともに最も有名で完成された面の一つです。 「小面【こおもて】」<写真2,3>、から「増女【ぞうおんな】<写真4>」、「深井」、「老女」などと、女性の年齢ごとに変化する美を描写・表現しているのが女面です。 男性の面としては、貴族的な表情をたたえた「中将」<写真5>、禅宗における半僧半俗の「喝食【かっしき】」<写真6>、精悍な表情の「平太【へいた】」などがあります。 老体の面は、男性の老人(「尉【じょう】」<写真7>といいます)の面で《高砂》や《老松》など神の化身として現れる役柄などに使用されます。
「翁面」については、「翁」がつける「白式尉【はくしきじょう】」や「三番叟」が「鈴の段」でつける「黒式尉【こくしきじょう】」(狂言面に分類される)などがあり、舞台上でつけるという特徴とともに形状の特徴として、顔と顎のパーツが別々で頬と顎が紐で結ばれている「切顎式」と呼ばれるとなっています。他の能面より古い様式を伝えるものといわれています。「翁面」をご神体とする神社も少なくありません。 いかがだったでしょうか「能面」について理解できたでしょうか? (今回は能面の写真を、京都市在住の能面師 中村光江氏のホームページから転載させていただきました。中村さんには、我々神奈川放友会のHPに快く写真の掲載を承諾していただき大変感謝しております。) |
||||||||||||||||||||||||
| 「舞の能楽解説」第二話 能楽を演じる人々 |
|
m(*^_^*)m こんにちは、「神奈川放友会」の公羽【こうう】舞【まい】で〜す。(私のことを知らない人は 第一話を読んでくださいね。) 主役を「シテ」と呼ぶことは既にお話しましたよね、『シテ方』はそれ以外に「ツレ」、「後見」(舞台の進行管理役)、「地謡」(謡曲のコーラス隊)、作り物の製作、揚幕(鏡の間と橋掛かりの間にかかる五色の幕)の操作、装束の着付けなどを担当します。能役者の中で一番人数も多く、能公演のオールラウンドプレーヤーと言ってもいいでしょう。先の「子方」もシテ方の役者です。現在『シテ方』としてはシテ五流といわれる次の流儀があります。<観世流・金春流・宝生流・金剛流・喜多流> 『ワキ方』の解説のところで、面【おもて】をつけないで演じることをお話しましたが、能の世界では面をつけないで演じることを直面【ひためん】といいます。「子方」はほとんど直面で演じます(「世阿弥」のいうところの「時分の花」を効果的に表現するための演出でしょうか?)、「シテ」でも役柄によっては直面で演じられることがあります。直面といえば、めずらしい曲がありますので紹介しておきましょう。私も好きな曲なのですが《鷺》という曲のシテは少年(しかも能の家の嫡男に限られているらしい)か、還暦を過ぎた老年の人が直面で演じることが常で、何かの都合で壮年の人が務めることとなった場合には面をつけて演じます。<ちょっと次回の予告編となりました。> いかがだったでしょうか能を演じる人々のことが多少なりとも理解できましたぁ? |
| 「舞の能楽解説」第一話 私って誰 |
|
m(*^_^*)m はじめまして、私の名は公羽【こうう】舞【まい】 「世阿弥」(「観世三郎元清」)は時の将軍「足利義満(室町幕府3代将軍)」に賞玩された能役者(藤若と呼ばれた稚児時代は、教養に溢れ男も惚れるアイドル的な存在)で、室町時代のとっても有名な人。お父さんは「観阿弥」(「観世清次」この人もとっても有名な人です)(「世阿弥」と「足利義満」が初めて会ったのは「世阿弥」が12歳の時、「足利義満」が17歳くらい、そして「観阿弥」は42歳の働き盛りでした、「観阿弥」・「世阿弥」親子二人の演じた能に義満が魅了されたのでした。)。今演じられている能の原形(当時は「猿楽」・「猿楽の能」などと呼ばれていました、「世阿弥」は「申楽」という字も用いました。)といっても良い芸能を大成させた役者であり、それらの劇の脚本・作詞・作曲を一手に担った人で、舞台監督でもあり、劇団の経営者でもあったスーパーマンです。 私の苗字、公羽を縦書きにすると「翁」になります、誰かとぼけた先祖が名付けたのか、高貴な人に授かったのか知りませんが変な名前ですよね。でも本当はとっても由緒正しいのかな?とも思っています、何といっても「観阿弥」・「世阿弥」親子が活躍した当事の能劇団(「座」という:(※)大和猿楽四座)は《翁猿楽》という芸能(半分神事芸能ですが。)をとっても重要だと考えていたし、生活の糧でもあったと伝えられていますから、「翁」・「翁面」に対する信仰・執着は大変強いものがあったのだと思います。 (※)大和猿楽四座:『風姿花伝』にも記述されていますが、「円満井座【えんまいざ】」・「結崎座【ゆうざきざ】」・「坂戸座【さかとざ】」・「外山座【とびざ】」の4つの座で多武峰【とうのみね】・春日興福寺などの寺社に参勤する義務を負い《翁猿楽》を演じていた。後の「金春座」・「観世座」・「宝生座」・「金剛座」の母体であったといわれています。「観阿弥」は「結崎座」に所属する太夫で「観世太夫」を名乗っていました。その後「世阿弥」が「観世太夫」を継ぎます。 いかがだったでしょうか私のことやご先祖さまの「世阿弥」のことを多少なりとも理解していただけましたぁ? |
| 能楽堂の舞台と座席について |
|
能楽堂の観客席のことを見所【けんしょ】といいます、舞台の上には屋根がありますがこれは昔の能舞台が屋外にあった名残です。その頃の絵画資料などを見ると後ろにも観客がいて360度全ての方向から見られていた事が伺えます。 現在のような能楽堂になったのは明治以降のことで、座席は舞台に対して約90度の角度で配置しています。 公演情報のチケット代の欄に、正面・中正面と書いたように場所により席の名前がつけられています(下図参照) 全部の席名に全て正面という名称がついていますので紛らわしいのですが、正面:鏡板(舞台奥に老松が描かれた板)に向かって正面、脇正面:舞台から見て右側・地謡と対面、中正面:正面と脇正面の間となります。 能舞台は三間四方の飾り気のない空間ですが、そこで場所を超え・時を超え、生と死・聖と俗・男と女の狭間を表象するのです、それが能役者の卓越した技といえるでしょう。
4本の柱をはじめ舞台上の場所には名前が付けられている。例えば中正面側の柱は目付柱【めつけばしら】と呼ばれ、面【おもて】をつけた役者は視界が良くないのでその柱を目印に演技をすることからその名がある。 そのような用語解説や役柄の解説など定期的に掲載して行こうと思っています。 |
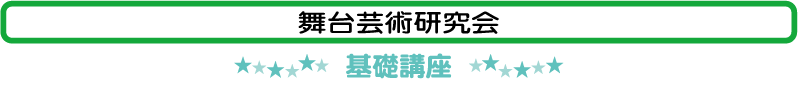







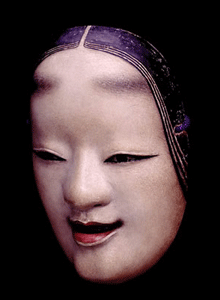
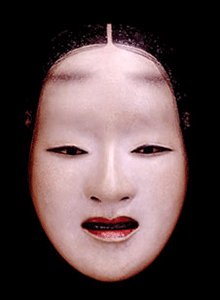
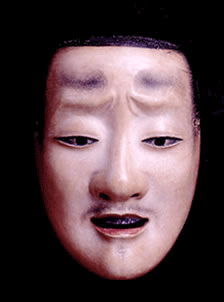
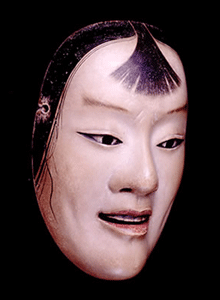
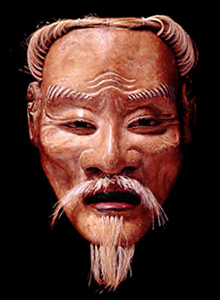
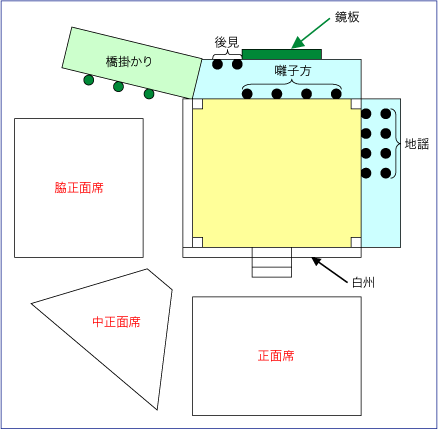 <左図解説>
<左図解説>