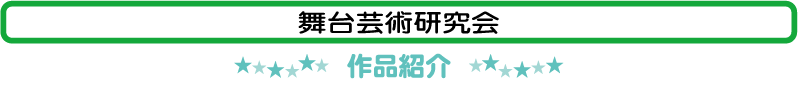| 能 | 鷺【さぎ】 |
| 能 | 隅田川 |
| 歌舞伎 | 双蝶々曲輪日記【ふたつちょうちょうくるわにっき】〜「引窓」〜 |
| <能> 鷺【さぎ】 |
|
こんにちは、「神奈川放友会」の公羽【こうう】舞【まい】で〜す。今回は作品の紹介をしましょう、『鷺【さぎ】』という曲ですが2008年7月5日横浜能楽堂にて公演されます。曲の分類は初・四番目物、季節は六月です。 <あらすじ> 延喜帝(注1)の御代、帝(ツレ)が夕涼みのために神泉苑(注2)に行幸した。人々が詩歌管弦に興じるなか鷺(シテ)が羽を休めている。それを見て帝は大臣(ワキツレ)に捕まえてくる様に命じ、更に下命を受けた蔵人(ワキ)が捕まえようとするが鷺は飛び去ってしまう。蔵人が勅諚であると呼びかければ、鷺は喜んで舞い戻る。蔵人はこれを帝に捧げ、帝は蔵人に爵を、そして鷺には五位の位を賜る。鷺は羽を羽ばたかせて舞(鷺乱【さぎのみだれ】)を舞い、やがて何処かへ飛び去る。鷺乱は重習【おもならい】の中でも特に別伝という最も難易度の高い曲になっています。 では、またお会いしましょう。 (*δ。δ)> ----- (注1)延喜帝=醍醐天皇(885〜930年) |
| <能> 隅田川 |
|
作者は観世十郎元雅、シテは都から我が子を探し武蔵国と下総国との国境を流れる大河、隅田川まで流浪して来た狂女。(狂女・・・精神病のように狂っているのではなく、夫や子供を想う余りになりふりかまわずその事しか頭になく周囲から見ると、まるで狂っているように見える女。笹を手に持つのが典型。) <あらすじ> 隅田川の渡し守<ワキ>が今日は大念仏があるから人がたくさん集まるといいながら登場。都からの旅人<ワキツレ>の道行きがあり、渡し守と「都から来たやけに面白い狂女を見たからそれを待とう」と話しあう。 里人は余りにも哀れな物語に、塚を築き、柳を植え、一周忌の念仏を唱えることにした。 最後の場面において、作者元雅と父世阿弥との間に我が子の亡霊である子方を出したほうが良いか否かで有名な問答(申楽談義に記載)があり、現在でも両方の演出で演じられている。(元雅流に、子方が出る場合の演じ方が多い。) |
| <歌舞伎> 双蝶々曲輪日記【ふたつちょうちょうくるわにっき】〜「引窓」〜 |
|
「双蝶々曲輪日記」は寛延2(1742)年、大坂竹本座での初演され同年歌舞伎に移されて上演された。竹田出雲・三好松洛・並木千柳の黄金トリオの合作で同じ作者たちの作品である「仮名手本忠臣蔵」の翌年にできた作品です。 <それまでのあらすじ(長五郎を中心に)> 関取の濡髪長五郎は、贔屓にしてもらっている山崎与次兵衛の息子与五郎が、藤屋の遊女吾妻と恋仲になり身請けするについて陰ながら力を尽くしている。それというのも、吾妻には平岡郷左衛門という侍も横恋慕しているからであった。 <八段目「引窓」> 濡髪の実母、お幸は義理の息子、南与兵衛【なんよへい】とその女房で廓から請け出したお早とともに幸せにくらしている。今日は与兵衛が奉行所に呼び出されて、父南方十字兵衛【なんぽうじゅうじべえ】の名前と、七ヶ村の郷代官という職を継ぐ嬉しい日。そこへお尋ね者となり身をくらませていた、濡髪が母にひそかに別れを告げにやってくる。そうとは知らず再会を喜んでご飯を作ってやろうとするお幸。 <みどころ> 天井の明りとりである引窓が巧みに劇展開の中で用いられ、中秋の名月や放生会の行事も作中にみごとに生かされている。 |