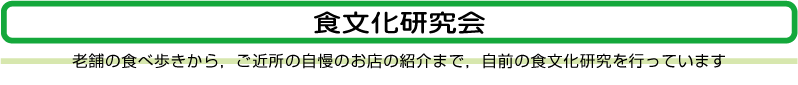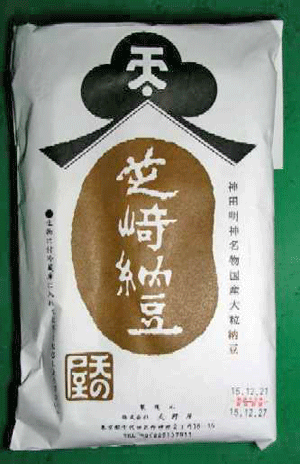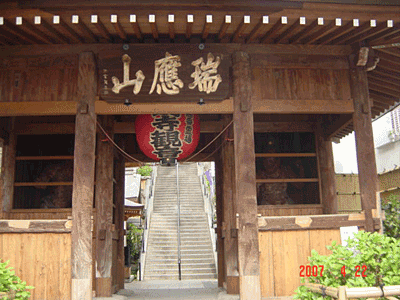| タイトル | 投稿者 | 投稿日 |
| 『食べアルキ帳』第1回〜浅草「駒形どぜう」と「酉の市」 | 木村 勝紀 | 2008.12.2 |
| カフェでひととき | 秋山 智子 | 2008.11.2 |
| 横浜のベトナム・レストラン | 木村 勝紀 | 2008.8.27 |
| 元禄二八そば・玉屋 | 木村 勝紀 | 2008.8.19 |
| 塩は食肴【しょくこう】の将 | 木村 勝紀 | 2008.5.31 |
| 鹿児島銘菓 軽羹【かるかん】 | 木村 勝紀 | 2007.12.14 |
| 江戸の味を伝える「蓮玉庵」 | 木村 勝紀 | 2007.9.5 |
| 蕎麦屋の老舗物語 | 木村 勝紀 | 2007.7.5 |
| 「神谷バー」へ行って | 高橋 照夫 | 2007.6.12 |
| 芝崎納豆の由来 | 芝崎 芳和 | 2007.6.12 |
| 江戸のファストフード | 木村 勝紀 | 2007.6.8 |
| 池之端藪蕎麦 | 木村 勝紀 | 2007.5.25 |
| 谷中の喫茶店「乱歩」と穴子寿司「乃池」 | 木村 勝紀 | 2007.5.11 |
| 「弘明寺縁起」と「弘明寺銘菓」 | 木村 勝紀 | 2007.4.26 |
| 伊勢路の赤福餅 | 木村 勝紀 | 2007.4.17 |
| 2009年以降はこちら |
| 『食べアルキ帳』第1回 浅草「駒形どぜう」と「酉の市」 |
|
| 木村 勝紀 2008年12月2日 |
|
食文化研究会は、ホームページに記事を載せるだけでは物足りない。そこで皆様と一緒に名店を訪ねて賞味をする、という企画を実施することに致しました。賞味の結果を「食べアルキ帳」として版を重ねて参りたいと思います。第1回目の今回は、「駒形どぜう」浅草本店です。実施日の平成20年11月29日(土)は、丁度「酉の市」の三の酉の日にあたり、食後の散歩に大勢で賑わう「鷲【おおとり】神社」にも参詣してまいりました。 今回は「jinhoyu-net」で同行を募集したところ9名の参加がありました。 「駒形どぜう」浅草本店 メニューの紹介
どぜうは江戸庶民のスタミナ食 鷲【おおとり】神社へ 酉の市の賑わい 境内に入れば無数の提灯と、縁起物を派手に取り付けた大小の熊手が所狭しと飾られ、商談成立となればシャン、シャン、シャンの手拍子が鳴り響きます。めいめいお賽銭を納め、熊手やお土産を買い求め鷲神社を後にしました。帰りの浅草寺までの沿道は各種の露店で埋め尽くされ、さながら町中がお祭りの風情となっていました。下町っていいな!
文責:木村勝紀 |
||||||||||||||
| カフェでひととき | |
| 秋山 智子 2008年11月2日 |
|
|
書店に行くと、カフェについての本や雑誌をよく見かけるようになった。 しかも携帯電話がある。 さて、わたしの目下のお気に入りのカフェは、ふたつある。 もうひとつは、『珈琲館』。ここもチェーン店である。 カフェの使い方も人それぞれである。 |
| 横浜のベトナム・レストラン | |
| 木村 勝紀 2008年8月27日 |
|
|
フェスタ・ヨコハマのお手伝い ベトナムの基礎情報 ベトナムの経済
西暦734年遣唐使・平群広成が帰国の途上、難破して崑崙国に漂着し抑留。753年には同じく遣唐使・藤原清河や阿倍仲麻呂が帰国の途上、漂着しています。これが縁で阿倍仲麻呂は761年から761年まで安南節度使としてハノイの安南都護府に在任したといいます。14世紀から15世紀にかけては琉球王国と通商し、17世紀になると朱印船がベトナムに進出し、江戸幕府も外交文書を交換したといいます。会安【ホイアン】には日本人町が形成されたこともあり、「日本橋」という橋が現存しています。日本の銅貨・寛永通宝はその材質の良さから、東アジアの基礎通貨の一つとして流通し、国際取引の決済に使われたそうです。1940年の日本軍の北部仏印進駐以降の現代史は、皆様ご承知の通りです。 ベトナム料理の特長 「ホイ・アン・カフェ」横浜ルミネ店 注文した料理 文責:木村 勝紀 |
||||||||||||
| 元禄二八そば・玉屋 | |
| 木村 勝紀 2008年8月19日 |
|
|
元禄二八そば・玉屋 日本人の「そば」好き 「そば」の歴史 「二八そば」とは? 赤穂浪士とそば屋の一件 「十割そば」と「討入りそば」
文責:木村勝紀
|
| 塩は食肴【しょくこう】の将 | |
| 木村 勝紀 2008年5月31日 |
|
久しぶりに話題を提供いたしましょう。「酒は百薬の長」とは、人口に膾炙されて皆様ご存知のことですね。左利きの者にとっては有難い御託儀です。ですがあくまで適量をわきまえることが前提のようですから、ご注意、ご注意。 さて、この「酒は百薬の長」の出典は、「漢書」の「食貨誌」で、王莽【おうもう】がくだした詔【みことのり】の冒頭の一句、「夫【そ】れ塩は食肴の将、酒は百薬の長、嘉会【かかい】の好、鉄は田農【でんのう】の本【もと】」からでているそうです。ここに「塩は食肴の将」が「酒は百薬の長」と対になって出ている訳ですね。塩は料理に欠かせないものであり、酒は適量で薬以上の効き目があり、めでたい集まりには必要なもので、鉄は農業器具の基本となるものだ、といったところでしょうか。 「王莽」の故事 「酒は百毒の長」とも 文責:木村勝紀 |
||||
| 鹿児島銘菓 軽羹【かるかん】 | |
| 木村 勝紀 2007年12月14日 |
|
|
九州一周旅行の際に鹿児島を訪れました。鹿児島といえば西郷隆盛です。鹿児島空港から程近くに西郷隆盛の銅像で有名な西郷公園があります(写真1)。 そこで買い求めたのが鹿児島銘菓の「軽羹【かるかん】」でした(写真2)。
「軽羹」をリュックに収めて、次に向かったのが西郷隆盛ゆかりの城山でした。城山は標高107mで山頂は鹿児島市街と桜島を一望できる絶好の展望台です。城山周辺は西南戦争で最後の激戦地であったところであり、近くに西郷隆盛が最後の5日間を過ごしたといわれる西郷洞窟があります。 |
||||||||
| 江戸の味を伝える「蓮玉庵」 | |
| 木村 勝紀 2007年9月6日 |
|
|
江戸時代創業で今に残る食べ物の老舗は、まだまだあちこちに健在です。今回は、東京上野で時代の変遷を見続けてきた蕎麦屋の「蓮玉庵」を紹介しましょう。 江戸人の外食の二本柱といえば、料理茶屋とファストフードです。ファストフードについては前回触れました。料理茶屋についても少し述べてみましょう。江戸は全国三百諸侯といわれる各地の大名が上屋敷、中屋敷、下屋敷を保有しました。各藩の抱える藩士の合計は約55万人におよぶといわれ、各藩の江戸留守居役は、お互いに天下の情報交換をすることが大事なお役目でした。あるいはまた幕府の要人とも連絡をゆめゆめ怠ることはできませんでした。一方、将軍のお膝元の消費生活を円滑に推し進めてきた商人たちは、元禄以降はその経済力も増大し、これまた同業者同士の打合せや、役人やお得意先への接待などが大切な日常となっていました。 江戸は度重なる大火で罹災し、武家屋敷も調度や食器などは罹災を考慮して、あまり高級なものを持たないという状況でした。また、当時の町家は人口が全体の50%であるのに対して、居住用面積が20%程度でしたから豪商といえども自邸に人を接待するような部屋を設ける余裕はありませんせした。そこで、然るべき会合のための広間を持ち、酒肴の提供も手際よくできる料理茶屋の出現が不可欠となったというわけです。これらの必要性は現代に引き継がれています。 さて、「蓮玉庵」の話題に移らねばなりませんが、もう一度、少しばかり江戸のファストフードについて触れさせてもらいます。江戸は、単身赴任の男性社会だったのです。江戸勤番の武士、出稼ぎの職人や商人などです。手間ひまかけず、手っ取り早く食べ物が口に入ればこれにこしたことはない、というわけでファストフードが喜ばれ、その代表例が「そば」だったのです。江戸時代後期、人口350人に一軒の割合で蕎麦屋があったそうです。
当時は注文が入ってからそばを打ち始め、お客さんは飲みながらゆっくり待って食べる、というのんびりしたものだったそうです。酒の肴は、今も出している板わさや、ヌキといわれる、そばのメニューからそばを抜いたもの(例えば天ぷらそばのヌキなら天ぷらをつゆにつけた品)だったといいます。 上野の山から落ちのびてきた彰義隊をかくまったこともあり、この界隈の歴史の証人といった存在なのです。現在のメニューは、せいろそば、天せいろ、天ぷらそば、おかめそば、玉子とじ、など、オーソドックスなものですが、天ぷらは朝のうちに衣をたっぷりとつけて揚げておき、つゆにつけて味を含ませて出すのが本来の形だといいます。 現在の店舗は、JR上野駅からでもJR御徒町駅からでも近いです。上野松坂屋に面した中央通りを挟んだ向かいにある「鈴本演芸場」横の仲町通りに店を構えています。湯島天神や不忍池や横山大観記念館から近いですから散策とセットでお出かけになるとよろしいと思います。写真は、過日「蓮玉庵」にお邪魔したときの店構えを写したものです。 |
||||
| 蕎麦屋の老舗物語 | |
| 木村 勝紀 2007年7月5日 |
|
|
蕎麦屋の老舗といえば「藪」「砂場」と並んで「更科」の三系列を掲げるのが通例です。それぞれに歴史と伝統と格式を誇りますが、今回は麻布十番の「永坂更科 布屋太兵衛」への訪問記をお届けいたします。 「藪」系 「砂場」系
創業は1790年と伝えられています。信州の織物の行商人をしていた清右衛門という人が、江戸での逗留先としていた麻布・保科家に勧められ、麻布永坂町で蕎麦屋を始めたとされます。開店に際し清右衛門は太兵衛に名を改め、開店時は「布屋 信州更科蕎麦所布屋太兵衛」との看板を掲げていたといいます。更科は、1880年代まで、のれん分けなどを一切せず、一軒のみでの営業を続けました。 「更科」の暖簾分け 「株式会社永坂更科 布屋太兵衛」へ 店内に入ると広々として調度も新しく清潔な印象でした。由緒を知らなければ200年続いた老舗であることに気が付かないかも知れません。 ビールを一気に飲んでほっとしていると、まずはそばつゆの入れ物が2種類出てきました(写真3)。「甘汁」と「辛汁」と書いてあります。要は自分の好きなほうを楽しめばいいのですが、混ぜて使ってもいいとのことでした。「御前そば」は、白くて細い上品なしろもの。「辛汁」を少しばかり付けてつるつると口に入れると、蕎麦の香りに加えて絶妙の口当たりと歯ごたえに思わずウーンと納得。老舗のネームバリューが加わって満足の逸品でした。 生ビール一杯のほろ酔い加減と「御前そば」の一枚を腹に収めて、意気揚々と地下鉄「麻布十番駅」に向かったのでした。 |
||||||||||||
| 「神谷バー」へ行って | |
| 高橋 照夫 2007年6月12日 |
|
神谷バーは浅草雷門のそばにあり、創業は1880年(明治13年)ですが、1912年(明治45年)に西洋風バーに改造し、わが国で始めてのバーとなりました。現在、1階神谷バー、2階レストランカミヤ、3階割烹神谷と複合店舗になっておりますが、今回は団体だったためレストランでした。 神谷バーは東京浅草ということもあって、多数の文学作品に登場しています。ということは、神谷バーを愛する数多くの文士、作家がいたことの証左でしょうか。 さて、お目当ての電気ブラン、これはブランデーをベースに、ジン、ワイン、キュラソー、薬草をブレンドしたしたもので、琥珀色の、ほんのりとした甘みのアルコール度は30度(オールドは40度)です。ユニークで上品なショットグラスに注がれて登場です。 口に含むと独特の風味がじんわりと広がってゆきます。ブランデーの香りと甘さのせいで、アルコールの強さはあまり感じません。 そして2杯目。ここで「生ビールをチェイサーにするのもいいですよ」とのアドバイスがありましたが、乾杯の大ジョッキは、時すでに遅く空っぽ。次回にチャレンジしてみましょう。締めはオールド。このタイプは熟成度が高いのでしょうか、私の味覚はマイルドな味わいに負けて、アルコールの10度違いは感じませんでした。 店を出るとき、「これぞ神谷バー」の雰囲気を知りたくて1階を見学しました。20時前だったので、店内は満席、お客はそれぞれ、みな楽しげにグラスを傾けていました。清潔感のある洋風居酒屋ですが、そのなかにほのかな昔ながらの下町情緒を醸し出していて、ふと、かつて1度だけ行ったことのあるロンドンのパブを思い出させてくれました。 お店で配布しているリーフレットに三浦哲郎の「忍ぶ川」にも神谷バーが登場していると紹介されています。この作品は彼の文壇デビュー作で、1960 年に芥川賞を受賞した純愛を描いた私小説です。神谷バーに思いを馳せて30数年ぶりに読み返してみます。 |
||||
| 芝崎納豆の由来 | |
| 芝崎 芳和 2007年6月12日 |
|
|
ちょっと古い話ですが、木村さん、岡本さん達が東京下町散策の折、神田明神に立ち寄られた際に、『芝崎納豆』なる看板を見付け、小生に関係ありや?、との質問があったので、このように答えた。
神田明神は大已貴命【おおなむしのみこと】を祭り、千二百年前、天正二年に武蔵国豊島郡芝崎村に創建されたが、その後、遊行上人が将門の霊を合わせて二座とし、社のかたわらに一字の草庵を建てて、芝崎道場(今の浅草芝崎町日輪寺)といった。この社と道場は慶長八年駿河台に、また元和二年には現在の所に移されたが、道場の寒暑堪忍の修法に供した五行珍味の中に金含豆【こんがんず】といって富貴延寿を祝福する穀種があった。 これが芝崎納豆の前身で、吾が祖両部膳所に関係ありし故を以て、その製法の直伝を受けた当店が、代々神社の表参道にあって、芝崎納豆の名のもとにこれを製造し、世に知られるに至ったものであります。 製造元 株式会社 天野屋『天野屋』は神田明神(正式には「神田神社」)の鳥井の右脇にある麹屋の老舗【しにせ】です。地下には広大な「室」があって,麹製造をはじめ,各種醗酵菌の保管をしていました。 納豆のお土産もよいですが、自家製の麹で作る「あま酒」は、江戸時代からの名物と聞いています。 「神田明神」に詣での節は一度召し上がってみてはどうですか。
|
||||||||||||||
| 江戸のファストフード | |
| 木村 勝紀 2007年6月8日 |
|
|
現代は街を歩けばフライドチキンやハンバーガーなどのファストフード店に当たる時代ですね。江戸時代にファストフード店があった、と言えば怪訝に思われるでしょうが本当にあったのです。以下は聞きかじりの受け売りの知識をお披露目することですから予めお断りしておきます。もっとも如何に偉い学者の説でも、最初は受け売りの知識から始まっているのですから、お許しいただきましょう。 「手軽に、早く、旨い物を」 <握り鮨> <天麩羅> <おでん> 江戸っ子の欲求から |
| 池之端薮蕎麦 | |
| 木村 勝紀 2007年7月25日 |
|
上野が江戸城の鬼門にあたるところから京都の「比叡山・延暦寺」にならって山号を東叡山にしたといいます。比叡山・延暦寺には琵琶湖がつきもの、そして琵琶湖には「竹生島」があります。上野「不忍池」を琵琶湖に似せるため、竹生島を模して「弁天島」を築いたという通説があり、そこにかの有名な「弁天様」が鎮座しているという訳です。 池之端の地名は、この不忍池に由来していますが、近くに池之端を冠した屋号を使う蕎麦屋があります。上野広小路の鈴本演芸場から湯島に向かう路地「仲町通り」の中にある「池之端藪蕎麦」(写真1)がそれです。 空いていると思われる日曜日の午後4時ごろ、暖簾をくぐって引き戸をそろりと開けてビックリ、ほぼ満席の盛況でした。さすがの老舗を思わせました。 |
||||||||
| 谷中の喫茶店「乱歩」と穴子寿司「乃池」 | |
| 木村 勝紀 2007年5月11日 |
|
この近辺は推理小説で有名な江戸川乱歩の生誕地なのです。江戸川乱歩の作品に「D坂の殺人事件」があります。このD坂とは団子坂のことですが、この小説の中に「白梅軒」という喫茶店が出てきます。今では場所を変えて不忍通りを渡った反対側の三崎坂【さんさきざか】の右側に「乱歩」という店の名前で現存しています。 マスターは江戸川乱歩の大ファンという店です。店の外観はいかにも古風で出がらしのお茶葉を乾かしたような佇まい(写真1)。中に入ると店の名前のとおり物がところ構わず乱雑に置いてありますが、煤けたインテリアに妙になじんで不快な感じにはさせません(写真2)。埋もれたスピーカーから眠たくなるようなレトロなジャズが流れています。マスターは70歳がらみのシャイで気さくなおじいちゃん。 途中でアルバイトらしき若い女子学生風が出勤してきてカウンターの中に入りました。別の客が「D坂がどうのこうの」と問いかけると的確に答えている。さすが「乱歩」の店員なのです。コーヒーは、まことによろしい芳香を醸し出し、乱雑ながらもゆったりした空間とスローなジャズにマッチして心地よい一服でした。これが心の贅沢というものでしょうか。 この「乱歩」とは道を挟んで反対側に穴子寿司で有名な老舗「乃池」があります。11時半開店を見計らって暖簾を潜ると、 江戸の寿司屋はこうでなくてちゃいけませんね。5〜6人用のカウンターと若干の椅子席の一階はもう満席で、さすがの人気寿司店を感じさせました。二階は十畳ばかりのお座敷で客はまだ居ませんでした。 「穴子」をお願いします。 程なく出てきた「穴子寿司」(写真3)は、脂がのって、口の中でトロリと溶けそうなほどやわらかい穴子と、甘すぎず辛すぎずのタレが絶妙なバランスで、つい口元がほころんでしまうほどの結構なものでした。やはり老舗らしい風格の満足すべき味でした。 芳醇な香りのコーヒーと穴子寿司をお腹にいれて、それから目的の団子坂方面への文学散歩に出かけたものでした。 |
||||||||||||
| 「弘明寺縁起」と「弘明寺銘菓」 | |
| 木村 勝紀 2007年4月26日 |
|
弘明寺という町は、弘明寺観音で知られた「弘明寺」の門前町なのです。 弘明寺観音の名で親しまれたこの寺は、古くは鎌倉幕府の源家、戦国時代の後北条家、江戸幕府の徳川家などの武家の信仰が厚かったといいます。鎌倉時代の「吾妻鏡」には、源頼朝公が源家累代の祈願寺として保護したと明記されています。 歴史のある門前町だけに参道は、参詣客や地元住民目当ての商店街になっており、お土産を売る店もあります。その中の銘菓を二つご紹介しましょう。
治承5年(1181年)源頼朝は源家再興の悲願を弘明寺観音に祈願しました。その折いずこともなく現れた一人の乙女が、柚子で作られたお菓子を頼朝公に献上したところ、公がこれを召され「観世音の慈悲にも似たる美味かな」と賞で勇気百倍、遂に源家再興の悲願を達成されたと伝えられます。「観音最中」はこの献上菓子に由来するもので、柚子餡と小倉餡の二色からなり、全国菓子博覧会でたびたび最高の栄誉を博している銘菓です。 ◇ 銘菓「かまくら路」(写真2右側) これらの銘菓を販売する盛光堂総本舗は、神奈川学習センターから鎌倉街道に出て、最初の信号を渡って左に折れ、弘明寺商店街入り口を越えて2軒目右側にあります。一度お試し下さい。 |
||||||||
| 伊勢路の赤福餅 | |
| 木村 勝紀 2007年4月17日 |
|
熊野といえば熊野古道、志摩といえば真珠となりますが、さて伊勢となるとどうなりますか? もちろん伊勢神宮ですね。しかし、「食」の話題となれば「赤福餅」を外せませんね。伊勢の本店を中心に主として関西地方で売っています。関東の人でも旅行や出張の帰りには、皆さんお土産にするのでお馴染みですね。 お土産用の「赤福餅」は、薄い小豆色の地にくっきり鮮やかな赤い文字で「赤福」と染め抜いた包装紙に包まれています。四角い折に収まった白い柔らかいお餅の上に、ほどよく甘さを抑えた餡子がのって、淡白ながらも甘い物好きの味覚を満足させてくれます。 発売元の「赤福」は、江戸時代中期、宝永4年(1707年)に初代治兵衛が伊勢神宮内宮の五十鈴川のほとりで餅屋を始めたのが始まりという老舗です。江戸以来お伊勢参りのお客様に親しまれてきた「赤福」は、2007年の今年が奇しくも創業以来300年という節目にあたります。 現在の「赤福」本店は、伊勢神宮内宮近くの「おかげ横丁」という郷土料理屋や伝統工芸品、種々のみやげ物店や飲食店などが立ち並ぶ商店街の中ほどにありました。「おかげ横丁」は、電柱をことごとく撤去し、石畳の道路を挟んで両側に木造建築を主体とした店が並び、すっきりした参宮街道のたたずまいをみせる気持ちの良い商店街でした。「赤福」本店は、その中にあって堂々たる老舗の風格を漂わせ、辺りを睥睨するかのごとくのたたずまいのお店でした(写真1)。店内で気軽に「赤福餅」を食することもできました。 「おかげ横丁」(写真2)では、国宝級の器も店頭に並べるという酒器の店で見つけた「ぐい飲み」のお土産もまた旅の思い出を彩る逸品で、しばしば手にとっては愛でつつ「般若湯」を頂戴しているのであります。 |
||||||||