| タイトル | 作 者 | 投稿日 |
| 対人恐怖とハサミ(読み切り) | 秋山智子 | 2011.12.24 |
| 風とたわむれて(読み切り) | 後藤雄二 | 2011.12.10 |
| フリーダム(1) (2) (3)最終回 | 熊倉都美 | 2011.11.04 〜2011.11.21 |
|
<< 作者およびホームページ委員会からのお知らせ>> すでに『星空文庫』にはこの作品以外のものも載せていますので、 『星空文庫 八木橋麻子』(http://slib.net/a/154)
|
||
| タイトル | 作 者 | 投稿日 |
| 私淑の人 (1)〜(7) | 後藤雄二 | 2009.4.01 〜 2009.10.1 |
| 面影の空に (1)〜(7) | 後藤雄二 | 2008.6.15 〜 2008.9.10 |
| 対人恐怖とハサミ | |
| 秋山智子 2011年12月24日 |
|
|
キタ氏は、昨年春、アヤメとともに、管理課に異動してきた男性である。 異動後1週間が過ぎたころ、同じ課の女性が、職場に来なくなった。 そうした嫌味はさておき、彼女があれこれ理由をつけて出勤しなくなったのである。 こうして、キタ氏の身辺は大げさに、かつ騒々しく彩られながら1年がたった。 異動からひと月ばかりたったある日のこと。 ともかく、これは想定外である。 このように、G氏に一旦引き渡された仕事は、それも束の間、再びキタ氏に戻されることになった。しかも彼には、班長としての仕事もある。 いずれにせよ、皆が皆、キタ氏になれるわけではない。 |
( 了 ) |
| 風とたわむれて | |
| 後藤 雄二 2011年12月10日 |
|
|
仕事も一段落し、所用のため外出すると、新聞配達のバイクとすれ違った。午後二時半だった。ずいぶん早くに夕刊配達をするものだと思った。貴司はふと自分の中学二年生の頃を思い出した。昭和四十九年。その頃は、中学生もよく新聞配達をしていた。現代の中学生はアルバイト自体が禁止されているらしいが、貴司の中学生当時は、特に厳しい校則もなく、貴司も自由に新聞配達などのアルバイトをしていた。 貴司は中学生になると、地域のシンフォニックバンドに加入した。二歳年上の兄が参加していたこともあるが、自分も楽器を吹けるようになりたいと思っていた。兄と同じクラリネットを吹くことになったが、楽器は高価なので、すぐに自分の楽器は持てない。バンド所有のクラリネットを借りて、練習が始まった。兄は自分のクラリネットを持っていたが、それは小遣いを貯め、計画的に購入したという。兄の堅実さは子どもの頃からのもので、大人になった今も、弟妹たちからの兄への信頼は絶大なものだ。 貴司は二年生の五月頃、友人数人とで、夕刊の配達を始めた。一カ月を過ぎると、ほとんどの友人が配達の辛さにアルバイトを辞めた。数カ月後には、一緒に始めた仲間は、貴司と和喜だけになった。和喜は中学校を卒業すると、高校へ進学せず就職した。貴司は、その後、朝刊配達に移ったが、高校三年生の五月まで新聞配達を続けた。貴司は働くことを少しも苦に思わなかった。勉強よりも働いているほうが性に合っていた。給料は全部母に渡した。家計の役に立つならそれでいいと思った。 文化祭を控えたある日から、音楽部の練習が本格的に開始された。部活に参加しない日は、学校が済むと、すぐに夕刊配達ができたが、その日からふだんより遅く配達をすることになった。配り始める時には、すでにあたりは薄暗く、夜になろうとしていた。当然、家々からいくらか苦情が出ることになる。いくら苦情が出ても、ますますそのような日が続くものだから、貴司は慌てながら、ひたすら、申し訳ありません、と頭を下げて、一軒一軒に夕刊を配った。 所用を終え、貴司は職場の学習塾に戻り、コーヒーを一杯飲んだ。ひょんなことで、懐かしき夕刊配達の思い出にひたることになった。その思い出と共に貴司の耳には、中学二年生当時のクラリネットの音色が聴こえてくる。拙く弱々しい音色がひろがる。自分のクラリネットがほしい、と夢にまで見た日々。あこがれ続けたショーウインドーの向こうのきらきら輝くクラリネット。そして、それを父母に買ってもらった中学三年生の春の日のこと。その夜、貴司はクラリネットをケースごと抱いて寝た。そして毎日毎日練習した。会心の美しい音色をいつも目指していたが、それはいつまで経っても、初心者の音色だった。名クラリネット奏者のレコードを聴くたびに、自分には果てしなく遠い道のりがあると感じた。青い翼をひろげることさえできず、飛び立ち始めることのできない中学生のクラリネットの音色。それはいま、数年を経て、遠い音色となりつつあるが、それでも貴司の耳の中で、その未熟な音色は鳴り響き続けている。 中学二年生のときから数えて、三十七年を経た今、あの喫茶店はどうなっているのだろうか。貴司はふとそのような気持ちを抱いた。ゴールデン・ウィークで帰省するのにまかせて、貴司はその場所に行ってみることにした。 ミスターC主催・フォークコンサート コンサートの実施を知らせるパネルが、彼女らが演奏している場所の上部に吊るしてあった。 「これもご覧ください」 オリジナル曲が主の彼女たちですが、この「風とたわむれて」は、私の敬愛する歌手、ペリー・コモの代表曲の一つです。ベット・ミドラ―の大ヒット曲のカヴァーではありますが、コモの熟練したヴォーカルには、ずいぶん酔いしれたものでした。コモの音楽との出会いは私が五十歳のときでした。ある日、ラジオから映画「追憶」のテーマが流れて来ました。何人かの歌手の聴き較べの番組だったのですが、コモの「追憶」を聴いたとき、とにかく歌のうまさに驚きました。穏やかな歌声に聴き入りました。そして、コモが、フランク・シナトラ、ビング・クロスビーと肩を並べるアメリカを代表する名歌手であることも知りました。 マスターは、この二人の歌を心から愛している。そして、ペリー・コモの歌を大切に思っている。コメントを読みながら、貴司にはそれが強く伝わった。 デュオが訳した「風とたわむれて」は次のような歌詞だった。 君はいつも僕のことを 表舞台にいるのは僕 君は僕のスターなのさ だけど気がつかなかったんだ 君は僕のスターなのさ 君という風のおかげさ 貴司は、マスターの人生にも、きっと紆余曲折があったにちがいないと思った。女性デュオに対するマスターの優しさは、いったいどこから来るのだろう。ペリー・コモの歌はよく知らないが、マスターが彼の人柄に心酔するのも、また、風のようにマスターの翼を支えてくれた今は亡き夫人への想いを吐露するのも、マスター自身が人として成長したことのあらわれなのだろう。 |
( 了 ) |
| フリーダム (3) | |
| 熊倉 都美(ペンネーム:八木橋麻子)
2011年11月21日 |
|
|
笑い合っている二人と、ホームレス一人が見えた。その笑い声に安心した私は、ヒッキーの「Etanally」を聴きながらゆっくり寝始めた。その曲はピアノの音から始まり、ドラマの主題歌とマッチしていて、とても感動的だった。歌詞は曲を紡ぐひとつの役割でもあり、主題でもある。ヒッキーはまた、ブログに何か書いてるんだろうな。有名人だから、手が届かないけれど。するとさんまの匂いがし始めた。秋になっていくこの季節は、さんまが大量に釣れるから、安く買える。そういえば、ママとスーパーに行ったっけ。生さんまが一匹80円で、家族の分を全部買っていたのを思い出した。ママは魚をさばくのが上手だった。ママがさんまをさばいている情景が浮かんだ。しかし、料理好きのママは、ここにはもういないんだわ。今もまだ、パパが惣菜を買ってきて、それを食べるのが日課なんだ。冷たいコロッケと、ひじきの和え物。焼きたての、熱々のコロッケを作るママは、ここにはもういない。Etanallyを聴きながら寝ている私の目から、自然と涙が流れていたのが判った。蒸し暑さが充満して、私のシャンプーの匂いがするテントは、訝しげな目でこちらを見ていた。私は上に見えるテントを無視した。Etanallyはゆっくりとその曲の幕を閉じ、私は寝た。私がごろごろしながらテントの毛布にくるまって、もう一週間が過ぎようとしていた。朝と昼になると耕一がやってきて、無理やりにでも何か口にさせようとした。炊き出しのものではなく、さっぱりとしたサラダを私の口に運ぶこともあった。夜中もまた来て、今度は栄養ドリンク。こんなに食べていたら、ただ寝続けるだけなのに、豚になっちゃうわよ。浩二がいつも炊き出しのメニューを考えているようで、だからホームレス達も飽きがこないんだと、そう思った。耕一は私が回復していく頃には、引越しの仕事に行っていた。朝五時からお昼までの時間で、よくこなせるなと思った。しかし正社員なので、まあまあ自由がとれると、耕一は言っていた。浩二はというと、夜の六時半にはここを出て、夜中の二時に帰ってくる。警備員にしては安いお給料。バイトだからかしら。 ☆ 「みんなやっちまっていいぜ、力有り余って仕方ねえだろ、ただ相手から手を出してきてからだ」私はテントの隙間から再び砂場の向こうを見た。実だ。男も数人連れて、やってきたのだ。なんて卑怯。 「おーこういっちゃん。俺は昔柔道をやったことがあるが、若者相手にそりゃきかねえだろ。目潰しがある」 おじさんは催涙スプレーを取り出して、手に持った。浩二はさんまの残骸をコップに入った水でじゅっと蒸気を抑えた後、再びビニールをかけて、テントの横に持っていった。耕一は実にちょっかいを出しながら、ちょうど中間地点のところにいた。みんなそれぞれ、鍋だの棒切れだの持ちながら実に近寄っていった。今度こそ終わりだ。ここも、あいつらも。せっかく楽しくやっていたのに、それをぶち壊すなんてあんまりだわ。実たちは、おじさん達よりも物凄い武器を持っている。ナイフに本物のライフル銃。それに実の手には、マッチ。 「やめて実! ここをぶち壊さないで、あなただってやり直せるのよ。ここの人達を殺したら、今度は刑務所から一生出られなくなるわよ!」 「まこっちゃん、いいから隠れてな。俺らは覚悟でここにきたんだ。判るかい。危険じゃない場所なんぞ、どこにもないんだよ。いつだって人は危険の中にいんだ。俺はもう充分に生きたし、楽しんだ。未練はねえ」 それがおじさんの最後の言葉になった。催涙スプレーは手から零れ落ち、ライフル銃の玉が、おじさんの心臓へと打ち抜かれ、まるでスローモーションのようにおじさんは仰向けに倒れた。私はおじさんが倒れていく姿を目に焼き付けた。血がぶしゅっと噴出したかと思うと、私の頬にあたり、伝った。左手で血を触ると、おじさんの血だとすぐに判った。私はしばらくおじさんの顔を見て、ゆっくりと横に頭をもたげるのに気づいた。おじさんの脈をすぐ調べたが、音がなるまでには至らなかった。あんな銃で打たれたら即死だということは判っていた。それでも私は人工呼吸を続けた。まだ生きているかもしれない。生きているかもしれないんだ。おじさんのお陰で、あごの傷は治ったのよ。しかし、必死に人工呼吸をしたけれど、おじさんは目を剥いたまま、赤い空を眺めていた。濃い赤い空が、おじさんの血を物語っているような気がした。上を見ると、赤い空が、泣いていた。赤い空が、何か言っていた。空は神様なんかじゃないわ! 私はふいとおじさんの胸に手をやり、人工呼吸を続けた。どうか、死なないで。死なないで! 赤い空がゆっくりとおじさんの顔を照らし、その赤い光が私を映した。しかしおじさんは、即死だった。目を手で優しく閉じさせると、私はありったけの声で叫んだ。サイレンのようにいつまでも鳴り止まない声は耕一を責めた。耕一、あんたって、あんたってやっぱりあの人達の手先だったのね。信じた私が馬鹿だった! 本当に、馬鹿だった。 「真琴!」 私は思いっきり耕一の右の頬を平手打ちした。 「あんたって最低ね! 人が死んでもなんとも思わないの、おじさんが死んだのよ。あのおじさんが」 「ああ、最低なんだ」 すると耕一の目から光ったものが見えた。幾度も幾度も止まらない涙が、持っている紙に滲んで、私に手渡した。鉛筆で書かれたようなその何枚もある手紙は、まるで遺書のようだった。 「あのおじさんには家族も何もいなかったんだ」 耕一は嗚咽を出しながらこう言った。 「末期がんだったんだ」 私は震えた手で耕一からその手紙を貰った。止まらない嵐達は容赦なくこちらを狙ってきて、一人のおじさんは、私の仕返しとでもいうように鍋で実の頭をぶん殴っていた。私はどちらの味方にもつけなかった。今耕一を信用するわけにもいかなかった。ただ泣き崩れて、横にそれていく銃から、身を守ることしかできなかった。耕一はテントに戻れと言ったが、それを無視して、私はおじさんの体に持たれこんだ。さっきまで温かかった体が、生きていた体が、冷たくなっていくのを感じた。男らは、至近距離でライフルをぶっ放すのだけは辞めていた。殴る蹴るのお互いの喧嘩のようなものが、延々と続いていただけだった。私はおじさんから貰ったその遺書を、ぎゅっと握り締めていた。ぎゅっと握り締めた手に汗が滲んで、鉛筆で書かれた文字が消え去りなくなくりそうだった。 「あの人達は俺の事情を判りながらも、最後までここにいてくれたんだ。だから協力してくれたんだ」 「あんたは黙ってなさいよ! この裏切り者!」 耕一は立ちすくみ、自分の中で、これが正しかったのか否か考えているようだった。こんなの、正しくもなんともない。私がおじさんの顔を思いっきり引っぱたいても、おじさんは起き上がるどころか瞳孔が開きっぱなしだった。耕一の涙が私の首下に伝った後、次の涙はライフル銃で二つに割れた。 「おいリーダー。こんなしけたところで、何やってんだよ」 「俺はもうリーダーじゃない。お前はただの殺し魔になっちまったんだな」 すると至近距離から耕一の右肩を打った。玉は耕一の右肩を貫通し、砂にぼとっと落ちたかと思うと、はねもしなかった。血は胸のほうに流れて、砂を血まみれにした。ぐっと唸る耕一は、右肩を抑えて蹲るように苦しんでいた。あの美しいダイヤモンドの砂は、血とは混ざりたくないと言ったような気がした。頬が血だらけの私を見て、男は笑いながらこう言った。 「実の次の女なんだろ? 耕一もずいぶんやり手だな」 私は男をきっとにらめ付けた。 「あんたはただの暴走族なんかじゃない。二人も撃った」 「それがどうした」 笑いながらその男は言うと、実が駆けつけていた。髪の毛から血を滴りながら。 「もうやめなさいっつってんだろ、おやじは死んだだろ。あたしの耕一まで撃って、何やってんだよ」 マッチ持っているくせに、何を言っているんだろうこの女。はは。ここを全部燃やし尽くそうと思っていたくせに、今更何を言っているんだろう。やり直せない女って、いるのね。実、あなたはただの犯罪者よ。言い尽くすべきところもないただの犯罪者。耕一がリーダーだからって、惚れてもいないくせに、ただその座を手にしたかったのね。私は耕一を一瞬裏切ろうと思ったが、裏切るわけにはいかなかった。あんなに沢山のことを教えてくれた。見返りも求めずに。私は一瞬耕一を疑っていた。でも、違った。耕一は一切手を出さない。ホームレス達の争いが終わりかけそうになった頃、救急車と警察がやってきた。このことで、耕一の考えていたことがすぐに判った。警察は、鋭い武器を持った連中よりも、弱いこちらの方に、味方をするのだと思い呼んだのだ。しかし警察達が来る前に襲われてしまった男性を、救うことができなかった自分に、腹が立っていたのだ。きっとあの遺書も、捨て去るべきだと男性に促した筈だ。しかし死んでしまったおじさんからの要望で、私に手渡したのだ。私達は何もしていない。鍋や棒切れで、ライフルやナイフに勝てると思うの。私達は、何もしていない。しかし、疑問が残る。ただやっちまえと言えば、警察だってこっちに目を配る。何か一人で策を練っていたのかしら。何にしろ、ギターを弾けなくしたこの男と実に憎しみが舞い上がってきた。炎の中で燃え上がる憎しみが、憎しみを呼び、炎はどんどん大きくなっていった。私は実に、貫通した玉を顔にぶつけると、くすっと笑った。相手を最大限に憎むとき、人はつい笑ってしまうのだ。不気味なおもちゃのように。赤い空から慈しみの念が降ってきそうだった。実は汚そうに顔を拭った。一人の警察官がピストルを持ち、男に銃を捨てろといった。仕方なくという風に、男は銃を下ろした。こいつは前も人を殺してきたんだ。こういう風に。ライフル銃なんて、どこで手にいれたというの。救急隊員が、私達の元に来ると、あなたが殺したのかと、実にそう言った。首を横に振る彼女はマッチをポケットに隠した。それに気づいた隊員は、いぶかしげな顔で実のジャケットの方を見た。こちらも何かあるようです、と。警官を呼んだ救急隊員は、実の体をぽんぽんと触ると、何か四角いものが入っていると気がついた。取り出した隊員は、これで何をしようとしていたのか瞬時に判った。殺したのは女ではなく男であって、火災を起こそうとしたのは女だと。浩二がいきなり襲ってきたんだというと、ここの公園で何をしていたんだと訊かれた。ボランティアだと言うと、二人の警察官が怪しげにこちらを見ながら公園にあるテントひとつひとつを見ていった。許可を取ってあるのかないのか、実は食い物にしようとしていたのではないかと、次々に答えさせられた。浩二の目に涙はなく、ただ淡々と答えていた。警官と刑事が疑っていたテントの中には寝巻きや、趣味の雑具があるだけで、他には何もなかった。重傷の耕一を、救急隊員は急いでタンカに乗せた。私も乗せてと言ったが、親類でもない私を乗せようとする隊員は誰もいなかった。耕一はひとつの紙切れを私に手渡した。どうして、おじさんも耕一も、そんな遺書のようなものを私に手渡すの。私は大雨が降る中で、ぽつんと一人、立ちすくんでいた。浩二が私に呼びかける声が聞こえたような気がしたが、私には何も聞こえなかった。鉛筆で書かれた二つの手紙は、どしゃ降りの雨で、濡れていき、私は大切な宝物のようにエプロンのポケットに入れた。髪の毛から滴る雨は、私の頬を伝い、泥になった砂と共に消えた。ずぶ濡れになった私は、何を思ったのか、泥で顔を洗うように塗り付けていた。彼らの血と、あの美しいダイヤモンドの砂を塗りこむように。ゆっくりと顔をあげると、私はしばらくここから離れることが、できなかった。 ☆ 私は起き上がると、そこは私の部屋だった。私は夢か……と思うと飛び上がり、自分の体を触った。あのエプロンだった。そして自分の顔を触ると泥はついていなかった。周りを見渡すと、高校時代の私の写真が張ってあり、ピンクのカーテンは、どう見ても私のもので、部屋だった。思い出しエプロンのポケットから二つの紙を取り出すと、おじさんの言葉にはこう書いてあった。ママの明るい声が聞こえた気がした。「真琴ちゃん、俺には身寄りも誰もいなかった。嫁さんはあの世に逝っちまったし、子供達は都心に行って戻ってきやしねえ。介護を呼ぶにも金はかかるし、入院するにも金がかかる。末期のがんだって知ってから、俺はふらふら外を出歩いて、短くてもいいから、生きたかったんだ。こういっちゃんから声を掛けられたときは、俺なんかが……と思ったんだが、入ってみると面白くてね。ここは面白い場所だった。退屈しないしな。真琴ちゃんが入ってから、更に面白くなったよ。あんたにはまだ夢がある。自由もある。責任もな。俺に何かあったとき、これを読んでくれとこういっちゃんに頼んだんだ。今までありがとな、真琴ちゃん」 大きな文字で書かれた手紙は、震えたような手だったような気がした。この数文を書くだけで、何枚にもなっている。思い出すとあのおじさんは、いくつだったのだろう。多分七十手前か、その辺だった。今はいつで、何時なんだろう。私はケータイを取り出してみた。あの事件が起こったのは、確か八月十三日で、今は九月二十四日。時間は朝の十一時で、曜日は土曜日だった。あれから一ヶ月も経ったんだ。私はもうひとつの、耕一の手紙を読んだ。短く雑に破ったノートの破片だった。 「090-○○○ー1158 you」 と書いてあるだけだった。Youの次? それとも前? 雨に濡れて、鉛筆で書かれた文字はかろうじて見えそうな気がしたけれど、私はわざと見ないようにした。私に愛しい悲しみだけを残して、去っていったあなた達は本当に馬鹿よ。大ばか者。私はあの思い出達を心の中に少しだけ、少しだけ封印した。心から楽しいと思える日もあった。しかしそれと共に痛みをも知ったからだった。ニュースをつけると、あの中村さんが富士山を上りきったとアナウンサーが言っていた。危険を伴いながら頂上で水を飲む中村さんはとても粋で、思わず拍手をしそうになった。中村さんも、みんなも、どこかで生きている。 「ちょっと真琴!母さん心配したのよ。パパなんか大慌てで仕事にも行けなかったのよ」 どんどんと、叩くドアの向こうに、本物のママがいた。 「ママ」 「ママよ。デイケアに行くことにしたのよ。一ヶ月間ボランティアなんてして、事件に巻き込まれて……どうしちゃったのよ。顔をはたいても起きなかったのよ」 「ママ!」 私は思いっきりママに抱きついた。ママは苦しそうに、ぶら下がる娘をよしよしと頭を撫でた。本物のママだ。夢じゃない。私はママから手を離すと、中村さんの映像を見せた。ママは何これ、といわんばかりに頭を傾げた。私は一人ではしゃいでいた。しかしふと、耕一のことが頭から離れなくなった。 「ねえママ、耕一は、生きてるの?」 「耕一……?ああ、鈴木くんのことね。あんたケータイ置きっぱなしであそこから逃げたんでしょ」 私はママの顔をじっと見つめていた。 「生きてるわよ。まだ病院みたいだけど、午前中からあんたのケータイが鳴りっぱなしでうるさかったわよ」 私は一瞬、耕一の元に電話を掛けようと思ったが、辞めた。耕一も病院から退院したら、使えなくなった右手ではなく、きっと左手で弾く。狐目のあの男なら、きっとそうする。アコースティックのメロディーが頭に流れてきた。耕一はまだ、私と関わるべきじゃない。耕一もまた、生きている。自由に、そして責任を持って。優雅に北欧の踊りなんかしながら。つららはぱきっと折れて、私の頭を突き刺した。ママに就職活動のつてがあるかどうか聞いてみると、任せなさいと言わんばかりにウィンクをした。あれから半年の三月、雪が解けて春になる頃、私は小さな企業のOLとして働くことになった。地味で、パソコンにばかり面と向かう私は、なんだかあの頃とはちょっと違うみたい。昼になるとおばさん達に連れられながら、昼食を取っていた。あの定食屋で。マスターは耕一の心配をちょくちょく私に聞いてきた。しかし私は何も知らない。マスターは、ロコモコをテーブルに置くと、金は要らないよとでもいうように、人差し指と親指で丸を作り、それからばってんをした。あの頃と同じように、目玉焼きとデミグラスハンバーグ、レタスにパイナップル。思い出しそうになりながら、黙々と食べていた。おばさん達も同じものだ。『真琴なら好きそうな味だ』、ふと振り返ると、ガラス窓には誰もいなくて、私は目を虚ろにしながら最後の一口を食べた。とても美味しかった。うん、美味しい。それと共に涙が溢れ出してきた。思い出をすべて消し去ろうとした。消してしまおう。どうしたのとおばさんは声を掛けるけれど、私はなんとでもないよと発して、そこで昼休みは終わった。夕方になる頃、私の定時は十七時で、黒いスーツを身にまといながら、まだ寒い冬の中をハイヒールで歩いていた。あの時ニュースで見たけれど、実は23歳だったらしい。実は一年三ヶ月の懲役。男も、懲役20年を受けて、すべてが終わろうとしていた。私は慣れないハイヒールを履いて、後ろを振り返った。死んだおじさんの言葉が、聞こえたような気がした。思い出達が雪の降るこの頃に、夏の照りつける日差しを思い出していた。ああ、あの恋しい夏。氷水をくれた耕一。必死に守ろうとしてくれた浩二。私は明日の仕事の片づけを今日中に仕上げなければと、走って家路にたどり着こうとしたが、ハイヒールが雪で邪魔をして、私は10cmもある雪の中へ放りこまれた。ああ。冷たい。雪できんきんする顎を抑えると、噴水が舞い降りてくる丸い円のレンガ作りの椅子のようなものに、誰かが座っていた。 「ちょっとあんた」 背の高い男性が私に触れようとした。私はその男性を見上げると、思わず雪をも蹴飛ばすような勢いで後ずさりした。耕一だ。ああ。連絡もしなかった私を殺そうとしてるの? 私はあの事件からまだ抜け出せずにいた。怯えながら耕一を見る私は、耕一にとっては不愉快だったような気がした。右手には義手の手をつけて、耕一は私を見ると、だいじょうぶかと言うように手を差し伸べた。冷たい手。あの頃とはまったく違う。しかし差し伸べられた耕一の左手を握った私は、じんわりと温かい感触が私に伝わってきたのが判った。 「義手になっちまったけど、左手でギターをマスターしたんだ。俺はどの企業にも入れるけど、今は入りたくないんだ。少し休みたい。自由にな」 「耕一」 私はぐいっと手を捕まれてレンガの椅子に座らせられると、  「何回もお前に電話掛けたんだぜ、今頃になっちゃもう遅い」 耕一は真剣にそう言うと、違う違うと首を横に振った。 「今はどうしてるの」 「浩二のところにいる。しばらく経てば、また働ける。それに」 私は雪を蹴っ飛ばすと、 「お前とも一緒に暮らせる」 と言った。 「はああ?」 「はは、お前あの手紙読んだだろ、伝わらなかったのか」 耕一はそう言うと、自分で作ったという曲を、アコースティックのギターで聴かせてくれた。雪が舞い散る古い駅にも、人がどんどん集まってくる。コインを入れる人もいれば、一万円を放り投げるおじさんもいた。耕一の声は透き通っていて、どんな駅にも響き渡るような気がした。最後に愛の言葉を言って、終わった。大勢の拍手たちが私達二人を見つめていた。なんだっていうの? 英語の歌詞じゃさっぱり判らない。 「自由っていうのはな」 耕一が義手で私の肩を抱いた。 「こういうことを言うんだ」 私は耕一の言いたいことがやっと判った。ホームレス達に、『やっちまえ』と言った言葉の意味も判ったような気がした。私達はみぞれ混じりの雪が降る中、静かに、寄せ合うように、していた。自由、だった。 |
〜 了 〜 |
| フリーダム (2) | |
| 熊倉 都美
2011年11月11日 |
|
|
「どこへ行くの」 |
〜 次回(3)に続く〜 |
| フリーダム (1) | |
| 熊倉 都美
2011年11月4日 |
|
私は家出をした。黒いショルダーバッグに、化粧品やら風呂道具、数枚の服に寝巻き。流行だったプチ家出とも言えないし、つてがあって家を出て行くわけでもない。十九歳の私は少し前まで高校に通いながら水商売をしていたし、そんな世界に入って今更就職ということもない。アパートには引きこもりの叔父とパパとママがいる。パパは建設会社の下っ端で、ママはというと鬱病だ。叔父もママも私にとっては害でしかなかった。しかし私もお水で稼いだお金を貯めるわけでもなく消費していた。私はこの家にも自分にも、嫌気がさしていたんだ。しかしどこに行くつもりなのか、これからどうやって生活するとか、考えて出てくる筈もない。ということで、つまりは何のあてもないってことだった。私は夏の暑い照り付ける光を浴びながら、ショルダーバッグを背負い、一人川沿いを歩いていた。左手にはすぐ小さな、もう廃れたような公園があるけれど、誰がそんなところに居座るかってんだ。まるでホームレスじゃない。ホームレスなんて生きる価値もない軍団がただ勢ぞろいしているだけじゃ……
☆
朝六時になって、私は早速起きる羽目になった。耕一は朝五時に出勤したらしい。朝は冷房もなくてもちょうどいい温度だった。湿度は少しばかり高いが、昨日よりマシだった。昨日の夜食はさんまの缶詰だった。秋ごろになりそうなこの時期には、さんまはいいのかもしれない。今までさんまの缶詰をまともに食べたことがなかった私には、口に合わなかった。しかし食べたのだった。ご飯は一番安いものを使っているらしい。お酒を飲むホームレスもいた。将棋をしながら、楽しむホームレスもいたが、私は一人で音楽プレイヤーを聴きながら、自分の世界に浸っていたのだった。
|
〜 次回(2)に続く 〜 |
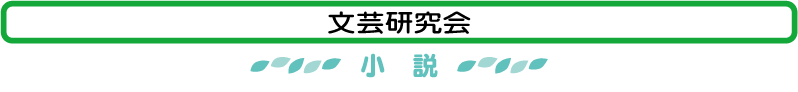
 痛さはなかった。さっきのあの凄まじさが頭に焼き付いて離れなかった。実……あなたも、やり直しが利くんだからね。ふと目を閉じた私を、大勢の人が見守り、処置をした。耕一…あなたって、やり直したのね。人間として。私はどうだったのかしら。まだあの水商売から抜け出せないでいるのかしら。人間って……私は夢の中にいた。ママやパパが私のバスデーパーティをしてるみたいで、ホールのケーキにろうそくが19個。19歳の誕生日を祝ってくれるのね、パパ、ママ。真っ白なケーキに氷菓子で作ったお人形さんが二つ。私はそれが嫌いで、避けて食べていた。この上もなく甘く、甘く口の中が塩を欲しがっているみたいだった。ママは微笑んで『真琴、就職活動、頑張るのよ』、そんな声がした。ママ、寝たきりじゃなかったの?三人で囲い込むケーキはすべてなくなり、ご飯も何も必要としなかった。そしてテーブルとケーキの箱が台風で飛んだみたいに、ママもパパも消えた。声がするだけで、部屋には誰もいなくなった。私は一人になって、ママとパパを探した。深い迷路の中に入って、足にまとわりつく雑草を足で追いやった。狭い迷路の両手にあるのは枯れた雑草のようなものが生い茂っていた。遠い向こうを見ると、あそこには何もなくて、ただ白い景色が見えただけだった。こちらをすっと照らし出す白い光は、天国にも狂気にも思えた。恐ろしく、私は走っていた。息を切らせながら、ママとパパを探していた。ママ? パパ? どこにいるの。私を一人にしないで。頑張るから、一人にしないで。お願いだから、私を孤独の底に突き落とさないで。私は雑草によって足をくじけた。ふと、目を開けると、真っ青なテントが見えた。パパとママはこんなところにいるの?
痛さはなかった。さっきのあの凄まじさが頭に焼き付いて離れなかった。実……あなたも、やり直しが利くんだからね。ふと目を閉じた私を、大勢の人が見守り、処置をした。耕一…あなたって、やり直したのね。人間として。私はどうだったのかしら。まだあの水商売から抜け出せないでいるのかしら。人間って……私は夢の中にいた。ママやパパが私のバスデーパーティをしてるみたいで、ホールのケーキにろうそくが19個。19歳の誕生日を祝ってくれるのね、パパ、ママ。真っ白なケーキに氷菓子で作ったお人形さんが二つ。私はそれが嫌いで、避けて食べていた。この上もなく甘く、甘く口の中が塩を欲しがっているみたいだった。ママは微笑んで『真琴、就職活動、頑張るのよ』、そんな声がした。ママ、寝たきりじゃなかったの?三人で囲い込むケーキはすべてなくなり、ご飯も何も必要としなかった。そしてテーブルとケーキの箱が台風で飛んだみたいに、ママもパパも消えた。声がするだけで、部屋には誰もいなくなった。私は一人になって、ママとパパを探した。深い迷路の中に入って、足にまとわりつく雑草を足で追いやった。狭い迷路の両手にあるのは枯れた雑草のようなものが生い茂っていた。遠い向こうを見ると、あそこには何もなくて、ただ白い景色が見えただけだった。こちらをすっと照らし出す白い光は、天国にも狂気にも思えた。恐ろしく、私は走っていた。息を切らせながら、ママとパパを探していた。ママ? パパ? どこにいるの。私を一人にしないで。頑張るから、一人にしないで。お願いだから、私を孤独の底に突き落とさないで。私は雑草によって足をくじけた。ふと、目を開けると、真っ青なテントが見えた。パパとママはこんなところにいるの?