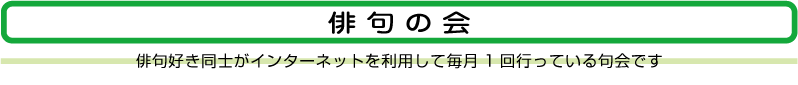| 2007年 |
| 2007年12月 | 第46回句会 | 作品 短評 |
| 2007年11月 | 第4回吟行句会 | 作品 |
| 2007年11月 | 第45回句会 | 作品 短評 |
| 2007年10月 | 第44回句会 | 作品 短評 |
| 2007年9月 | 第43回句会 | 作品 短評 |
| 2007年8月 | 第42回句会 | 作品 短評 |
| 2007年7月 | 第41回句会 | 作品 短評 |
| 2007年6月 | 第40回句会 | 作品 短評 |
| 2007年5月 | 第3回吟行句会 | 作品 |
| 2007年5月 | 第39回句会 | 作品 短評 |
| 2007年4月 | 第38回句会 | 作品 短評 |
| 2010年分はこちら | 2009年分はこちら | 2008年分はこちら |
| 第46回 句会 (2007年12月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| よくもまあ角にあつまる落ち葉かな | 野路 風露 |
|
| 古時計鐘の音響く冬座敷 | 千草 雨音 |
|
| 月面に沈む地球や冬に入る | 松本 道宏 |
|
| 銃声のあとの黙【しじま】や木の葉散る | ひらと つつじ |
|
| 碁敵を負かし勤労感謝の日 | 吉田 眉山 |
|
| 神の留守境内かける餓鬼大将 | 飯塚 武岳 |
|
| 銀杏散る赤門の屋根江戸小紋 | 奥隅 茅廣 |
|
| 石和の花木漏れ日そっと包みける | 菊地 智 |
|
| 陽だまりに猫も寄り添う今朝の冬 | 木村 桃風 |
|
| 湯豆腐や湯気の向こうに父母の笑み | 長部 新平 |
|
| 木枯らしの吹き付けし夜や仮住まい | 益子 紫苑 |
|
| 漬け物に赤い南蛮冬はじめ | 芝崎 よし坊 |
|
| 湯豆腐のことりとゆれて一人酒 | 舞岡 柏葉 |
←最高得点
|
| ■ 短 評 ■■■ 第46回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| 銃声のあとの黙【しじま】や木の葉散る | ひらと つつじ |
| 銃声が木の葉を散らした訳ではないが、銃声の後の一瞬の静寂に木の葉が散ったという感覚的な句である。 | |
| ★ 入選句 | |
| 銀杏散る赤門の屋根江戸小紋 | 奥隅 茅廣 |
| 赤門は東京大学の南西隅の朱塗りの門であろうか。その赤門の屋根に江戸時代の小紋模様を発見された作者の感性が良い。 | |
| 碁敵を負かし勤労感謝の日 | 吉田 眉山 |
| 碁敵ほど日頃仲の良い友達はいない。勤労感謝の日に碁敵を負かした気分は爽快であったであろう。碁敵とは何んの関係もない配合がずばりと決まっている。 | |
| 神の留守境内かける餓鬼大将 | 飯塚 武岳 |
| 諸国の神々が出雲に集まるため留守になるという境内を、餓鬼大将が家来を引き連れて駆けずり回って遊んでいる様子が眼に浮かぶ。「神の留守」が利いている。 | |
| 湯豆腐のことりとゆれて一人酒 | 舞岡 柏葉 |
| 既に多くの俳人によって詠まれている光景であるが、「ことりとゆれて」と「一人酒」で共感を得た句である。 | |
| ★ 並選句 | |
| 初時雨海みる少女赤い靴 | 飯塚 武岳 |
| 湯豆腐や湯気の向こうに父母の笑み | 長部 新平 |
| 一人居の眠れぬ夜やもがり笛 | 益子 紫苑 |
| 水槽に沈む大鰐山眠る | ひらと つつじ |
| 漬け物に赤い南蛮冬はじめ | 芝崎 よし坊 |
| 第4回 吟行句会 (2007年11月24日 金沢八景 参加者:8名) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 龍となる柏槙(びゃくしん)の幹冬空へ | 舞岡 柏葉 |
| 光あび舫うヨットや冬日和 | 野路 風露 |
| 小鴨浮き満ち干見守る照天姫(てるてひめ) | 吉田 眉山 |
| 日蓮と問答ありし寺小春(上行寺にて) | 松本 道宏 |
| 坂のぼり鳥の目で見る山紅葉 | 千草 雨音 |
| とんび舞ふ空の青きや石蕗の花 | ひらと つつじ |
| 冬木立分け入りて見る苔の石 | 木村 桃風 |
| 裏垣に咲き急ぎたる帰り花 | 益子 紫苑 |
| 第45回 句会 (2007年11月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 澄む秋や山塊一気に近づきて | 舞岡 柏葉 |
←最高得点
|
| 風の幅ススキの原で見つけたり | 野路 風露 |
|
| 名月に未来の道をたずねけり | 千草 雨音 |
|
| 野良着着てパントマイムの案山子かな | 松本 道宏 |
|
| 護摩の火の照らす伽藍やそぞろ寒 | ひらと つつじ |
|
| 傘寿喜寿肩寄せ合いて秋の旅 | 吉田 眉山 |
|
| 秋澄みて万年筆の文字青く | 飯塚 武岳 |
|
| 過ぎし日に蕉翁が寺山紅葉 | 奥隅 茅廣 |
|
| 籾焼きのけむりのひくく雨模様 | 菊地 智 |
|
| 真鶴の黒松越しに秋の富士 | 木村 桃風 |
|
| 風吹けば薄の群れの大拍手 | 長部 新平 |
|
| 弁当の隅に添えるや初紅葉 | 益子 紫苑 |
|
| 段畑に両腕伸ばす青蜜柑 | 芝崎 よし坊 |
|
| ■ 短 評 ■■■ 第45回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| 澄む秋や山塊一気に近づきて | 舞岡 柏葉 |
| 秋の大気が澄んでくると遠くの山々も鮮明に見えて、山塊が近づいてくる思いに駆られる。気宇壮大な秋が詠われている。 | |
| ★ 入選句 | |
| 弁当の隅に添えたる初紅葉 | 益子 紫苑 |
| 紅葉といえば楓だが、いちはやく色づくのは山桜といわれている。いずれの木であれ初めに紅葉する木は私達を喜ばせてくれる。その初紅葉をそっと弁当の隅に添えた主婦の心情が嬉しい。 | |
| かくれんぼ落ち葉の海に埋まれけり | 益子 紫苑 |
| 落葉を踏んでかくれんぼをしている子どもたちの様子が素直に詠まれている。「落ち葉の海」の捉え方は新鮮であるが、「埋まりけり」は「埋もれけり」としたい。 | |
| 名月に未来の道をたずねけり | 千草 雨音 |
| 「未来の道」とは自分の行く末であろうか、子どもたちの歩む道であろうか。一寸不思議な句であるが、ロマンあふれる句。 | |
| 夕富士や影伸ばしたるいぼむしり | ひらと つつじ |
| 秋も深まってくると夕日が作る影はどんどん伸びてくる。蟷螂の影もしかりである。夕富士をバックにした景色の設定が綺麗である。 | |
| ★ 並選句 | |
| おんちくの鯨汐吹きどっと避け | 菊地 智 |
| 護摩の火の照らす伽藍やそぞろ寒 | ひらと つつじ |
| 秋灯のぼつぼつ点る過疎の里 | 益子 紫苑 |
| 秋澄みて万年筆の文字青く | 飯塚 武岳 |
| 籾焼きのけむりのひくく雨模様 | 菊地 智 |
| 第44回 句会 (2007年10月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| あきあかねビル間となりし道祖神 | 芝崎 よし坊 |
|
| 山裾に向かう奔流薄かな | 舞岡 柏葉 |
|
| 大地より突如湧き出る彼岸花 | 野路 風露 |
|
| 直売所陽のぬくもりの柿並ぶ | 千草 雨音 |
|
| 組体操どっと崩れて天高し | 松本 道宏 |
←最高得点
|
| 蓮の実や仏はみんな美男美女 | ひらと つつじ |
|
| 鐘の音に白く燃ゆるや曼珠沙華 | 吉田 眉山 |
|
| 神棚へ水の缶詰震災忌 | 飯塚 武岳 |
|
| 挽曳の馬たくましく天高し | 奥隅 茅廣 |
|
| 羅漢像目線の先の彼岸花 | 菊地 智 |
|
| 初秋の樹間透きとおり神の山 | 木村 桃風 |
|
| 囲い網枯れ鬼灯の紅い実よ | 長部 新平 |
|
| 捨畑や葛の葉覆う古き井戸 | 益子 紫苑 |
|
| ■ 短 評 ■■■ 第44回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| 直販所陽のぬくもりの柿並ぶ | 千草 雨音 |
| 柿は日本の秋を代表するにふさわしい果実で、その種類は900に及ぶという。直販所に並ぶ柿の色艶まで見えてくる句である。並んでいる柿の色を「陽のぬくもり」と捉えたところが良い。作者の暖かい気持ちが伝わってくる。 | |
| ★ 入選句 | |
| 草の実を道連れにして子等駆ける | 千草 雨音 |
| 草の実を衣服に着けて駆け回っている子どもたちの姿が見えてくる。秋草の実は大半が地味で目立たないが、藪虱や牛膝のように人間や動物に付着する草の実も多い。「道ずれにして」がこの句のセールスポイントである。 | |
| 大地より突如湧き出る彼岸花 | 野路 風露 |
| 秋の彼岸の頃、畦や墓域などに群がって咲く彼岸花。気付いたときは既に真紅の花が輪状に咲いている。「突如湧き出る」に発見がある。 | |
| 綿の実のはじける笑いふんわりと | 野路 風露 |
| 綿の花が実を結ぶと50日か60日で完熟するが、その際3乃至5片に裂けて白色の綿毛を外に吹き出す。綿の実をじっくりと観察し、丁寧に表現されている。 | |
| 蓮の実や仏はみんな美男美女 | ひらと つつじ |
| 蓮の実と仏は付き過ぎの感があるが、「仏はみんな美男美女」には仏に対する作者の感慨が主観的に表現されている。 | |
| ★ 並選句 | |
| あきあかねビル間となりし道祖神 | 芝崎 よし坊 |
| 神棚へ水の缶詰震災忌 | 飯塚 武岳 |
| 名月や池を舞台に舞い降りて | 野路 露風 |
| 第43回 句会 (2007年9月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 盆送りざわめき残し子等帰る | 益子 紫苑 |
|
| 盆おどりナツメロばかりで音歪み | 芝崎 よし坊 |
|
| 滝水の岩間に架けし玉すだれ | 舞岡 柏葉 |
←最高得点
|
| 孫たちの置き土産かな麦藁帽 | 野路 風露 |
|
| 新涼や皿にはねるか焼肴 | 千草 雨音 |
|
| 鰯の群れ紙折るやうに向き変へる | 松本 道宏 |
|
| こほろぎや賽銭箱の闇深し | ひらと つつじ |
|
| 王将が王手に待った竹牀几 | 吉田 眉山 |
|
| 星月夜夢の鏤む万華鏡 | 飯塚 武岳 |
|
| 玉砂利の白さ目に染む晩夏かな | 奥隅 茅廣 |
|
| 土を掻く敗れし球児に大西日 | 菊地 智 |
|
| 炎熱に鏡もゆがむ昼の顔 | 木村 桃風 |
|
| 水玉のネクタイ締める初秋かな | 長部 新平 |
|
| ■ 短 評 ■■■ 第43回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| こほろぎや賽銭箱の闇深し | ひらと つつじ |
| 古今東西、蟋蟀の句ほど詠まれている句材はないかも知れない。「蟋蟀の深き地中を覗き込む」という有名な句や「底のない箱の暗闇ちちろ鳴く」など蟋蟀と闇を詠った句は沢山ある。しかし、この句の「賽銭箱の闇」にはアイロニーがある。 | |
| ★ 入選句 | |
| 孫たちの置き土産かな麦藁帽 | 野路 風露 |
| 孫たちが帰った後は嵐が過ぎ去ったようだと言われている。その孫たちが忘れて帰ってしまった麦藁帽子を「置き土産」と捉えた感覚が鋭い。 | |
| 滝水の岩間に架けし玉すだれ | 舞岡 柏葉 |
| 「玉簾」の比喩が素晴しい。滝の落下する水しぶきは正に岩間に架かっている玉簾のようだと言うのである。涼感の溢れた句であり、兼題が上手に使われている。 | |
| 盆送りざわめき残し子等帰る | 益子 紫苑 |
| この句も前々句に似ていて、盆送りに集まった子ども達が帰った後の余韻を楽しんで詠んでいる。「盆送り」が効いている。 | |
| 地芝居や善玉すぐに斬られたる | ひらと つつじ |
| 地芝居は秋の収穫のあと秋祭などで行われる素人芝居で、日本全国百ヵ所ほどで伝統を守り代々継承されている。善玉がすぐに斬られるところに地芝居の面白さがある。 | |
| ★ 並選句 | |
| 新涼や皿にはねるか焼肴 | 千草 雨音 |
| 玉砂利の白さ目にしむ晩夏かな | 奥隅 茅廣 |
| 草むらに玉を転がす虫の声 | 野路 風露 |
| 水玉のネクタイ締める初秋かな | 長部 新平 |
| 玉虫や千年超えて厨子守る | 益子 紫苑 |
| 第42回 句会 (2007年8月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 旅の宿窓開け見れば月涼し | 長部 新平 |
|
| 枝先に朱き数珠あり天道虫 | 益子 紫苑 |
|
| 明日開く朝顔数え投票す | 芝崎 よし坊 |
|
| 哲人となりて青田にさぎ孤影 | 舞岡 柏葉 |
|
| 天からの叱咤のごとし稲光 | 野路 風露 |
|
| 瞬かず線香花火の果つるまで | 千草 雨音 |
|
| 心音のかたちに開く遠花火 | 松本 道宏 |
|
| 桃色に爪透きとほる白夜かな | ひらと つつじ |
|
| 隣席の扇子の風を貰ひけり | 吉田 眉山 |
|
| 蝉は鳴く地上に七日の命賭け | 飯塚 武岳 |
|
| 地の果や知床の滝海に落つ | 奥隅 茅廣 |
|
| 手の平に隠れる程の遠花火 | 菊地 智 |
←最高得点
|
| 鷺草のゆれる姿や天を飛ぶ | 木村 桃風 |
|
| ■ 短 評 ■■■ 第42回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| 哲人となりて青田にさぎ弧影 | 舞岡 柏葉 |
| 青田の中に佇む鷺を哲人に見立て、その鷺の孤影を強調した句。青田の中の鷺が一幅の絵になっている。「さぎ孤影」という表現に一寸違和感があるが、独特な表現で鷺の生態を上手に詠んでいる。 | |
| ★ 入選句 | |
| 枝先に朱き数珠あり天道虫 | 益子 紫苑 |
| 枝先に数匹の天道虫が連なって止まっている状態を上手く表現されている。「朱き数珠あり」に発見がある。 | |
| 手の平に隠れる程の遠花火 | 菊地 智 |
| 近くで見る花火と遠くで見る花火の印象は全く異なる。「遠花火」をこのように把えたところに発見がある。表現としては「程」を「ほど」と平仮名にした方がよい。 | |
| 瞬かず線香花火の果つるまで | 千草 雨音 |
| 線香花火が終わるまで瞬かないで見ていたという集中力を詠んだところが面白い。 | |
| 隣席の扇子の風を貰ひけり | 吉田 眉山 |
| 一寸川柳ぽいが、隣の席からおくられてくる扇子の風に至福の時間を満喫しているという、誰でも経験する光景を素直に詠んでいる。楽しい句。 | |
| ★ 並選句 | |
| 天からの叱咤のごとし稲光 | 野路 風露 |
| 桃色に爪透きとほる白夜かな | ひらと つつじ |
| 地の果や知床の滝海に落つ | 奥隅 茅廣 |
| 胸に秘めし風の便りや落し文 | 益子 紫苑 |
| 水打って今日も終わりとひとりごと | 野路 風露 |
| 第41回 句会 (2007年7月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 雨去りて光る新樹の垣根かな | 木村 桃風 |
|
| 涼み床夜空の屋根を座し仰ぐ | 長部 新平 |
|
| 梅雨晴間貸し農園に弾む声 | 益子 紫苑 |
|
| 児と遊ぶ蚊帳吊草の匂いかな | 芝崎 よし坊 |
|
| 間を取りて鮎釣る人や竿ひかる | 舞岡 柏葉 |
←最高得点
|
| 万緑の間くぐりて陽の光 | 野路 風露 |
|
| 客間より談笑とだえ半夏生 | 千草 雨音 |
|
| 神輿来る録音テープの太鼓鳴り | 松本 道宏 |
|
| 風青し土手に円座の茶碗酒 | ひらと つつじ |
|
| 梅雨晴れや掘割川の水鏡 | 吉田 眉山 |
|
| 時空間超えて屋久杉夏闇に | 飯塚 武岳 |
|
| 豊かなる瀑布の響き夏木立 | 奥隅 茅廣 |
|
| 間を置いて返事の返る昼寝覚め | 菊地 智 |
|
|
|
| ■ 短 評 ■■■ 第41回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| 客間より談笑とだえ半夏生 | 千草 雨音 |
| 来客と談笑している声が突然途絶えた一瞬を捉えた句ですが、「半夏生」の配合がこの句にぴったりとあっていて素晴らしい句です。しかも兼題も上手に使っています。 | |
| ★ 入選句 | |
| 豊かなる瀑布の響き夏木立ち | 奥隅 茅廣 |
| 滝の落ちる響きが聞こえてくるような句で、一幅の絵を見ているようです。「夏木立ち」は「夏木立」で良いと思います。 | |
| 風青し土手に円座の茶碗酒 | ひらと つつじ |
| 「土手に円座の茶碗酒」とはどんな宴なのでしょうか。「風青し」が一寸唐突ですが、この句も兼題を上手く詠み込んでいます。 | |
| 夏嵐露座の大仏泰然と | 飯塚 武岳 |
| 鎌倉の旅吟でしょうか。「泰然と」の捉え方が平凡かも知れません。 | |
| 梅雨晴れ間貸し農園に弾む声 | 益子 紫苑 |
| 最近はやっている「貸し農園」での収穫の喜びが伝わってきます。「梅雨晴間」の季語が決まっています。 | |
| ★ 並選句 | |
| 間を取りて鮎釣る人や竿ひかる | 舞岡 柏葉 |
| 麦笛や頬ふくらませ子等競う | 益子 紫苑 |
| 葉を研ぎてあやめ一輪毅然たり | 舞岡 柏葉 |
| 開け放し風自在なり夏座敷 | 奥隅 茅廣 |
| 雨しずく葉裏に遊ぶ蝸牛 | 飯塚 武岳 |
| 第40回 句会 (2007年6月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 花蜜柑香り閉じ込め闇深し | 菊地 智 |
|
| 母の日に一輪の風とどきたり | 木村 桃風 |
|
| 飼い犬や夏めく庭を駆け回る | 長部 新平 |
|
| 実桜の踏まれぼかし絵めく紫紺 | 益子 紫苑 |
|
| 遠足の黄の帽子行くえごの花 | いまだ 未央 |
|
| にわか雨窓辺のパセリ蘇り | 芝崎 よし坊 |
|
| 夏雲の姿見となる玻璃の壁 | 舞岡 柏葉 |
|
| 車窓まで伸びて手を振る夏木立 | 野路 風露 |
|
| 十薬や土壁ひやりかくれんぼ | 千草 雨音 |
|
| 引越しのピアノ宙吊り夏燕 | 松本 道宏 |
|
| みどり児の握りしめたる初夏の風 | ひらと つつじ |
←最高得点
|
| 床の軸名筆なるや風五月 | 吉田 眉山 |
|
| 若葉風出窓で踊る野次郎兵衛 | 飯塚 武岳 |
|
| 床板や足の裏より皐月かな | 奥隅 茅廣 |
|
| ■ 短 評 ■■■ 第40回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| 若葉風出窓で踊る野次郎兵衛 | 飯塚 武岳 |
| 若葉風に踊っている野次郎兵衛の姿が見えてくるさわやかな句です。但し、説明的な「で」よりも「に」に推敲した方が更に野次郎兵衛の動きが出ると思います。 | |
| ★ 入選句 | |
| 夏雲の姿見となる玻璃の壁 | 舞岡 柏葉 |
| 近年、ガラス張りの豪華なビルが林立している都会。そのビルのガラスが壁となって逞しい夏雲を姿見のように写し出している。兼題の「壁」を上手に詠み込んだすばらしい句です。 | |
| 実桜の踏まれぼかし絵めく紫紺 | 益子 紫苑 |
| 赤く熟して落ちた実桜が子供たちによって踏み散らかされていたのでしょう。その様子を「ぼかし絵」と把えています。俳句は発見と意外性が生命です。「ぼかし絵」に作者の独特な発見があります。 | |
| 車窓まで伸びて手を振る夏木立 | 野路 風露 |
| 夏木立を擬人化した句です。樹木が茂って、通過する列車の車窓に手を振っているように感じた作者の感性に感心しました。 | |
| みどり児の握りしめたる初夏の風 | ひらと つつじ |
| すでに類句があるかも知れませんが、初夏の風を握り締めているみどり児の姿が的確に表現されています。 | |
| ★ 並選句 | |
| 天窓に雀わらわら夏来る | ひらと つつじ |
| 初夏の街臍出しルックが闊歩して | 飯塚 武岳 |
| 田水張る青らの深さを映しては | ひらと つつじ |
| 十薬や土壁ひやりかくれんぼ | 千草 雨音 |
| にわか雨窓辺のパセリ蘇り | 芝崎 よし坊 |
| 第3回 吟行句会 (2007年5月6日 舞岡公園) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 雨しとど竹皮を脱ぎ天を指す | 奥隅 茅廣 |
| 桐の花そぼ降る雨に鈴を振る | 千草 雨音 |
| 睡蓮を睨んで河童の相撲かな | 吉田 眉山 |
| 里山に紗を拡げたり青しぐれ | 舞岡 柏葉 |
| 相撲取るブロンズ河童若葉雨 | 松本 道宏 |
| 八幡の石の階段五月【さつき】暗 | いまだ 未央 |
| げんげ田やかくれた跡は大の字に | 益子 紫苑 |
| 野仏の笑みおだやかに今朝の夏 | ひらと つつじ |
| 雨空やタンポポ旅立ちひとやすみ | 野路 風露 |
| 桐の花一つ落ちたり雨しきり | 芝崎 よし坊 |
| どの木々も緑を競ふ五月かな | 長部 新 |
| 第39回 句会 (2007年5月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 京町屋風通り抜け春暖簾 | 奥隅 茅廣 |
←最高得点
|
| 松の芯曇天刺してつんと伸び | 菊地 智 |
|
| 淡き夢群れて飛び交う胡蝶蘭 | 木村 桃風 |
|
| 町屋にてふと遠い日のかざぐるま | 長部 新平 |
|
| 苗代や過疎の山河を写しをり | 益子 紫苑 |
|
| バス降りる本屋の町につばくらめ | いまだ 未央 |
|
| 町角の駄菓子屋静か大連休 | 芝崎 よし坊 |
|
| 晩春の日差しを濾過す竹の寺 | 舞岡 柏葉 |
|
| 新学期少し長めの袖光る | 野路 風露 |
|
| 恥じらいて赤味さしたる楠若葉 | 千草 雨音 |
|
| 駅前の巨大画面や月朧 | 松本 道宏 |
|
| 行く春の町から消えし理髪店 | ひらと つつじ |
|
| うららかやぷかり桟橋波しずか | 吉田 眉山 |
|
| 梅が香や飛鳥美人は石室に | 飯塚 武 |
|
| ■ 短 評 ■■■ 第39回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| 晩春の日差しを濾過す竹の寺 | 舞岡 柏葉 |
| 爛熟の春は日差しも強くなりどことなく気怠い。寺を囲む竹林はそんな晩春の日差しを濾過したように涼しくしてくれる。竹林が日差しを濾過するという捉らえ方が素晴らしい。 | |
| ★ 入選句 | |
| 京町屋風通り抜け春暖簾 | 奥隅 茅廣 |
| 京の町並みを通り抜ける春風と、その風によって一杯に膨らんだ暖簾を配した句で、駘蕩とした気分を感じさせる。春暖簾の「春」の季語の使い方に疑問が残るが、京都町屋の雰囲気は出ている。 | |
| 苗代や過疎の山河を写しをり | 益子 紫苑 |
| 水の張られた苗代一面に過疎の山河が写っている風景で、「過疎」がこの句のセールスポイント。写生句であるが作者の主張が伝わってくる。 | |
| 松の芯曇天刺してつんと伸び | 菊地 智 |
| 若々しい松の緑の新芽を素直に詠んだ句であるが、「晴天」でなく「曇天」と言ったところが面白い。 | |
| 行く春の町から消えし理髪店 | ひらと つつじ |
| 近年は大型量販店の進出によって個人商店が町から消えているが、理髪店は激安店の進出で同じ様に状態にある。世の中の変遷が上手に詠まれている。 | |
| ★ 並選句 | |
| 梅が香や飛鳥美人は石室に | 飯塚 武岳 |
| 新学期少し長めの袖光る | 野路 風露 |
| 恥らいて赤味さしたる楠若葉 | 千草 雨音 |
| 菜の花の揺れて青空深くせり | ひらと つつじ |
| 春の虹最期を看取る祈りかな | 益子 紫苑 |
| 第38回 句会 (2007年4月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 浜風に黒髪揺れて春匂ふ | 飯塚 武岳 |
|
| 寄せる波渚に光る春をみる | 奥隅 茅廣 |
|
| 流れ星落ちて春山串刺しに | 菊地 智 |
|
| 国分寺跡の礎石も花見かな | 木村 桃風 |
|
| 「サクラサク」教室内のミニパーティー | 長部 新平 |
|
| 麦踏や吾子も踏んばる母の背で | 益子 紫苑 |
|
| 雛納め壁に寂しさ残りけり | いまだ 未央 |
|
| 目を病みて香で知りしライラック | 芝崎 よし坊 |
|
| 夜桜の幹闇にとけ花浮かぶ | 舞岡 柏葉 |
|
| 花びらと一緒に帰る千鳥足 | 野路 風露 |
|
| 光浴びアニメのごとく花ほどけ | 千草 雨音 |
|
| 田の神を煙に捲きて畦を焼く | 松本 道宏 |
←最高得点
|
| 亀鳴くや線香太き孔子廟 | ひらと つつじ |
|
| 薄暗き矢倉に供ふ落ち椿 | 吉田 眉山 |
|
| ■ 短 評 ■■■ 第38回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| 麦踏や吾子も踏んばる母の背で | 益子 紫苑 |
| 作者の体験でしょうか。子供を背負っての麦踏は体力的にも大変と思われますが、母親と一緒になって背中の子も踏ん張って麦踏をしているという把握が独特で素晴らしいです。 | |
| ★ 入選句 | |
| 春筍を探す裏技足裏に | 益子 紫苑 |
| まだ地上に顔を出していない春筍を足裏で探している情景はよく目にしますが、そんな状況をうまく句に纏めてられています。 | |
| 雛納め壁に寂しさ残りけり | いまだ 未央 |
| 華やかに飾られていたお雛様も3月3日の雛祭りが過ぎますとすぐに箱に収められます。雛を収めた後の寂しさが詠われていますが、俳句の場合は「寂しさ」という直接的表現でなく「寂しさ」をもので表現できたら最高です。 | |
| 亀鳴くや線香太き孔子廟 | ひらと つつじ |
| 儒教の祖 孔子の遺品を祭った孔子廟は長崎の孔子廟が有名ですが、この句は湯島聖堂での作でしょうか。俳句はものに託して詠みますので「線香太き」に孔子を崇拝する気持ちが出ています。「亀鳴く」の季語も決まっています。 | |
| 花びらと一緒に帰る千鳥足 | 野路 風露 |
| 花見を終えた酔漢が、花びらと一緒に帰宅する姿をユーモアに詠んでいます。やや、川柳ぽい俳句ですが、目の付け所が良いです。 | |
| ★ 並選句 | |
| 夜桜の幹闇にとけ花浮かぶ | 舞岡 柏葉 |
| 浜風に黒髪揺れて春匂ふ | 飯塚 武岳 |
| 光浴びアニメのごとく花ほどけ | 千草 雨音 |
| 目を病みて香で知りしライラック | 芝崎 よし坊 |
| 彼岸西風帽子目深に浜を行く | いまだ 未央 |