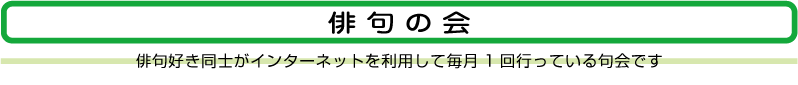| 2008年 |
| 2008年12月 | 第58回句会 | 作品 短評 |
| 2008年11月 | 第57回句会 | 作品 短評 |
| 2008年11月 | 第6回吟行句会 | 作品 |
| 2008年10月 | 第56回句会 | 作品 短評 |
| 2008年9月 | 第55回句会 | 作品 短評 |
| 2008年8月 | 第54回句会 | 作品 短評 |
| 2008年7月 | 第53回句会 | 作品 短評 |
| 2008年6月 | 第52回句会 | 作品 短評 |
| 2008年5月 | 第5回吟行句会 | 作品 |
| 2008年5月 | 第51回句会 | 作品 短評 |
| 2008年4月 | 第50回句会 | 作品 短評 |
| 2008年3月 | 第49回句会 | 作品 短評 |
| 2008年2月 | 第48回句会 | 作品 短評 |
| 2008年1月 | 第47回句会 | 作品 短評 |
| 2010年はこちら | 2009年はこちら | 2007年はこちら |