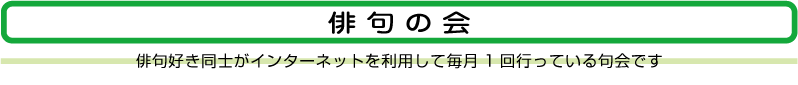| 2009年 |
| 2009年12月 | 第70回句会 | 作品 短評 |
| 2009年11月 | 第69回句会 | 作品 短評 |
| 2009年11月 | 第8回吟行句会 | 作品 |
| 2009年10月 | 第68回句会 | 作品 短評 |
| 2009年9月 | 第67回句会 | 作品 短評 |
| 2009年8月 | 第66回句会 | 作品 短評 |
| 2009年7月 | 第65回句会 | 作品 短評 |
| 2009年6月 | 第64回句会 | 作品 短評 |
| 2009年6月 | 第7回吟行句会 | 作品 |
| 2009年5月 | 第63回句会 | 作品 短評 |
| 2009年4月 | 第62回句会 | 作品 短評 |
| 2009年3月 | 第61回句会 | 作品 短評 |
| 2009年2月 | 第60回句会 | 作品 短評 |
| 2009年1月 | 第59回句会 | 作品 短評 |
| 2010年はこちら | 2008年はこちら | 2007年はこちら |
| 第70回 句会 (2009年12月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 猫の道小さく空けて障子貼る | ひらと つつじ |
←最高得点 |
| 消し炭をひょっとこ面して吹く子かな | 奥隅 茅廣 |
|
| 消炭や燃え残したる過去ありて | 千草 雨音 |
|
| 毒を盛る淑女恐ろし冬芝居 | 長部 新平 |
|
| 冬の夜の静寂【しじま】に消ゆる第九かな | 舞岡 柏葉 |
|
| 老い二人言葉少なに冬構 | 境木 権太 |
|
| 毒舌に怒り心頭狂ひ花 | 飯塚 武岳 |
|
| 切り株の木目隠して霜真白 | 菊地 智 |
|
| 釣り船の傾きてあり石蕗の花 | 野路 風露 |
|
| 名刹にカメラ混み合ふ冬紅葉 | 吉田 眉山 |
|
| 娘が嫁ぎ一人の庵に初時雨 | 益子 紫苑 |
|
| 夕闇に消えなんとする化粧富士 | 木村 桃風 |
|
| 木枯やアウシュヴィッツの引込線 | 松本 道宏 |
|
| 店先でポインセチアや出番待つ | 中里 くらき |
|
| ■ 短 評 ■■■ 第70回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| 白菜をざっくと切りし鍋奉行 | 長部 新平 |
| 忘年会の雰囲気の感じられる素直な句です。鍋料理を作る際、材料を入れる順序やたべごろなどをあれこれ指図する所謂鍋奉行の姿が見えてきます。白菜という物を通して詠まれているところが良いです。 | |
| ★ 入選句 | |
| 毒舌に怒り心頭狂ひ花 | 飯塚 武岳 |
| 兼題を上手に使った句です。面と向って辛辣な皮肉や批判を浴びせられると誰でも怒り心頭になりますが、そんな気持ちが上手に詠まれており季語が効いています。 | |
| 柿すだれひなたの猫の大あくび | 舞岡 柏葉 |
| 渋柿がすだれのように干されている晩秋の風物詩もさることながら、柿すだれの下で猫が大あくびをしている長閑で平和な風景が詠まれています。 | |
| 毒を盛る淑女恐ろし冬芝居 | 長部 新平 |
| 冬芝居」という季語はありませんが、演じられている芝居の内容から考えるとやはり「冬芝居」がぴったりかも知れません。 | |
| 猫の道小さく空けて障子貼る | ひらと つつじ |
| 猫は適当な時間間隔で室内を出たり入ったりしますが、そんな猫の気持ちを察して障子を貼っている作者のやさしい心意気まで感じられる句です。 | |
| 消し炭をひょっとこ面して吹く子かな | 奥隅 茅廣 |
| 句意は明瞭。この句のセールスポイントは「ひょっとこ面」で、子どもの生態をよく観察されていています。兼題もうまく使っています。 | |
| ★ 並選句 | |
| ブーメラン冬の青空きり抜いて | 長部 新平 |
| 消炭や燃え残したる過去ありて | 千草 雨音 |
| 晩学の部屋に炭火の暖かし | 奥隅 茅廣 |
| 冬の夜の静寂【しじま】の消ゆる第九かな | 舞岡 柏葉 |
| 老い二人言葉少なに冬構 | 境木 権太 |
| 第69回 句会 (2009年11月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 夜のはやき高野宿坊茶立虫 | ひらと つつじ |
←最高得点
|
| 秋の蜂監視カメラのごとをりぬ | 松本 道宏 |
|
| ひとすじの星の流れや空の杖 | 菊地 智 |
|
| 手に軽き宮古上布や空の澄む | 舞岡 柏葉 |
|
| 秋遍路御杖に添いて早寝かな | 益子 紫苑 |
|
| 無人駅ディーゼル去って柿日和 | 境木 権太 |
|
| 湧き水にそっとくちづけ尾瀬の秋 | 飯塚 武岳 |
|
| 灯に浮かぶべったら市の白き山 | 木村 桃風 |
|
| 血圧を測る二の腕夜寒かな | 奥隅 茅廣 |
|
| 願掛けの暇もなしや流れ星 | 菊地 智 |
|
| 異界への扉はここと枯れ尾花 | 野路 風露 |
|
| 枯山水何を思案の赤とんぼ | 千草 雨音 |
|
| 高階の廂にかかる十三夜 | 吉田 眉山 |
|
| 秋深し内科待ち合いBGM | 長部 新平 |
|
| ■ 短 評 ■■■ 第69回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| ひとすじの星の流れや空の杖 | 菊地 智 |
| 秋の夜空は澄んでいますので流星がはっきりと見えます。ひとすじの光を放ち流れ行く星に焦点を当てた句で、その流星を空の杖と捉えたところが斬新です。 | |
| ★ 入選句 | |
| 湧き水にそっとくちづけ尾瀬の秋 | 飯塚 武岳 |
| 秋の尾瀬は彩色も表情も豊かで大変静かです。湧き水を発見した作者は喉を潤すためその湧き水にそっとくちずけをしたのでしょう。気持ちの良い句です。 | |
| 秋遍路御杖に添いて早寝かな | 益子 紫苑 |
| 弘法大師の修行の遺跡である四国八十八ヶ所の札所は、秋にも巡拝されます。日暮れの早い秋は翌日の巡礼のために早寝するのでしょうが、遍路に使っている御杖の傍で寝ている巡礼者の姿を的確に表現されています。 | |
| 落鮎や尺の混じりて簗の上 | 舞岡 柏葉 |
| 成魚の鮎は秋産卵のために上流から中流の瀬を目指して川を下ります。落鮎です。簗の上の沢山の鮎の中に尺鮎が飛び跳ねたのでしょう。光景がよく見えます。 | |
| 大山の水育みて新豆腐 | 舞岡 柏葉 |
| 横浜では丹沢山系から流れる良質な水を使った大山豆腐が有名です。何処でも市販されているので新豆腐の季節感は薄いですが、良質な水が育ててくれます。 | |
| ★ 並選句 | |
| 高階の廂にかかる十三夜 | 吉田 眉山 |
| 火の山の煙ひとすじ崩れ簗 | ひらと つつじ |
| 灯に浮かぶべったら市の白き山 | 木村 桃風 |
| 血圧を測る二の腕夜寒かな | 奥隅 茅廣 |
| 夜のはやき高野宿坊茶立虫 | ひらと つつじ |
| 第8回 吟行句会 (2009年11月1日 鎌倉八幡宮 参加者:9名) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 狛犬の口の中まで秋日和 | 菊地 智 |
| 菊の香や鈴振り鳴らし巫女の舞ふ | 千草 雨音 |
| 宮鳩を追いかけ廻す千歳飴 | 松本 道宏 |
| 神楽女のゆるやかに舞ふ秋日和 | ひらと つつじ |
| 鯉跳ねて弁天島に秋の旗 | 吉田 眉山 |
| 小雀が一羽跳び躍ね秋深し | 大野 たかし |
| 木の葉散り視界全開段葛 | 東 酔水 |
| 秋日和巫女厳かに舞ひにけり | 中里 くらき |
| 秋晴れや笙篳篥【ひちりき】の音響き | 野路 風露 |
| 第68回 句会 (2009年10月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 秋の蝶夕日まとひて羽たたむ | ひらと つつじ |
←最高得点
|
| 暮れ行きてなお赤々と曼珠沙華 | 境木 権太 |
|
| 読み返す仰臥漫録子規忌かな | 奥隅 茅廣 |
|
| 秋鯖の模様めがけて切断す | 舞岡 柏葉 |
|
| 満天の星より降るや虫時雨 | 飯塚 武岳 |
|
| 日本語は窓多き文字天高し | 松本 道宏 |
|
| 旅立ちの化粧ほのかに銀杏の実 | 菊地 智 |
|
| 曼珠沙華街の移ろい知らず咲き | 長部 新平 |
|
| 研修の実り豊かに糸瓜かな | 吉田 眉山 |
|
| 野辺送り足元からむくづかずら | 益子 紫苑 |
|
| 新米を供え一日【ひとひ】の始まりぬ | 千草 雨音 |
|
| 野仏や羽を休める秋の蝶 | 野路 風露 |
|
| 再現の街道筋に走り蕎麦 | 木村 桃風 |
|
| 若竹や皮を残して天空へ | 中里 くらき |
|
| ■ 短 評 ■■■ 第68回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| くるぶしに波の寄せくる愁思かな | ひらと つつじ |
| 人影のめっきり少なくなった浜辺に跣で立っていると、一定の間隔で寄せくる波によって砂が削られ、寄せくる波がくるぶしを洗うようになります。自然の営みの中に、人間存在の哀れさ、人生のはかなさなど人間心理の陰翳が詠まれています。 | |
| ★ 入選句 | |
| 秋鯖の模様めがけて切断す | 舞岡 柏葉 |
| 秋鯖を捌くとき、秋鯖特有の鮮やかな模様めがけて包丁の刃を差込み、一刀のうちに鯖を切断したのでしょう。爽やかな包丁捌きが感じられます。 | |
| 暮れ行きてなお赤々と曼珠沙華 | 境木 権太 |
| 曼珠沙華は梵語で天上に咲く花を意味しますが、釣瓶落としの日が暮れても曼珠沙華の赤い花はなお赤く燃えています。素直な写生句です。 | |
| 秋の蝶夕日まといて羽たたむ | ひらと つつじ |
| この句も素直な句で説明は要りません。秋の蝶の生態をよく観察して作られた句で、中七の「夕日まといて」がセールスポイントです。 | |
| 風穴の奥を探りて秋のかぜ | 舞岡 柏葉 |
| 秋風には爽やかな風もあれば、野分けにも似た激しい風もあり、また天地粛殺たる風があります。風穴の奥を探るために来た秋風を詠んだ感性に感服しました。 | |
| ★ 並選句 | |
| 曼珠沙華街の移ろい知らず咲き | 長部 新平 |
| 尖端の細さいとしみ木賊刈る | 舞岡 柏葉 |
| 満天の星より降るや虫時雨 | 飯塚 武岳 |
| 再現の街道筋に走り蕎麦 | 木村 桃風 |
| 読み返す仰臥漫録子規忌かな | 奥隅 茅廣 |
| 第67回 句会 (2009年9月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 無花果や熟れた心を葉に隠し | 境木 権太 |
←最高得点
|
| 夏休み付箋のついた時刻表 | 飯塚 武岳 |
|
| 僧の頭のあをあをとある原爆忌 | ひらと つつじ |
|
| 夫の忌や膳に手植えの秋野菜 | 益子 紫苑 |
|
| 唐黍を焼いてる男寡黙なり | 菊地 智 |
|
| ぬか洗い紫紺の茄子や目にうまし | 千草 雨音 |
|
| 檸檬切る香りの粒子拡がりて | 舞岡 柏葉 |
|
| 星月夜酔うて候千鳥足 | 奥隅 茅廣 |
|
| 上げた手に一瞬止まる流れ星 | 野路 風露 |
|
| 風鈴の夜陰に鳴りて母来たる | 木村 桃風 |
|
| 満天の交響曲や星月夜 | 松本 道宏 |
|
| 月出たとベランダからの妻の声 | 吉田 眉山 |
|
| 蜩【ひぐらし】や鳴きつくしたか七日間 | 中里 くらき |
|
| 夕暮れや虫の音たのし散歩道 | 長部 新平 |
|
| ■ 短 評 ■■■ 第67回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| 夏休み付箋のついた時刻表 | 飯塚 武岳 |
| 時刻表を使って夏休みの旅行計画を創るのは楽しいものです。列車の出発・到着時刻を追って時刻表に貼って行った付箋に家族の楽しい語らいの姿が見えてきます。 | |
| ★ 入選句 | |
| 無花果や熟れた心を葉に隠し | 境木 権太 |
| 熟れた無花果の姿を面白く詠まれています。「熟れた心」は一寸オーバーな表現ですが、葉隠れに発見した熟れた無花果を詠んだ作者の気持ちは伝わってきます。 | |
| 僧の頭のあをあをとある原爆忌 | ひらと つつじ |
| この場合、あをあをと頭を剃った僧侶と原爆忌は直接的には関係がないと思いますが、「原爆忌」の配合で頭を剃りあげた僧侶と「原爆忌」が響きあっています。 | |
| 檸檬切る香りの粒子拡がりて | 舞岡 柏葉 |
| 檸檬を切ったときの飛び散るあのさわやかな香りを、「粒子」が拡がると把握した感覚は素晴しいと思いました。 | |
| 結納の口上ながし白木槿 | ひらと つつじ |
| 仲人さんが難しい結納の口上を長々と述べているだけの句ですが、季語の「白木槿」によって、結納の日には着ていない白無垢の花嫁の姿まで見える不思議な句です。 | |
| ★ 並選句 | |
| 闇灯す月下美人やシャンデリア | 千草 雨音 |
| 夫の忌や膳に手植えの秋野菜 | 益子 紫苑 |
| 福耳のみどりご抱くや敗戦忌 | 舞岡 柏葉 |
| 秋の空鉄棒ぐるっと一回転 | 野路 風露 |
| 唐黍を焼いてる男寡黙なり | 菊地 智 |
| 第66回 句会 (2009年8月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| のうぜん花こぼるるままの空き家かな | 益子 紫苑 |
←最高得点
|
| ベランダに端座瞑想あまがえる | 舞岡 柏葉 |
←最高得点
|
| 天の川千波よせくる九十九里 | 飯塚 武岳 |
|
| 千の目を釘付けにして西瓜割る | 松本 道宏 |
|
| 雨脚の機銃掃射や大夕立 | 吉田 眉山 |
|
| 川開き宴のあとの暗き波 | 木村 桃風 |
|
| 千羽鶴汗と笑顔の甲子園 | 千草 雨音 |
|
| 青山椒口ひげ生やし子の帰る | ひらと つつじ |
|
| 雪渓を仰ぎて心すっと晴れ | 野路 風露 |
|
| 落下する千条の滝行者打つ | 奥隅 茅廣 |
|
| 穂麦絵に喉を潤す缶ビール | 中里 くらき |
|
| 古里の空一杯の花火かな | 境木 権太 |
|
| 初蝉の声を打ち消す回収車 | 菊池 智 |
|
| 可憐なり老舗の粗品水中花 | 長部 新平 |
|
| ■ 短 評 ■■■ 第66回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| ベランダに端座瞑想あまがえる | 舞岡 柏葉 |
| 句意は明瞭。「端座」は作者の造語だと思いますが、ベランダの端に坐って瞑想している雨蛙に焦点を当てた句で、作者の驚きがあります。 | |
| ★ 入選句 | |
| 千羽鶴汗と笑顔の甲子園 | 千草 雨音 |
| 8日に開幕した全国高校野球選手権大会の熱戦も今年は異常気候の関係で2日間水をさされましたが、「千羽鶴」に勝利への祈り「汗と笑顔」に選手の姿が見えます。 | |
| 雨脚の機銃掃射や大夕立 | 吉田 眉山 |
| 夏の風物詩である夕立にあった作者の気持ちが上手に詠まれています。夕立の雨脚を「機銃掃射」と把握された感性の素晴らしさに感心しました。 | |
| 遠泳や千メートルの息づかい | 吉田 眉山 |
| 千メートルを泳ぎきった泳者の息づかいが聞こえてくるような句です。 | |
| 青山椒口ひげ生やし子の帰る | ひらと つつじ |
| 山椒は春に花を咲かせて秋に実が熟しますが、夏の、粒が小さくて青いものが「青山椒」です。未熟でも香りが高く、辛味もあります。季語の使い方が上手です。 | |
| ★ 並選句 | |
| 天の川千波よせくる九十九里 | 飯塚 武岳 |
| のうぜん花こぼるるままの空き家かな | 益子 紫苑 |
| 蝸牛アンテナたてて危険予知 | 飯塚 武岳 |
| 猫の目の密林めきて日の盛り | ひらと つつじ |
| 川開き宴のあとの暗き波 | 木村 桃風 |
| 第65回 句会 (2009年7月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| あめんぼうパンタグラフの脚走る | 松本 道宏 |
←最高得点
|
| ワイシャツの風に泳ぎて梅雨晴れ間 | 舞岡 柏葉 |
|
| 魚跳ねて刹那川鵜の嘴の中 | 千草 雨音 |
|
| わたすげの草原わたる風になり | 野路 風露 |
|
| 夕焼けを包んで闇の棚田かな | 菊池 智 |
|
| 年老いて農事の遅れ走り梅雨 | 益子 紫苑 |
|
| 青空に光る機影やかき氷 | ひらと つつじ |
|
| 藪を跳ぶ老鶯や名調子 | 中里 くらき |
|
| 階【きざはし】に滴る雫木下闇 | 吉田 眉山 |
|
| 海開き古式泳法扇舞う | 奥隅 茅廣 |
|
| 咲き乱れあぜ道ふさぐ立葵 | 境木 権太 |
|
| 歩むごとイヤリング揺れ百合匂ふ | 飯塚 武岳 |
|
| 夏至の日の明け六つに啼く鴉かな | 木村 桃風 |
|
| 太宰忌や生誕百年記事おどる | 長部 新平 |
|
| ■ 短 評 ■■■ 第65回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| 敷石を斑【まだら】に濡らす青時雨 | 舞岡 柏葉 |
| 「青時雨」は青葉の頃の時雨のことで、夏の青葉に降り注ぎ、ぱらぱらと落ちてくる雫を時雨にたとえたものです。難しい季語を使った写生句ですが、「敷石を斑に濡らす」に「青時雨」の特徴が的確に表現されています。 | |
| ★ 入選句 | |
| 魚跳ねて刹那川鵜の嘴の中 | 千草 雨音 |
| 川鵜が魚を捕らえる瞬間を上手に表現されています。普通、川鵜は潜水して魚を捕り、喉に一時蓄える習性がありますが、跳ねた魚を一瞬にして嘴の中に捕らえたという見事な技に感動して作句されたのでしょう。面白い句です。 | |
| ワイシャツの風に泳ぎて梅雨晴れ間 | 舞岡 柏葉 |
| 梅雨の晴れ間に干されたワイシャツの様子が気持ちよく詠まれています。 | |
| わたすげの草原わたる風になり | 野路 風露 |
| 綿菅は茎の先に長楕円形の花穂をつけ、花のあとは果実の下に白毛が長く伸びて絹糸のような綿毛に覆われます。綿菅の草原を渡る風の様子が詠まれています。 | |
| 海開き古式泳法扇舞う | 奥隅 茅廣 |
| 安全祈願するオープン・セレモニーの様子が詠まれています。古式泳法は日本古来の泳ぎ方で、甲冑を着用しての着衣泳法や立ち泳ぎでの火縄銃の射撃など、武術としての水中戦闘技術の泳法です。焦点を「扇舞う」に当てた所が良かった句です。 | |
| ★ 並選句 | |
| 年老いて農事の遅れ走り梅雨 | 益子 紫苑 |
| 階【きざはし】に滴る雫木下闇 | 吉田 眉山 |
| 泳ぎ子の背なに弾ける日差しかな | ひらと つつじ |
| 浴衣着てケータイ打つや3拍子 | 益子 紫苑 |
| 青空に光る機影やかき氷 | ひらと つつじ |
| 第64回 句会 (2009年6月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 理髪師の鋏かろやか風薫る | 飯塚 武岳 |
←最高得点
|
| ネクタイの固き結びめ五月病 | ひらと つつじ |
|
| 夕明かり使ひ切るまで田植かな | 松本 道宏 |
|
| 夏座敷良寛の書の余白かな | 千草 雨音 |
|
| 暮れなずむ植田に鷺の白さ増す | 境木 権太 |
|
| 夏めくやネールアートの青光る | 益子 紫苑 |
|
| 雲間よりのぞく青空夏燕 | 野路 風露 |
|
| 独り居に一点の青花菖蒲 | 舞岡 柏葉 |
|
| 木漏れ日に揺れる吊り橋風薫る | 木村 桃風 |
|
| 赤シャツの乙女の騎手や若葉風 | 吉田 眉山 |
|
| 菖蒲湯に幼と老との響声 | 菊地 智 |
|
| つつがなく菖蒲湯に入る至福かな | 奥隅 茅廣 |
|
| 食卓の筍飯や光りたる | 長部 新平 |
|
| ■ 短 評 ■■■ 第64回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| 暮れなずむ植田に鷺の白さ増す | 境木 権太 |
| 私が住む舞岡公園でも毎年田植えが行われていますが、植えられたばかりのさみどりの早苗田に鷺が何時までも佇む姿が印象的です。夕暮れが迫ると鷺の白さが一 層目立ってきます。一服の日本画を見ているようで、写生眼の効いた句です。 | |
| ★ 入選句 | |
| 地を這ひて登山電車の一直線 | 舞岡 柏葉 |
| 山を登っていく登山電車の喘ぐ姿が的確に詠まれています。「地を這ひて」と「一直線」の表現が響きあっています。 | |
| 雲間よりのぞく青空夏燕 | 野路 風露 |
| 梅雨時、雲間より青空が見えますとほっとしますが、そこを夏燕が豪快によぎって行ったという、心地よさの感じられる句です。 | |
| 木漏れ日に揺れる吊り橋風薫る | 木村 桃風 |
| 薫風に揺れる吊り橋でなく「木漏れ日に揺れる吊り橋」にこの句のセールスポイントがあります。揺れる吊り橋を巧みに詠んでいます。季語も効いています。 | |
| 理髪師の鋏かろやか風薫る | 飯塚 武岳 |
| 理髪師が使う鋏の軽やかな音は心地よく、眠りを誘う音です。窓の隙間から入る薫風がさらにその心地よさを誘っている句です。 | |
| ★ 並選句 | |
| 夏座敷良寛の書の余白かな | 千草 雨音 |
| 赤シャツの乙女の騎手や若葉風 | 吉田 眉山 |
| 一周忌手向けし花に初夏の風 | 木村 桃風 |
| 子供の日ぽつんと壁に野球帽 | 飯塚 武岳 |
| ネクタイの固き結びめ五月病 | ひらと つつじ |
| 第7回 吟行句会 (2009年5月31日 馬の博物館・根岸森林公園 参加者:10名) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 青蔦や貴顕紳士が夢の跡 | 木村 桃風 |
| 剥製の馬嘶【いなな】けり五月尽 | 松本 道宏 |
| 蔦からむ物見の塔や夏の雲 | 奥隅 茅廣 |
| 駒の目に映りて黒き深緑 | 菊地 智 |
| 草を食むポニーの肩に夏の蝶 | 野路 風露 |
| 野の起伏なぞる五月の風のみち | 舞岡 柏葉 |
| 万緑や馬のいななき鳥のこえ | 飯塚 武岳 |
| 蔦覆ふ廃墟を眺め夏近し | 吉田 眉山 |
| 薫風へ乗馬興じる乙女かな | 中里 くらき |
| 万緑や乗馬クラブの賑やかに | 東 酔水 |
| 第63回 句会 (2009年5月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 大山を斜めに切りて初つばめ | 舞岡 柏葉 |
←最高得点
|
| 大藤の風おさまりて揃い踏み | 中里 くらき |
|
| 花筏仄かに揺らぎ色模様 | 飯塚 武岳 |
|
| 亀の背に亀のっている仏生会 | ひらと つつじ |
|
| 綾取りの川から橋へ風薫る | 松本 道宏 |
|
| 朱印帳ページ狂わす春疾風 | 益子 紫苑 |
|
| 夏近しナイトゲームのホームラン | 吉田 眉山 |
|
| 山並みを包みて白き春霞 | 木村 桃風 |
|
| 新緑や花嫁乗せし人力車 | 野路 風露 |
|
| 天文台出でて緑の星ありき | 宇野 まりえ |
|
| 祝き事や君の亡きこと沁むる春 | 長部 新平 |
|
| ビル街の小さな花屋スイートピー | 千草 雨音 |
|
| 蓬摘む北は吹雪のニュースあり | 菊地 智 |
|
| 雨上がり眩しき朝や山笑う | 境木 権太 |
|
| ■ 短 評 ■■■ 第63回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| 大藤の風おさまりて揃い踏み | 中里 くらき |
| 古木の藤の花穂は1メートルを超えるものがあります。大きく揺れていた藤の花も風が止んだとき、力士の化粧回しのように美しい絵模様に見えたのでしょう。 暗喩で詠まれている「揃い踏み」が素晴らしいです。「の」は小さな切字です。 |
|
| ★ 入選句 | |
| 緑児の母追ふ瞳風光る | 飯塚 武岳 |
| 日常的によく見掛ける情景です。類句を恐れますが、初心者の上達段階に於ける通過点の句です。 | |
| 亀の背に亀のっている仏生会 | ひらと つつじ |
| 大亀の上に小亀や大亀の乗っている光景はよく見掛けます。亀と仏生会は直説的には関係ありませんが、右手で天、左手で地を指して「天上天下唯我独尊」と言われた釈迦の誕生を祝う「仏生会」の季語と響きあっています。 | |
| 大山を斜めに切りて初つばめ | 舞岡 柏葉 |
| 遠景の大山と近景の初つばめをバランスよく対照的に詠んだ句ですが、遠近法の表現が見事であり、大きな景を巧みに詠んでいます。 | |
| 朱印帳ページ狂わす春疾風 | 益子 紫苑 |
| 春は巡礼の季節。朱印帳を手に、例えば四国八十八ヶ所で順次朱印を頂く際、春の疾風でページが捲られ、押印の手元が狂ってしまったという句です。面白いポイントを句に纏められています。 | |
| ★ 並選句 | |
| チューリップ妖精たちの笑い声 | 野路 風露 |
| つつじ燃ゆ根津の社の千社札 | 木村 桃風 |
| 花筏仄かに揺らぎ色模様 | 飯塚 武岳 |
| 山並みを包みて白き春霞 | 木村 桃風 |
| 新緑や花嫁乗せし人力車 | 野路 風露 |
| 第62回 句会 (2009年4月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| おぼろ夜の空に分け入る観覧車 | ひらと つつじ |
←最高得点
|
| 道幅を一尺残しひじき干す | 菊地 智 |
|
| 半身を闇に隠して修二会の僧 | 舞岡 柏葉 |
|
| 浜風に父の好みし干鰈 | 千草 雨音 |
|
| 巣立つ日や父に目礼駅を発つ | 益子 紫苑 |
|
| お出かけにどの沓はこう春うらら | 飯塚 武岳 |
|
| 球春の日の丸まぶし彼岸かな | 木村 桃風 |
|
| 墨塗られ魚拓にされし桜鯛 | 松本 道宏 |
|
| 右左走る千鳥や浜の春 | 境木 権太 |
|
| 幾度の学位記受けて花の宴 | 吉田 眉山 |
|
| 春色に染まりて歩く里の山 | 野路 風露 |
|
| 土筆摘み土手の窪みの基地遊び | 長部 新平 |
|
| 道の駅チューリップたち自己主張 | 宇野 まりえ |
|
| ■ 短 評 ■■■ 第62回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| おぼろ夜の空に分け入る観覧車 | ひらと つつじ |
| 朧夜の風情が観覧車を通して申し分なく詠まれています。今までにこれほど高得点の句はなく、13人中6人が特選、5人が入選句に選んでいます。 | |
| ★ 入選句 | |
| 駅名のひらがな書きや初燕 | 千草 雨音 |
| 駅名は通常漢字が多いのですが、たまたまひらがなの駅に接した作者は「おや」と思われたのでしょう。発見があり、「初燕」が生き生きと効いています。 | |
| 道幅を一尺残しひじき干す | 菊地 智 |
| 漁師町の道幅はそんなに広くありませんが、最盛期には人一人通れる幅を残して 道幅いっぱいにひじきを干していたのでしょう。「一尺残し」がこの句の見せ場です。 | |
| 浜風に父の好みし干鰈 | 千草 雨音 |
| 干鰈は通常鰈の腸を抜き、日に干したものでありますが、地域によっては、焼いたものを槌でたたき、骨と身を離して短時間日に干すデビラと呼ばれる干鰈もあります。浜風にひらめく干鰈を通して父の笑顔までが見えてくる句です。 | |
| 半身を闇に隠して修二会の僧 | 舞岡 柏葉 |
| 修二会は3月1日から14日間、奈良東大寺で国家安泰を祈願する行事で修二月会の略ですが、二月堂の行の僧侶の姿が大変上手に詠まれています | |
| ★ 並選句 | |
| 雨去りてつつじ明かりの無人駅 | ひらと つつじ |
| 土筆摘み土手の窪みの基地遊び | 長部 新平 |
| お出かけにどの沓はこう春うらら | 飯塚 武岳 |
| 長閑さや途中下車せし無人駅 | 益子 紫苑 |
| 両の手で打ち香り立つ芽山椒 | 千草 雨音 |
| 第61回 句会 (2009年3月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 春筍【しゅんじゅん】の盛り上がりたる坂の径 | 吉田 眉山 |
←最高得点
|
| 灯明に仏像笑みて春の闇 | 舞岡 柏葉 |
|
| 床屋より新しき顔木の芽風 | 松本 道宏 |
|
| ケント紙のまつすぐな線冴返る | ひらと つつじ |
|
| 春色のエプロンを買う立子の忌 | 宇野 まりえ |
|
| 芋坂の羽二重団子江戸の春 | 木村 桃風 |
|
| 山茱萸の花にぽっちり今朝の雨 | 千草 雨音 |
|
| 巽より日の出動くも春浅しく | 菊地 智 |
|
| 行き止まる坂に迷いし春散歩 | 益子 紫苑 |
|
| 雛あられはじける夢の音ありて | 野路 風露 |
|
| 雛が出て賑わい戻る商店街 | 境木 権太 |
|
| 洛東の坂のぼりきり花見とす | 長部 新平 |
|
| 春北風赤銅色の仁王像 | 飯塚 武岳 |
|
| ■ 短 評 ■■■ 第61回 |
俳句グループ代表 松本 道宏
|
| ★ 特選句 | |
| 今生の夕日とどめて涅槃像 | ひらと つつじ |
| 陰暦2月15日はお釈迦様の入寂の日ですが、入寂の日の涅槃像が今生の夕日を全身にとどめているという見方に感動しました。 | |
| ★ 入選句 | |
| 春筍の盛り上がりたる坂の径 | 吉田 眉山 |
| 坂の小径に顔を出した春筍の勢いを詠んで句で、何でもない風景を素直に詠んでいます。筍は夏の季語ですが、春筍に新鮮味があり、「坂の径」が効いています。 | |
| 灯明に仏像笑みて春の闇 | 舞岡 柏葉 |
| 朧に潤んだような闇の中にあげた灯明。その灯明が仏像を照らし、映し出された仏像が微笑みを湛えているという荘厳な句で、仏像の微笑みが見えてくるようです。 | |
| ケント紙のまっすぐな線冴え返る | ひらと つつじ |
| 大変感覚的な句です。ケント紙の一本のまっすぐな線を境に冬と春の季節が鬩ぎ合っていると感じ取った句で、この感性は素晴らしいです。 | |
| 芋坂の羽二重団子江戸の春 | 木村 桃風 |
| 江戸文化歴史検定に合格している作者ならではの句。「芋坂」、「羽二重団子」についての詳細は省略しますが、江戸の春を詠んだ句として感心しました。 | |
| ★ 並選句 | |
| 山茱萸の花にぽっちり今朝の雨 | 千草 雨音 |
| 春北風赤銅色の仁王像 | 飯塚 武岳 |
| 淡雪や合格通知ありそうな | 宇野 まりえ |