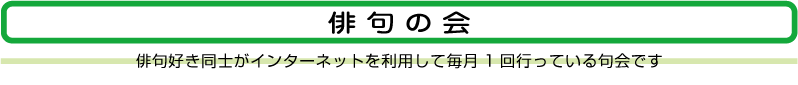| 2010年 |
| 2010年12月 | 第81回句会 | 作品 弘明寺抄(9) |
| 2010年11月 | 第80回句会 | 作品 弘明寺抄(8) |
| 2010年11月 | 第10回吟行句会 | 作品 |
| 2010年10月 | 第79回句会 | 作品 弘明寺抄(7) |
| 2010年9月 | 第78回句会 | 作品 弘明寺抄(6) |
| 2010年8月 | 第77回句会 | 作品 弘明寺抄(5) |
| 2010年7月 | 第76回句会 | 作品 弘明寺抄(4) |
| 2010年6月 | 第75回句会 | 作品 弘明寺抄(3) |
| 2010年5月 | 第9回吟行句会 | 作品 |
| 2010年5月 | 第74回句会 | 作品 弘明寺抄(2) |
| 2010年4月 | 第73回句会 | 作品 弘明寺抄(1) |
| 2010年3月 | 第72回句会 | 作品 |
| 2010年1月 | 第71回句会 | 作品 短評 |
| 2009年分はこちら | 2008年分はこちら | 2007年分はこちら |
| 第81回 句会 (2010年12月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 塩鮭やもっとも怒る貌を買ふ | 松本道宏 | ←最高得点 |
| 雪舟の篆刻の朱や冬ざるる | 舞岡柏葉 | |
| 冬晴れや何事もなき日の終わる | 長部新平 | |
| 旧邸や障子五厘の飾り継ぎ | 千草雨音 | |
| そぞろ寒衣服に迷う旅支度 | 木村桃風 | |
| 秋深し時間を落とす砂時計 | 飯塚武岳 | |
| 鵯の声あかつきの空を切る | 村木風花 | |
| 三塔の際立つ師走港町 | 吉田眉山 | |
| 晩菊の括られ残る八重葎 | 菊池智 | |
| 人造湖あをく沈みて山眠る | ひらとつつじ | |
| 朝日浴び満天星もみじこんもりと | 中里くらき | |
| 黄落や返信あてなきメール打つ | 野路風露 | |
| 落ち葉散る夜の歩道に犬遊ぶ | 猪股蕪焦 | |
| 噎せ換える硫黄噴き上げ冬の暖 | 東酔水 | |
| 迷い来て窓辺に憩う冬の蝶 | 奥隅茅廣 | |
| 入院の友の見舞いや初時雨 | 境木権太 |
| ■ 弘明寺抄(9)■■■ |
平成22年12月
松本 道宏 |
|
今月は『現代俳句のエロス』について考えてみました。一般的にエロスを俳句で表現することはタブーとされています。しかし、俳句は言葉と言葉の響きあいであり、エロスと相反するものではありません。 |
| 駆けそうな狛犬のあり敷紅葉 | 千草雨音 |
|
地面に散り敷いた紅葉は樹上の紅葉とはまた違った趣があります。神社の社頭に据え置かれている一対の狛犬が敷紅葉の上を今にも駆け出しそうだと感じ取った作者の感性に拍手を贈りたいと思います。 |
|
| 迷い来て窓辺に憩う冬の蝶 | 奥隅茅廣 |
冬の暖かい日に窓辺に迷い込んできた冬の蝶を素直に詠んでいます。俳句を作る人でないとこの感慨は詠めません。「迷い来て」に冬の蝶に対する作者の暖かい気持ちが表現されています。 | |
| 人造湖あをく沈みて山眠る | ひらとつつじ |
「山眠る」は『林泉高致』の「冬山の惨淡として眼るが如し」から出ている言葉で冬山を擬人化した俳味のある季語です。人造湖は周りの山々に囲まれて空を写し沈んだように静かです。中七の「あをく沈み」は写生を超えています。 |
|
| 朝日浴び満天星もみじこんもりと | 中里くらき |
素直な写生句。紅葉の美しい満天星が朝日を浴びて更にこんもりと美しく映えているさまを詠んだ句で、「朝日浴び」がこの句のセ−ルスポイントです。 | |
| 雪舟の篆刻の朱や冬ざるる | 舞岡柏葉 |
|
雪舟の水墨画の掛軸に篆刻の落款が鮮やかに押されていたのでしょうか。蕭条たる冬ざれの中に落款の朱が目に見えるようで、季語の使い方が上手です。 |
|
| 第80回 句会 (2010年11月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 全天に無音のひびき鰯雲 | 松本道宏 | ←最高得点 |
| 寒暖の狭間に迷う秋の蝶 | 飯塚武岳 | |
| 一陣の風戯【たはむ】るる花野かな | 村木風花 | |
| 赤とんぼ小石抱きて動かざり | 千草雨音 | |
| 秋天やころがしてゆく旅かばん | ひらとつつじ | |
| 草の実を体いっぱい子犬かな | 野路風露 | |
| 島人の言の葉重し秋出水 | 菊池智 | |
| 透き通るルビー貯め込む石榴かな | 中里くらき | |
| 幕引きの如く過ぎ去る時雨かな | 奥隅茅廣 | |
| ひろびろと机上かたづけ夜学かな | 長部新平 | |
| 里山に我が者顔に猪の道 | 境木権太 | |
| 狭き庭を掃き清めたり白秋忌 | 舞岡柏葉 | |
| 木々の間の空の色さえ秋の末 | 木村桃風 | |
| 茸飯婿と久しく差し向い | 吉田眉山 | |
| 枯葉から色を濃くして冬すみれ | 東酔水 |
| ■ 弘明寺抄(8)■■■ |
平成22年11月
松本 道宏 |
|
先月に引き続き、今回は「奇妙な季語」について考えてみました。
|
| 草の実を体いっぱい子犬かな | 野路風露 |
|
草の実は大半が地味で目立たないのですが、人間や動物に付着して種を撒き散らすものが多くあります。草の実の側を通った子犬が体中に草の実をつけて来た様子はなんともユーモラスであり、大変素直な句です。 |
|
| 雁の絵文字のごとく飛び行けり | 村木風花 |
|
雁が絵文字のように渡っていくという見方は一つの見方です。雁の飛び方には特徴があり、鍵状か横一線に隊列を組んで飛行します。雁の飛んで行く姿を絵文字のようだ感じたところが新鮮と思いました。 |
|
| 透き通るルビー貯め込む柘榴かな | 中里くらき |
|
裂けた柘榴の果肉がルビー色というのは常識的な見方ですが、「貯め込む」に柘榴に対する作者の思いが感じられます。西東三鬼に「露人ワシコフ叫びて柘榴打ち落とす」という有名な句があります。 |
|
| 赤とんぼ小石抱きて動かざる | 千草雨音 |
|
爽やかな秋のシンボルとしての赤蜻蛉は、多くは草原の空に群れをなす姿を詠まれていますが、小石を抱えて動かない赤蜻蛉を詠んだ句は珍しいと思います。赤蜻蛉の生態をよく観察された句です。 |
|
| 狭き庭を掃き清めたり白秋忌 | 舞岡柏葉 |
|
忌日は11月2日。北原白秋は浪漫精神の復興を提唱した歌人で、忌日には生地の柳川市で毎年慰霊祭が行なわれています。白秋忌を迎えるに当たって作者の気持ちが中七に表現されています。 |
|
| 第10回吟行会
(2010年11月5日 金沢文庫称名寺〜旧伊藤博文別邸〜野島公園 参加者:10名) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 行く秋や鳶の高さに登り来る | いまだ未央 |
| 小春日や浄土へ続く太鼓橋 | 飯塚武岳 |
| 茅の家に海の風くる石蕗の花 | ひらとつつじ |
| どんぐりを拾ふ指先赤らみて | 千草雨音 |
| 微動だにせぬ亀並ぶ秋うらら | 野路風露 |
| 秋空をくっきりくぎる山の端 | 坂神純生 |
| 秋うらら八景島に動くもの | 松本道宏 |
| 秋の空きらりと光る白き船 | 大野たかし |
| 阿字ケ池観艦式か鴨の群れ | 吉田眉山 |
| 八景より関東平野冬の景 | 東酔水 |
| 第79回 句会 (2010年10月) |
| ■ 作 品 ■■■ |