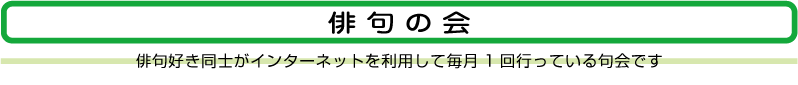
| 2014年 |
| 2014年12月 | 第129回句会 | 作品 弘明寺抄 (57) |
| 2014年11月 | 第17回吟行句会 | 作品 |
| 2014年11月 | 第128回句会 | 作品 弘明寺抄 (56) |
| 2014年10月 | 第127回句会 | 作品 弘明寺抄 (55) |
| 2014年9月 | 第126回句会 | 作品 弘明寺抄 (54) |
| 2014年8月 | 第125回句会 | 作品 弘明寺抄 (53) |
| 2014年7月 | 第124回句会 | 作品 弘明寺抄 (52) |
| 2014年6月 | 第123回句会 | 作品 弘明寺抄 (51) |
| 2014年5月 | 第16回吟行句会 | 作品 |
| 2014年5月 | 第122回句会 | 作品 弘明寺抄 (50) |
| 2014年4月 | 第121回句会 | 作品 弘明寺抄 (49) |
| 2014年3月 | 第120回句会 | 作品 弘明寺抄 (48) |
| 2014年2月 | 第119回句会 | 作品 弘明寺抄 (47) |
| 2014年1月 | 第118回句会 | 作品 弘明寺抄 (46) |
| 2013年分はこちら | 2012年分はこちら | 2011年分はこちら |
| 2010年分はこちら | 2009年分はこちら | 2008年分はこちら | 2007年分はこちら |
| 第129 句会 (2014年12月) 参加者:9名 |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 正座して物畳む妻冬ぬくし | 松本道宏 | ←最高得点 |
| 舌焦がす深川飯や初しぐれ | 吉木つつじ | |
| 野良猫のぬつと顔だす冬日向 | 飯塚武岳 | |
| 七五三ふくれつら子と笑む祖父母 | 千草雨音 | |
| 乳呑みて満願の笑み姫椿 | 志摩光月 |
|
| 留守番の柿熟れ残る峪の村 | 境木権太 |
|
| 大茶盛の一味和合や冬日向 | 舞岡柏葉 |
|
| 山里の新そばの札引かれ入る | 浅木純生 |
|
| 落ち葉掃き焼き芋した頃懐かしく | 柳風凡庸 | |
| ■ 弘明寺抄(57)■■ |
平成26年12月7日
松本 道宏 |
十二月の名句は「遠山に日の当りたる枯野かな 高浜虚子」です。
|
|
|||||
| 冬帽をちょっと気取って友と会ふ | 千草雨音 |
最初「冬帽」でなくともと思いましたが、俳句では帽子そのものに加え、帽子はその持ち主の人生、生活を想起させますので、納得しました。 |
|
| 野良猫のぬっと顔だす冬日向 | 飯塚武岳 |
日向ぼっこをしていると人恋しさで野良猫がぬっと現われることは誰でもが経験していますが、そんななんでもないことを上手に捉えいます。 | |
| 小宴会味噌かおり立つ茹大根 | 志摩光月 |
茹大根に味噌を乗せた香りが漂ってきます。「小宴会」が効いています。 「大宴会」では味噌の香りが立ちません。些細な事が句になっています。 |
|
| 七五三ふくれつら子と笑む祖父母 | 千草雨音 |
七五三の視点がユーモラスに詠まれています |
|
| 第17回吟行句会 (日産スタジアム〜新横浜ラーメン博物館)(2014年11月) 参加者:13名 |
| ■ 作 品 ■■■ |
| どんぐりや揃い帽子の子等遊ぶ | 千草雨音 | ←最高得点 |
| 麺つゆの油ぎらりと冬に入る | 吉木つつじ | |
| 風わたる丘に小さき冬桜 | 野路風露 | |
| ラーメン館昭和の歌に小春かな | 東酔水 | |
| 立冬や博物館に昭和あり | 舞岡柏葉 |
|
| 綿入やラーメンすする影ひとつ | 志摩光月 |
|
| 虫喰うて捨てておかれし木の実かな | 夏陽きらら |
|
| ラーメンを見比べ迷う食の秋 | 飯塚武岳 |
|
| 晴れわたる桜紅葉に鯉集ふ | 大野たかし | |
| 干し物が窓辺に残る秋の暮 | 境木権太 |
|
| 冬ざれにオールゴール刻むスタジアム | 森かつら |
|
| 冬に立ちカーンとカフー夢のあと | 柳風凡庸 | |
| 凍てる夜や夜鳴きそばの音響き泣く | 土屋百瀬 | |
 |
 |
|
  |  |
| 第128 句会 (2014年11月) 参加者:12名 |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 輪のきしみ小江戸の街に秋祭 | 境木権太 | ←最高得点 |
| 虫食いの穴も見事な枯葉かな | 川瀬峙埜 | |
| 父が子に伝ふる笛や豊の秋 | 吉木つつじ | |
| 苛立ちを持て余しをり秋潮 | 千草雨音 | |
| カメラより思いはみ出す秋景色 | 野路風露 |
|
| 雨上がり落ち葉染み付く朝の道 | 柳風凡庸 |
|
| 新蕎麦の飛んでくるなり椀の中 | 松本道宏 |
|
| 灯に映えてとろりたらりと初紅葉 | たま四不像 |
|
| 枝先に百舌鳥高鳴きや青き空 | 奥隅茅廣 | |
| 庭先に老女の笑みと石蕗の花 | 志摩光月 |
|
| アーケードにモカの香りや文化の日 | 舞岡柏葉 |
|
| 図書室に老若男女秋深し | 飯塚武岳 | |
| ■ 弘明寺抄(56)■■ |
平成26年11月7日
松本 道宏 |
十一月の名句は「霜柱俳句は切れ字ひびきけり 石田波郷」です。
|
|
|||||
| どんぐりに目鼻を描きやじろべい | 千草雨音 |
どんぐりでやじろべいを作ったのでしょうか。ただそれだけですと淋し いので、どんぐりに目鼻を書き入れたというユーモアのある句です。 |
|
| 爺婆も晴れ着姿や七五三 | 野路風露 |
孫の七五三を祝うために爺婆まで晴れ着姿となっている現代の風物詩が描かれています。 | |
| 苛立ちを持て余しをり秋潮 | 千草雨音 |
人間苛立ちに苛まれるときがありますが、夏の賑わいの去った秋の潮に淋しさを感じ、苛立ちを持て余している心理的状態が表現されています。 |
|
| アーケードにモカの香りや文化の日 | 舞岡柏葉 |
皆さんご存知のように、昭和2年に明治天皇の威徳を偲ぶ祝日として明治節が制定され、昭和23年に文化の日が制定されましたが、アーケードにまでモカの香りが流れてモカの香りを楽しんでいる作者が描かれています。 |
|
| 第127 句会 (2014年10月) 参加者:14名 |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 栗拾い先へ先へと目の走る | 野路風露 | ←最高得点 |
| 皮を剥く音も初物青蜜柑 | 川瀬峙埜 | |
| 鵙日和小瓶のジャムを荷に足して | 吉木つつじ | |
| 畏友病む色なき風に無事託す | 舞岡柏葉 | |
| 針穴に少しいびつなけふの月 | 夏陽きらら |
|
| 城攻めの兵の血汐か曼珠沙華 | 境木権太 |
|
| くつたくをさらりと流す秋の風 | たま四不像 |
|
| 鶺鴒や銀の水面をすくい飛ぶ | 福和来 |
|
| 大文字盃に汲みとる至福かな | 奥隅茅廣 | |
| 遠回りして木犀の続く道 | 千草雨音 |
|
| 蕎麦の花下野の野はほの白し | 浅木純生 |
|
| 異境界妖しく立てり曼珠沙華 | 飯塚武岳 | |
| 釣瓶落しテールランプの列つづく | 松本道宏 | |
| 手を合わせ祈る足下曼珠沙華 | 柳風凡庸 |
| ■ 弘明寺抄(55)■■ |
平成26年10月7日
松本 道宏 |
十月の名句は 「曼珠沙華どれも腹出し秩父の子 金子兜太」です。
|
|
|||||
| 日蓮の衣かけたる松に露 | たま四不像 |
日蓮は海が静まるようにと祈祷した時に掛けたという松、所謂 「袈裟掛けの松」 は現在はありませんが、故事にちなんだ句として頂きました。 |
|
| 針穴に少しいびつなけふの月 | 夏陽きらら |
今年は生憎の無月でしたが、場所によっては雲間から満月が見えたそうです。針穴から今日の月を見た「少しいびつ」に臨場感があります。 | |
| 何事を耳打ちするか秋の蚊よ | 野路風露 |
秋の蚊の羽音に悩まされることは屡あります。 蚊が何事かを耳打ちするかのように寄ってきた時の様子、「秋の蚊」の独特な声を詠んでいます。 |
|
| お袋の丸き背中や秋刀魚焼く | 境木権太 |
秋刀魚を焼いている母親を詠まれていますが、「丸き背中」に母親の特徴がでており、哀れを誘う句です。 |
|
| 第126回 句会 (2014年9月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 手鏡に空のかけらや終戦日 | 吉木つつじ | ←最高得点 |
| 納涼祭母は稲荷を三つ食べ | 浅木純生 | |
| 逢ひたくて窓辺によれば盆の月 | 千草雨音 | |
| 飛び込んで翡翠の色の波紋かな | 境木権太 | |
| ほんのりと一隅照らす曼珠沙華 | 志摩光月 |
|
| 蜩や同窓会の返信す | 野路風露 |
|
| 朝顔や深紫のブラックホール | 飯塚武岳 |
|
| プール券使わぬままに暦剥ぐ | 長部新平 |
|
| 名なし虫生きよと放つ八月尽 | 村田一女 |
|
| 新築の壁がまぶしと蝉落つる | 松本道宏 |
|
| 窓開けてきっぱりと知る今朝の秋 | 福和来 |
|
| 子供らと熱く語りし白鳥座 | たま四不像 | |
| ポトス伸び葉先のしずく煌めきて | 川瀬峙埜 | |
| 遠花火遅れて音の届きけり | 奥隅茅廣 | |
| ビーズ連ねミサンガを編む式部の実 | 舞岡柏葉 | |
| 手をつなぐ母と幼子同浴衣 | 柳風凡庸 |
| ■ 弘明寺抄(54)■■ |
平成26年9月7日
松本 道宏 |
九月の名句は「糸瓜咲いて痰のつまりし仏かな 正岡子規」です。
|
|
|||||
| 納涼祭母は稲荷を三つ食べ | 浅木純生 |
納涼祭の世話役をしている母であろうか。勇んで出て行く母が稲荷鮨を3個も食べていつたというユーモラスな句です。 |
|
| 手鏡に空のかけらや終戦日 | 吉木つつじ |
何かの都合で使っていた手鏡に炎天の空の青さを捕らえたのでしょう。一瞬に写った空のかけらにあの終戦の日の空を見たのでした。 | |
| ほんのりと一隅照す曼珠沙華 | 志摩光月 |
庭の片隅に曼珠沙華が咲いていたのを発見した作者は「曼珠沙華が一隅を照らしている」と感じたのでしょう。「ほんのりと」に発見があります。 |
|
| ビーズ連ねミサンガを編む式部の実 | 舞岡柏葉 |
ビーズを使ってミサンガを編むことと配合の紫式部の実とは何の関係もありませんが、この季語が実によくあっています。 |
|
| 第125回 句会 (2014年8月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 泳ぎ子の光まとひて水を出づ | 吉木つつじ | ←最高得点 |
| 頭突き蹴り張り手げんこつ昼寝の子 | 松本道宏 | |
| 白桃の赤子の肌や匂い立つ | 境木権太 | |
| 青柿や古稀近づくもまだ青し | 千草雨音 | |
| 抜け出して羽伸びのびと油蝉 | 奥隅茅廣 |
|
| 焼き茄子のつゆだくだくと飯を食う | 浅木純生 |
|
| 朝顔や咲いて萎んで無にかえり | 飯塚武岳 |
|
| ふるさとに「帰る」のメール大暑来ぬ | 長部新平 |
|
| 桶に沿ひて下りうなぎのうの字かな | 舞岡柏葉 |
|
| 朝響く歓声に知る夏休み | 福和来 |
|
| 紫蘇繁る畑の先に母の影 | 志摩光月 |
|
| ガブリでツーンこめかみ押さえるかき氷 | 柳風凡庸 |
| ■ 弘明寺抄(53)■■ |
平成26年8月7日
松本 道宏 |
八月の名句は「冷やされて牛の貫禄しづかなり 秋元不死男」です。
|
|
|||||
| 紫蘇繁る畑の先に母の影 | 志摩光月 |
紫蘇が大変繁っている畑の先に幻の母を見たのでしょうか。「母の影」 に作者の思いが感じられます。 |
|
| 白桃の赤子の肌や匂い立つ | 境木権太 |
赤子の肌が白桃の肌に似ているという類句は沢山ありますが、「匂い立つ」に新鮮さがあります。 | |
| 裸子はころころ笑ひ逃げ回る | 千草雨音 |
汗をかいたので肌着を変えるために裸にさせられた子供は、裸になったのが嬉しくて裸のまま逃げ回っています。裸子の生態が詠まれています。 |
|
| 海の日や波の調べは子守唄 | 千草雨音
|
海の日に特別な思いを持っている方の句でしょうか。波の調べが子守唄に感じた思いもさることながら 「海の日」の季語が大変良く効いています。 |
|
| 第124回 句会 (2014年7月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 朝顔の先陣競う蔓の先 | 飯塚武岳 | ←最高得点 |
| あめんぼの遊びつくせし水一枚 | 吉木つつじ | |
| 香焚けば煙とどめる梅雨湿り | 福和来 | |
| てらてらと水面脈打つ薄暑かな | 夏陽きらら | |
| 病む妻と十薬の花眺めおり | 境木権太 |
|
| 引く波の後ろ向きなり薄暑光 | 松本道宏 |
|
| おしめりや柿の花散る王禅寺 | 千草雨音 |
|
| 羽音聞き寝惚けて取り出す蚊取りかな | 柳風凡庸 |
|
| 紫陽花や心変わりが色に出て | 浅木純生 |
|
| 鮎を負う釣り師膝まで川の中 | 舞岡柏葉 |
|
| 山百合の白き姿や遠き君 | 野路風露 |
|
| 落下する滝に自然の節理かな | 奥隅茅廣 |
| ■ 弘明寺抄(52)■■ |
平成26年7月7日
松本 道宏 |
七月の名句は「七月の青嶺まじかく溶鉱炉 山口誓子」です。
|
|
|||||
| 朝顔の先陣競う蔓の先 | 飯塚武岳 |
常識的な句ではありますが、「先陣を競う」に作者の鑑賞眼があります。 |
|
| 笹の葉に短冊飾る親子かな | 野路風露 |
七夕の行事が素直に詠まれています。「親子かな」が効いています。 | |
| 紫陽花や心変わりが色に出て | 浅木純生 |
紫陽花の七色の変化を恋人の心の移り変わりに掛けて詠まれている句です。中々面白い心の変化が詠まれています。 |
|
| 空蝉のささやき合へる夜の底 | 吉木つつじ |
空蝉がささやき合うことはありませんが、「ささやき合う」と感じ取った「夜の底」が効いています。 |
|
| 第123回 句会 (2014年6月) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| カナヘビは筆箱の中九九を聞く | 松本道宏 | ←最高得点 |
| 麦秋やローカル線の一人旅 | 千草雨音 | |
| 幼児の目泳がせる苺狩り | 舞岡柏葉 | |
| もてなしの指美しき葛桜 | 浅木純生 | |
| 無重力ゆらりふわりと蛍かな | 奥隅茅廣 |
|
| 烏帽子岩卯波の中に浮き沈み | 飯塚武岳 |
|
| 夕されば月になりたき水母かな | 吉木つつじ |
|
| 散り急ぐバラの花びら手に包む | 境木権太 |
|
| 我が姿母の姿や半夏生 | 野路風露 |
|
| 葉柳や青々と揺れ人誘ふ | 長部新平 |
|
| 道くねり青葉の闇がさわさわと | 村田一女 |
|
| 色かさね若葉の輝き風を描く | 東酔水 |
| ■ 弘明寺抄(51)■■ |
平成26年6月7日
松本 道宏 |
六月の名句は 「じゃんけんで負けて蛍に生まれたの 池田澄子」 です。
|
|
|||||
| 我が姿母の姿や半夏生 | 野路風露 |
「自分の姿は母の姿に大変似ている」といふ格言みたいな言葉にぴったりな季語で意外と「半夏生」を配合として使用している句が多いです。 |
|
| 烏帽子岩卯波の中に浮き沈み | 飯塚武岳 |
卯波は走り梅雨のころ荒南風と呼ばれる風によって立つ風波のことですが、卯波だからこそ烏帽子岩の浮き沈みする変化が見られます。 | |
| 亀の子の歩みをまねる園児かな | 飯塚武岳 |
人間にしろ動物にしろ赤ちゃんは可愛いものです。あの子亀の歩き方を見て園児が真似るというユーモラスな風景が詠まれています。 |
|
| 散り急ぐバラの花びら手に包む | 境木権太 |
薔薇の花びらが散るときその花びらを手で包むようにして薔薇をたたえた句が詠まれています。 |
|
| 第16回 吟行句会 2014年5月22日(木) 横浜港 大さん橋、象の鼻 |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 木もれ日は初夏の色夢の色 | 夏陽きらら | ←最高得点 |
| 青空に汽笛の踊る聖五月 | 松本道宏 | |
| 百年の赤き倉庫や風薫る | 野路風露 | |
| 覇を競う横浜三塔雲の峰 | 境木権太 | |
| 木の道の足裏にやさし五月晴れ | 吉木つつじ |
|
| 風薫る明治を偲ぶ象の鼻 | 飯塚武岳 |
|
| 夏の日やステンドグラスの蒸気船 | 大野たかし |
|
| 翼立て鴎の乗りし春の波 | 土屋百瀬 |
|
| 風薫る大さん橋でコンサート | 東酔水 |
|
| 留守宅の守宮を想う大さん橋 | 森かつら |
|
|
||
 |  |
|
|