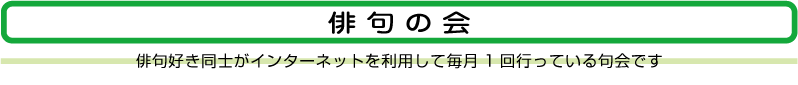
| 2016年 |
2016年12月 |
第153回句会 | 作品 特選句短評 |
2016年11月 |
第152回句会 | 作品 特選句短評 |
2016年10月 |
第151回句会 | 作品 特選句短評 |
2016年9月 |
第150回句会 | 作品 弘明寺抄 (78) |
2016年8月 |
第149回句会 | 作品 弘明寺抄 (77) |
2016年7月 |
第148回句会 | 作品 弘明寺抄 (76) |
2016年6月 |
第147回句会 | 作品 弘明寺抄 (75) |
2016年5月 |
第19回吟行句会 | 作品 |
| 2016年5月 | 第146回句会 | 作品 弘明寺抄 (74) |
| 2016年4月 | 第145回句会 | 作品 弘明寺抄 |
| 2016年3月 | 第144回句会 | 作品 弘明寺抄 (72) |
| 2016年2月 | 第143回句会 | 作品 弘明寺抄 (71) |
| 2016年1月 | 第142回句会 | 作品 弘明寺抄 (70) |
| 2015年分はこちら | |||
| 2014年分はこちら | 2013年分はこちら | 2012年分はこちら | 2011年分はこちら |
| 2010年分はこちら | 2009年分はこちら | 2008年分はこちら | 2007年分はこちら |
第153回句会 (2016年12月) 参加者:14名 |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 初雪や荒ぶる貌の阿夫利山 | 舞岡柏葉 | ←最高得点 |
| 母送る読経静かに石蕗の花 | 境木権太 | ←最高得点 |
| 焼き芋で話がはずむ足湯かな | 小正日向 | |
| 風に舞ひ光はなてる落葉かな | ただの凡庸 |
|
| 秋の山湖面鏡に化粧かな | 野路風露 |
|
| 胸騒ぐ庭の紅葉の雪化粧 | 志摩光月 |
|
| 山のふゆ古木(こぼく)の皺の浮き上がり | たま四不像 |
|
| 衣かつぎつるりほくほく舌鼓 | 翁山歩存 |
|
| 枯菊へ押し寄せてくる野の光 | 比良戸つつじ | |
| 秋深ししじまを破る犬一声 | 木村桃風 | |
| 寒暁の地震(なゐ)によろけるトイレかな | 川瀬峙埜 | |
| 初時雨レインコートの犬散歩 | 千草雨音 | |
| 初雪やねぐらへいそぐはぐれ鳥 | 飯塚武岳 | |
| 子らが打つ祭りばやしに聞き惚れる | 石敬 | |
|
| ■第153回インターネット句会特選句短評■■ |
|---|
| 胸騒ぐ庭の紅葉の雪化粧 | 志摩光月 |
|---|
| たま四不像)今回の自分的選句テーマは「類句や類想」のなさそうなもの。5・7・5は余りに短く人の考えることは結構似ています。さらに巧い!と人がうなるような技巧の句は難しいところです。なので類句や類想がだめという意味ではありません。そこで選句は似たような発想や同じような表現ではなく、素直に自分なりの心情をあらわして好感が持てる句を「類句や類想」でない句として選ばせていただきました。句が巧いとか下手とか以上に「自分が感じたという事実の重さが俳句の大黒柱」とある俳人も言ってます。この句は早い初雪となり紅葉と雪がいっしょになった驚きが表れ、自分も素直に実感と共感が持てました。 |
|---|
| 山城の守り固める霧ぶすま | 境木権太 |
|---|
| 翁山歩存)山城に霧がかかっている状態が上手く表現さてている。 |
|---|
| 初雪や荒ぶる貌の阿夫利山 | 舞岡柏葉 |
|---|
比良戸つつじ)普段は穏やかで端正な姿を見せている阿夫利山が初雪を被って荒ぶる姿になっている。毎年、なにがしかの驚きをもって迎えられる初雪が齎した荒ぶる山に納得。 |
|
|---|---|
| 初雪や子猫相手に酒を呑む | 野路風露 |
|---|
| 小正日向)酒を呑んでいる人と、子猫の表情が目に浮かんでほのぼのとします。 |
|---|
| 風に舞ひ光はなてる落葉かな | ただの凡庸 |
|---|
| 石敬)黄金色の枯葉も舞うカラッとした秋晴れが思い浮かびます。美しい句ですね。 志摩光月)散歩すると落ち葉に朝日が当たり、輝いている光景に出会います。 「光はなつ」の表現に感服しました。 |
|---|
| 母送る読経静かに石蕗の花 | 境木権太 |
|---|
木村桃風)母堂を送った悲しみの心情が黄色い石蕗の花に沁み込んで行きます。 野路風露)お母様に対する優しさが静かな中の読経と石蕗の花ににじみ出ているように思われました。 |
|---|
| 神鹿(しんろく)の濡るる瞳や小春空 | 舞岡柏葉 |
|---|
| 千草雨音)神鹿という言葉を初めて知りました(神の使いとして神社に飼われている鹿のこと)鹿の濡るる瞳に小春日のきれいな空が映っていたのでしょう。 厳かできれいな句だと思います。 |
|---|
| 秋の山湖面鏡に化粧かな | 野路風露 |
|---|
| 舞岡柏葉)山奥の静かな湖の情景が伝わりました。 |
|---|
| 故郷の我が家に一人木守柿 | 境木権太 |
|---|
| ただの凡庸)久し振りに故郷に帰ると、今は誰も住んでいない家を守るように一本の柿の木が赤い実をつけて迎えてくれた。作者の気持ちが良く出ている。 |
|---|
第152回句会 (2016年11月) 参加者:19名 |
| ■ 作 品 ■■■ |
| かのひとのかぼそきゆびや初紅葉 | 飯塚武岳 | ←最高得点 |
| 地芝居や父の口紅はみ出して | 境木権太 | |
| 逆上がり蹴って夕焼色の秋 | たま四不像 | |
| 色鳥の一筋の緋や富士樹海 | 舞岡柏葉 |
|
| 蟷螂の考えてゐる眼かな | 比良戸つつじ |
|
| 同窓の寄せ書きの詩や杜鵑草 | 千草雨音 |
|
| 夢うつつ古希の恋路や返り花 | 志摩光月 |
|
| 黒髪の湿り月夜の孤独かな | 夏陽きらら |
|
| どんぐりや初恋の人逝くを知る | 野路風露 | |
| 白鷺や忍び歩きの浅瀬かな | 木村桃風 | |
| 言の葉を紡ぎし歩む秋箱根 | 石敬 | |
| 稲架掛(はざかけ)や三浦の里ぞ米どころ | 翁山歩存 | |
| 人影に蝗くるりと葉隠れし | 奥隅茅廣 | |
| うそ寒や湯呑みの温み手で包む | 菊地智 | |
| 香りつれきのこ届いて祝い膳 | 小正日向 | |
| 鶸鳴くや梢揺らぎて朋を呼ぶ | 川瀬峙埜 | |
| 山の端や黄茜(あか)闇(くろ)に釣瓶落ち | ただの凡庸 | |
| 赤々と色づく山を紅葉狩り | 相模野之長山 | |
| 親類へ文書きおえる野分晴 | 森かつら | |
|
| ■第152回インターネット句会特選句短評■■ |
|---|
| 夢うつつ古希の恋路や返り花 | 志摩光月 |
|---|
| 翁山歩存)古希を過ぎたけど、こういう気分になってみたいものです。 |
|---|
| 逆上がり蹴って夕焼色の秋 | たま四不像 |
|---|
| 比良戸つつじ ) 逆上がりをして空をさかさまに見たものと思われる。そこには夕焼に 染まった秋の空があった。 「夕焼色の秋」の表現が秀逸。 |
|---|
| 蟷螂の考えてゐる眼かな | 比良戸つつじ |
|---|
夏陽きらら)蟷螂は怖そうな風貌ですが、小首をかしげてお澄ましするような一瞬もあります。 奥隅茅廣)蟷螂が獲物を狙うときや警戒する時に首を良く動かして様々な表情をしますがよく見ていますね。 |
|
|---|---|
| かのひとのかぼそきゆびや初紅葉 | 飯塚武岳 |
|---|
| 石敬)かの人とは誰なのでしょうか。まだ一歳にも満たないお孫さんでしょうか。 モミジの様な小さな御手てをパッと開いた赤児を愛おしく見つめる作者、そんな光景を思いました。 |
|---|
| 秋惜しむ霧笛のひびく港町 | 飯塚武岳 |
|---|
| 森かつら)港町、霧笛ひびくと秋惜しむが合っている。横浜はいい街です。 |
|---|
| 末っ子が勝気満々運動会 | 境木権太 |
|---|
野路風露)良いですね。目に浮かびます。笑がこみ上げてきました。 舞岡柏葉)次男、末っ子は上に対抗して、勝気でやんちゃですね。ほほえましい句です。 |
|---|
| 稲架掛(はざかけ)や三浦の里ぞ米どころ | 翁山歩存 |
|---|
| ただの凡庸)三浦が米どころとは思えないが、"里ぞ"と強調したところが気に入りました。 |
|---|
| 新蕎麦や石臼挽きの香り立つ | 千草雨音 |
|---|
| 小正日向)蕎麦の香りがしてくるような、それを食べている人の顔の表情までも浮かんできます。 |
|---|
| 黒髪の湿り月夜の孤独かな | 夏陽きらら |
|---|
| 木村桃風)一瞬、竹久夢二の絵を思い起こしました。 女性の孤独感が感じ取れました。 |
|---|
| 鶸鳴くや梢揺らぎて朋を呼ぶ | 川瀬峙埜 |
|---|
たま四不像)11月の自分的テーマは「擬人化」にしました。 |
|---|
| 山頭火忌ひねもす重き秋の雨 | たま四不像 |
|---|
| 川瀬峙埜)一日中 秋の雨を眺めて 山頭火を思いやれば自由の意味や自由の過酷さが身に沁みてくる心情に同感を憶えます。 |
|---|
| どんぐりや初恋の人逝くを知る | 野路風露 |
|---|
| 志摩光月)どんぐり、初恋、逝くの取り合わせが良い。深みのある情景が浮かぶ。 |
|---|
| 同窓の寄せ書きの詩や杜鵑草 | 千草雨音 |
|---|
| 境木権太)杜鵑草の花言葉は「秘密の恋」だそうです。同窓生の寄せ書きに杜鵑草の詩を書いて、恋心を伝えたかったのでしょうか。今月は恋の歌が多かったですが、その中でこの句が一番詩的ですね。 菊地智)ほととぎす草今の季節にぴったりです。寄せ書きの皆さんの元気な様子が伺います。 |
|---|
| マンホールの蓋の浮世絵いわし雲 | 比良戸つつじ |
|---|
| 千草雨音)マンホールの蓋はバラエティに富んでいますね。浮世絵の蓋に出会った感動と爽やかな秋を象徴するいわし雲との取り合わせが決まっていると思います。 |
|---|
第151回句会 (2016年10月) 参加者:20名 |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 剥製の大魚口あく残暑かな | 松本道宏 | ←最高得点 |
| 下車1人そっと迎える彼岸花 | 境木権太 | |
| 秋蒔くや詩片いくつか鋤き込めり | 夏陽きらら | |
| いくたびもいでて無月をながめをり | たま四不像 |
|
| Tシャツと背広姿の秋彼岸 | 川瀬峙埜 |
|
| 鼻曲がり貌恐ろしき鮭遡上 | 奥隅茅廣 |
|
| 足速を待てよといえど秋の夕 | 石敬 |
|
| 遠き灯の十字に滲む秋黴雨 | 比良戸つつじ |
|
| 錆鮎のひととせの生果つ場所へ | 舞岡柏葉 | |
| 人住まぬ家にも咲くや金木犀 | 菊地智 | |
| 独り居のネット映画や秋黴雨 | 志摩光月 | |
| 赤々と命輝く曼珠沙華 | 野路風露 | |
| 長き夜や煩悩の渦果てしなく | 飯塚武岳 | |
| かぼす届き秋刀魚を買ひに一走り | 千草雨音 | |
| 夢うつつひつじ数へる長き夜 | ただの凡庸 | |
| 柿の実やかぞくの数に余りあり | 森かつら | |
| 三十年(みそとせ)や吾子を偲びて曼珠沙華 | 翁山歩存 | |
| 夏納め汗の吹き出る上り坂 | 木村桃風 | |
| リンリンと鳴く鈴虫の子守唄 | 相模野之長山 | |
| 彼岸入り舌が覚えてたあんをねる | 小正日向 | |
| ■ 十月の名句鑑賞(松本道宏)■■ |
|
十月の名句は 「足もとは もうまつくらや 秋の暮 草間 時彦」 です。 |
| ■第151回インターネット句会特選句短評■■ |
|---|
| 剥製の大魚口あく残暑かな | 松本道宏 |
|---|
| ただの凡庸)暑い残暑を、剥製の魚まで大きな口を開けているという表現が素晴しい。 |
|---|
| たま四不像)今回の自分的選句テーマは「オリジナリティ」です。 |
|---|
| たとえ上手であってもどこか見たような似たものがあるような句ではなく、 |
|---|
| 1 作者本人が体験したり作りたいことだったりを実感していると思われ、 |
|---|
| 2 それを「言葉や場面の切り取りでうまく表現」している |
|---|
| 3 そこに「オリジナリティ」を感じられた |
|---|
| この3点を基準にすると5選句のなかの6番が特選かなと。 |
|---|
| 比良戸つつじ)口をあけている剥製の大魚が、やりきれない暑さの残暑と響き合っている。とても上手い句だと思う。 |
|---|
| 木漏れ日のしづかなぬくみ秋の色 | 夏陽きらら |
|---|
| 相模野之長山)森林浴をしながら散歩している光景が浮かぶ。 |
|---|
| Tシャツと背広姿の秋彼岸 | 川瀬峙埜 |
|---|
| 石敬)墓参りに行くと、必ず見かける、父親と息子のちぐはぐさがどこかユーモラスな親子連れの姿。微笑ましいですね。 |
|---|
| 鼻曲がり貌恐ろしき鮭遡上 | 奥隅茅廣 |
|---|
| 舞岡柏葉)南部(岩手)の鮭でしょうか。たしかに鋭くとがった鼻は凶暴そうで恐ろしい顔ですね。 |
|---|
| 錆鮎のひととせの生果つ場所へ | 舞岡柏葉 |
|---|
| 菊地智)一年魚の鮎が産卵という仕事を終り次世代に命を託して終わる。人にも相通じます。 |
|---|
| 柿の実に青空映える里の山 | 野路風露 |
|---|
| 小正日向)青空に柿の実の熟れた色が映える里山の光景が目の前広がりほのぼのしました。 |
|---|
| 秋蒔くや詩片いくつか鋤き込めり | 夏陽きらら |
|---|
| 志摩光月)暮れには、香りの高い美味しい大根を頂けそうです。夢があります。 |
|---|
| 下車1人そっと迎える彼岸花 | 境木権太 |
|---|
| 奥隅茅廣)静かな駅の雰囲気の感じがよく出ています。 |
|---|
| いくたびもいでて無月をながめをり | たま四不像 |
|---|
| 千草雨音)「無月」のみ漢字を使われている表現に「曇れる十五夜」見えぬ月を観たいと願う気持ちが強く感じられ共感を覚えました。 |
|---|
| 川瀬峙埜)今年の名月の夜は曇りで月を見る事はできませんでした。川瀬峙埜)今年の名月の夜は曇りで月を見る事はできませんでした。 |
|---|
| 夏陽きらら)今年の中秋は生憎のお天気で、私も何度も空を見上げて溜息をつきました。お月さまの美しさを愛でるだけでなく、無月や雨月を惜しむのにもなんて趣があるのだろうと、俳句の奥深さを実感いたしました。 |
|---|
| 人住まぬ家にも咲くや金木犀 | 菊地智 |
|---|
| 木村桃風)住まっていたであろう住人が愛でた金木犀、無き住人を偲んで未だに芳香を放つ。人間と植物の麗しき機微を詠った句と思います。 |
|---|
| 柿の実やかぞくの数に余りあり | 森かつら |
|---|
| 野路風露)家族の人数も少なくなり、沢山の残された柿の実を目にします。 |
|---|
| 足速を待てよといえど秋の夕 | 石敬 |
|---|
| 境木権太)つるべ落としの秋の暮。もう一寸待って欲しいという気持ちになる今の季節にぴったりですね。 |
|---|
| 秋雨やシャッター街のジャズ喫茶 | 夏陽きらら |
|---|
| 翁山歩存)秋雨の寂しさとシャッター街の寂しさに似合わないジャズ喫茶とのアンバランスがよい。 |
|---|
| 森かつら)秋雨とシャッター街が合っている。 吉田町を思いました。 |
|---|
第150回句会 (2016年9月) 参加者:16名 |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 声援の喉の奥まで残暑かな | 松本道宏 | ←最高得点 |
| 点滴の滴の映す秋の空 | 野路風露 | |
| 言の葉の漂ふ世界蚯蚓鳴く | 比良戸つつじ | |
| 何もかも洗い流して野分晴 | 飯塚武岳 |
|
| 一人居の深夜の帰宅ちちろ鳴く | 川瀬峙埜 |
|
| 紅褪せて気だるき朝や酔芙蓉 | 境木権太 |
|
| 校庭の白線薄れ文月尽 | 舞岡柏葉 |
|
| 吾亦紅地蔵通りの喫茶店 | 千草雨音 |
|
| 玄関の蝉の死骸や秋きざす | たま四不像 | |
| 天心の雲に触れたる百日紅 | 菊地智 | |
| 羽化後蝉いのち煌くひすい色 | 翁山歩存 | |
| 暮れてゆく空の芯より秋の雲 | 夏陽きらら | |
| 黄昏にひぐらしを聴く老夫婦 | 木村桃風 | |
| 木洩れ日に微かに映ゆる秋の虹 | ただの凡庸 | |
| クーラーの部屋睨むかな古ヤモリ | 石敬 | |
| 雑草に来て人恋し赤蜻蛉 | 森かつら | |
| ■ 弘明寺抄(78)■■ |
平成28年9月7日
松本 道宏 |
九月の名句の紹介は 「頂上や殊に野菊の吹かれ居り 原 石鼎」 です。 |
第149回句会 (2016年8月) 参加者:16名 |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 篝火の火影に光る鵜の眼かな | 夏陽きらら | ←最高得点 |
| 空蝉にいのちの色の残りけり | 比良戸つつじ | |
| 空高く鳶の滑空梅雨明ける | 飯塚武岳 | |
| いのち生み風に揺れてる空(うつ)の蝉 | ただの凡庸 |
|
| 恙なく八十路を過ごす冷やし酒 | 菊地智 |
|
| 言い訳を笑って流す土用波 | 千草雨音 |
|
| 葉の先に背の紋割るや天道虫 | 奥隅茅廣 |
|
| 雲の峰わが胸中に休火山 | 松本道宏 |
|
| 狭き桶に一回り半江戸あなご | 舞岡柏葉 | |
| 海開き若き姿態の眩しけり | 志摩光月 | |
| 球場の蝉鳴き止みぬこの一球 | 境木権太 | |
| 機織りの音(ね)を呼び起こす綿の花 | 川瀬峙埜 | |
| 簾越し墨絵のごとき雨景色 | 翁山歩存 | |
| 油照りロックの響き弾け散る | 石敬 | |
| 老婆の背向かうは選挙夏の朝 | 森かつら | |
| あざなえる縄にも見える藤の幹 | 木村桃風 | |
| ■ 弘明寺抄(77)■■ |
平成28年8月7日
松本 道宏 |
八月の名句は『 炎天より僧ひとり乗り岐阜羽島 森澄雄 』です。 |
第148回句会 (2016年7月) 参加者:18名 |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 番茶つぐ音の響きや梅雨座敷 | 志摩光月 | ←最高得点 |
| ぼた山の長き眠りや梅雨の月 | 比良戸つつじ | |
| づんづんと雲の脱走夏の山 | 夏陽きらら | |
| 梅雨空やゆったり回る観覧車 | 野路風露 |
|
| 神の森梅雨こんもりと纏(まと)いをり | たま四不像 |
|
| 雨濡れる崖の割れ目の かたつむり | 森かつら |
|
| 池の端静かに語る白菖蒲 | ただの凡庸 |
|
| 雑草の我がもの顔や男梅雨 | 飯塚武岳 |
|
| 早口で哲学説く師田水沸く | 千草雨音 | |
| 雨脚を乱し乱して翡翠飛ぶ | 境木権太 | |
| 燃ゆる天折り鶴二つ黙しをり | 松本道宏 | |
| 濃紫陽花滴に藍を移しけり | 菊地智 | |
| 夏の川笹舟ゆるり進みおり | 東酔水 | |
| 白杖に愛犬そいて夕薄暑 | 翁山歩存 | |
| 窓ガラス上下左右と蝿自在 | 奥隅茅廣 | |
| とりどりに色変え魅せる梅雨の花 | 木村桃風 | |
| 鮎釣りの相模の河原一変す | 舞岡柏葉 | |
| 颯爽とカメラ目線の枝かわせみ | 石敬 | |
| ■ 弘明寺抄(76)■■ |
平成28年7月7日
松本 道宏 |
七月の名句は『七夕竹借命の文字隠れなし 石田波郷』です 。 |
第147回句会 (2016年6月) 参加者:14名 |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 草笛を鋭く鳴らし反抗期 | 比良戸つつじ | ←最高得点 |
| サングラスかけて見知らぬ街となり | 境木権太 | |
| 紙魚(しみ)の痕「源氏絵巻」の夏 | たま四不像 | |
| 背を割ってサーファ脱皮するところ | 松本道宏 |
|
| 麻のれん揺れて和金を分断す | 舞岡柏葉 |
|
| 根を張りてここが棲家と庭の雑草(くさ) | ただの凡庸 |
|
| 新緑の漲るちから天を突く | 木村桃風 |
|
| 母の日や形見の着物派手になり | 千草雨音 |
|
| 初恋の乙女現る昼寝かな | 志摩光月 | |
| 参道も御堂も埋めし山紫陽花 | 野路風露 | |
| シャクヤクや深紅のドレス八重衣 | 翁山歩存 | |
| 竹とんぼ五月の空にホバリング | 飯塚武岳 | |
| 車椅子目線の先につつじ咲く | 菊地智 | |
| 山里の夏柑のはな にほふとき | 森かつら | |
| ■ 弘明寺抄(75)■■ |
平成28年6月7日
松本 道宏 |
六月の名句は『青蛙おのれもペンキぬりたてか 芥川龍之介』です。 |
| 第19回吟行句会 (2016年5月) 参加者:15名 |
| (横浜公園〜県庁〜山下公園〜横浜港クルージング) |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 紫陽花のつほみならびて雨をまつ | 森かつら | ←最高得点 |
| 灯台に風のしなるや夏燕 | 夏陽きらら | ←最高得点 |
| 海跨ぐベイブリッチや雲の峰 | 飯塚武岳 | |
| 新緑に水琴窟の音の転ぶ | 比良戸つつじ |
|
| 小波に白き航跡夏に入る | ただの凡庸 |
|
| 氷川丸の歴史浮かべる卯波かな | 千草雨音 |
|
| 風の的船のデッキや夏帽子 | 土屋百瀬 |
|
| 海と空ひとつ色なり更衣 | たま四不像 |
|
| 夏草や鴨の姿のみえかくれ | 野路風露 | |
| 緑陰や水琴窟に耳澄ませ | 川瀬峙埜 | |
| 籐椅子に微笑む二人海広し | 志摩光月 | |
| 涼しげに水琴窟の響きかな | 翁山歩存 | |
| 噴水の前に並びし学友達 | 銀の道 | |
| 五月晴鴎が飛んでニューヨーク | 大野たかし | |
| 薄暑はや日陰うれしき船の上 | 東酔水 | |
 |
 |
|
| 第146回句会 (2016年5月) 参加者:13名 |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 潮干狩り大小尻の居並びて | 千草雨音 | ←最高得点 |
| 玉筋魚(いかなご)のつの字くの字のくぎ煮かな | 舞岡柏葉 | ←最高得点 |
| 葉桜や阿修羅の像の哀しき目 | 野路風露 | |
| 雨やんで力みなぎる若葉かな | 境木権太 |
|
| 富士の山乗せて揺らめく芝桜 | 飯塚武岳 |
|
| こいのぼり泳ぎつかれてぶら下がり | 木村桃風 |
|
| 願いもて高く生きよと武者飾り | 翁山歩存 |
|
| 死後のこと妻に言いおく日永かな | 比良戸つつじ |
|
| 春の虹手の傘上げて横断す | 松本道宏 | |
| 連れ立ちて逆遍路や閏年 | 奥隅茅廣 | |
| 雨上がり竹の子供は顔を出し | ただの凡庸 | |
| 中吊りの桜はらりと微睡みて | 森かつら | |
| プラタナス並樹の先に海に出ず | 浅木純生 | |
| ■ 弘明寺抄(74)■■ |
平成28年5月7日
松本 道宏 |
五月の名句は『祝辞みな未来のことや植樹祭 田川飛旅子』です。 |
| 第145回句会 (2016年4月) 参加者:16名 |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 縄文のビーナスの臍(ほぞ)山笑ふ | 松本道宏 | ←最高得点 |
| 米を研ぐこの手の記憶水温む | 菊地智 | |
| ひらひらと貝の舌だす日永かな | 比良戸つつじ | |
| 古稀迎えなおさかりなり紅枝垂 | 志摩光月 |
|
| 古民家に伝えのありて江戸の雛 | 翁山歩存 |
|
| いかなごのくぎ煮に箸の止まらざる | 千草雨音 |
|
| やはらかくひとひらほぐれ初桜 | 夏陽きらら |
|
| 草餅の鄙びたかほり母恋ひし | ただの凡庸 |
|
| 振り仰ぎ振り仰ぎつつ初音かな | 境木権太 | |
| 畑打の上りつめたり瀬戸の島 | 舞岡柏葉 | |
| 開花日や波紋の如く拡がりて | 奥隅茅廣 | |
| 北窓に春の形見を置きにけり | たま四不像 | |
| 花見客褒める言葉は多国籍 | 川瀬峙埜 | |
| たれと問ふ母の窓辺で桜観る | 浅木純生 | |
| 友と在る弘明寺公園花の宴 | 飯塚武岳 | |
| 枯れ枝に忽然と咲く姫こぶし | 木村桃風 | |
| ■ 弘明寺抄(73)■■ |
平成28年4月7日
松本 道宏 |
四月の名句は『外にも出よ触るるばかりに春の月 中村汀女』です。 中村汀女は昭和期に活躍した代表的な女流俳人です。星野立子、橋本多佳子、(この方の俳句は2年前にお知らせしました)三橋鷹女と共に「4T」と呼ばれました。本名は破魔子。中村汀女の経歴は調べてありますが、体調不良と視力の低下により仔細を記載できません。申し訳ありませんが、後は皆さん各自で調べて下さい。よろしくお願い致します。 |
|
|||||||
| (並選) | |
| 富士川や裾上げをした春の富士 | 境木権太 |
雪溶けで春の富士山が裾を上げたという把握は素晴らしいと思いました。 |
|
| 草餅の鄙びたかほり母恋ひし | ただの凡庸 |
「母恋し」で句が甘くなりましたが、「草餅の鄙びた香り」は素晴らしい感覚です。 | |
| 蕗味噌の卓に溢れる野の香り | 菊地智 |
| 食卓に蕗味噌の匂いが溢れている様子がよく分かります。「野の香り」がよいと思いました。 | |
| 春光に揺らぐ三半規管かな | 比良戸つつじ |
春の光の眩しさを自分の三半規管が揺らいでいると把握した作者は大変感覚的な方です。面白いところを捉えています。 |
|
全体的に物事の捉え方が昨年より素晴らしく上達し皆さんお上手になりました。 |
|
| 第144回句会 (2016年3月) 参加者:16名 |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 老夫婦形ばかりの雛人形 | 木村桃風 | ←最高得点 |
| 早起きに厨の床や冴え返る | 奥隅茅廣 | |
| 曳き売りの籠を溢るる春菜かな | 比良戸つつじ | |
| 訛りもて始まる噺土雛 | 松本道宏 |
|
| あの日には帰れぬものを涅槃西風 | 浅木純生 |
|
| 立春や昨日とちがふ富士の嶺 | 飯塚武岳 |
|
| 斑雪山(はだらやま)隈取り猛き武者のごと | 舞岡柏葉 |
|
| 白梅や風に色あり香あり | 翁山歩存 |
|
| 美酒に酔ひそぞろ歩きや春の宵 | 千草雨音 | |
| 里人に一声残し鳥帰る | 境木権太 | |
| これ以上淡き色なし桜貝 | 野路風露 | |
| 蛇穴を出て見れば街はゼロ金利 | 志摩光月 | |
| 斑猫のそり横切る春の夕 | 川瀬峙埜 | |
| モチベーション何のことやら朧月 | たま四不像 | |
| 膝を組みスマホ片手に花便り | 銀の道 | |
| チュンチュンの声高まりて春近し | ただの凡庸 | |
| ■ 弘明寺抄(72)■■ |
平成28年3月7日
松本 道宏 |
三月の名句は 『まさをなる空よりしだれざくらかな 富安風生』 です。 |
|
|||||||
| (並選) | |
| むくむくと小石持ち上げ福寿草 | 木村桃風 |
よく見ると、芽を出して大きくなった福寿草が小石を持ち上げているのに驚いている作者が見えてきます。福寿草ではありませんが草が小石を持ち上げている状況は時々見受けます。 |
|
| 蛇穴を出てみれば街はゼロ金利 | 志摩光月 |
世の中、ゼロ金利に驚いているのは人間だけでなく、冬眠から覚めた蛇もゼロ金利に驚いているのがユーモラスに描かれています。 | |
| 春風に乙女の葛匂いたち | 飯塚武岳 |
| 春風によっての匂いたっている乙女の鬘とは何んと美しい姿でしょうか。 | |
| 白梅や風に色あり香りあり | 翁山歩存 |
白梅によって風に色と香りを感じた作者の気持ちが良く表れています。 |
|
| 第143回句会 (2016年2月) 参加者:16名 |
| ■ 作 品 ■■■ |
| こめかみに風の尖りや初薬師 | 比良戸つつじ | ←最高得点 |
| 蝋梅に遙かな記憶匂い立ち | 川瀬峙埜 | |
| 装ひてパンと帯打ち初句会 | 千草雨音 | |
| 飛び石を浮島と化す敷松葉 | 舞岡柏葉 | |
| 轟轟と登り窯吼ゆ冬銀河 | 松本道宏 |
|
| 母となる娘の笑顔福寿草 | 飯塚武岳 |
|
| 恙なく総身に浴びる初日かな | 奥隅茅廣 |
|
| 黒塀のなかは異界か寒椿 | たま四不像 |
|
| グツグツと良き味いずる鍋の声 | 翁山歩存 | |
| 太き柄に力みなぎる冬北斗 | 境木権太 | |
| 積樽の菰の髭文字黒々と | 菊地智 | |
| 若僧の掛け声冴ゆや禅の寺 | 志摩光月 | |
| しんしんと雪の降る夜救急車 | 木村桃風 | |
| 大根のほっかり煮えて母の味 | 野路風露 | |
| 風花や手のひら上での星座かな | ただの凡庸 | |
| 初場所に十年ぶりの賜杯かな | 浅木純生 | |
| ■ 弘明寺抄(71)■■ |
平成28年2月7日
松本 道宏 |
| 二月の名句は「冬蜂の死にどころなく歩きけり 村上鬼城」です。 村上鬼城は鳥取藩主小原平之進の長男として1865年6月10日(慶応元年以下元号は略します)江戸に生まれました。8歳の時群馬県高崎市に移り住み、11歳の時に母方の村上家の村上源兵衛の養子となり村上を名乗りました。 1884年に東京に行き軍人を志しましたが目疾のために断念し、明治法律学校(明治大学の前身)、で法学を学びながら司法代書人(司法書士の前身)になった。父の勤務先である高崎裁判所司法代理人となりました。以後、鬼城は亡くなるまでの一生を高崎で過ごしました。勤務の傍ら俳句を嗜み、広島市の大本営にいた正岡子規に俳句の教えを請い、また幾度となく「ホトトギス」に投句を行っていました。子規の死後、高濱虚子から句を見てもらいました。 高崎での俳句会で虚子の推挽を受けました。これが契機となって1913年からホトトギスの同人活動を始め、1918年に自身の句が入選。以後司法代書人の傍ら俳人として、また、選者として敏腕を振るいました。51歳のときに代書人を解雇されましたが、虚子門下の弁護人を立てて復職を遂げました。 1938年(昭和13年)74歳で死去。お墓は高崎の龍広寺にあります。 |
|
|||||
| 母となる娘の笑顔福寿草 | 飯塚武岳 |
自分の娘が母となる事は自分は「おじいちゃん」になることですが、至福の喜びが季語の「福寿草」によくあらわれています。 |
|
| 初孫が嫁つれて来る御慶かな | 菊地智 |
初孫が嫁をつれて来ることほど御慶なことはありません。句に詠みたい気持はよく判りますが、俳句の質としては落ちますのでご注意を。 | |
| しんしんと雪の降る夜救急車 | 木村桃風 |
| あたり一面雪に覆われた静かな時に、救急車がひときわ高い音を立ててやってくる情景が詠まれています。 | |
| 凍て空や残月に添ふ星一つ | 千草雨音 |
寒い夜が明けて残月に星が寄り添うように輝いている状態が詠まれています。何となく心引かれる句です。俳句はこのように詠みたいものです。 |
|
| 第142回句会 (2016年1月) 参加者:18名 |
| ■ 作 品 ■■■ |
| 装いをきっぱり脱いで冬木立 | 境木権太 | ←最高得点 |
| しらす丼叫ぶごときの眼が千個 | たま四不像 | ←最高得点 |
| 故郷(くに)は今大雪警報賀状書く | 舞岡柏葉 | |
| 祈るとは立ち止まること冬の菊 | 松本道宏 | |
| 朝日受け骨格露わに冬木立 | 野路風露 |
|
| 冴ゆる夜寒柝(カンタク)の音打ち通る | ただの凡庸 |
|
| 卒寿こえ爺はたっしゃで年暮るる | 翁山歩存 |
|
| 鎌倉路石蕗に日の差す切通し | 菊地智 |
|
| くつくつと音の煮えゆく冬至粥 | 比良戸つつじ | |
| 初めての道に迷ふや冬の虹 | 千草雨音 | |
| 枯葉散る気儘に描く軌跡かな | 奥隅茅廣 | |
| 障子貼る日射しのなかに妣(はは)の影 | 飯塚武岳 | |
| クリスマス隣家の灯り楽しげに | 長部新平 | |
| 凍てついた闇を切り裂く鐘の音 | 志摩光月 | |
| ジビエ食う江戸散策や枯柳 | 森かつら | |
| 大歳の蕎麦茹で時間5分なり | 川瀬峙埜 | |
| 景気よし師走の雑踏物語る | 木村桃風 | |
| 賑わいの街に繰り出し年忘れ | 浅木純生 |
| ■ 弘明寺抄(70)■■ |
平成28年1月7日
松本 道宏 |
| 明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。 一月の名句は「湯豆腐やいのちのはてのうすあかり 久保田万太郎」です。 久保田万太郎は1889年(明治32年)東京府東京市浅草区浅草田原町3丁目 (現在の東京都台東区雷門)に生まれました。生家は「久保勘」という袋物製造販売(足袋)を業とし、店にはいつも15〜16人程の職人が働いていました。浅草馬道(現在の花川戸)の市立浅草尋常小学校(現在の台東区立浅草小学校)を卒業し、東京府立第三中学校(現在の東京都立両国高等学校)に進みました。一級下に芥川龍之介がいました。1906年4年への進級試験で数学の点が悪く落第した為に中退し、慶応義塾普通部へ編入し、三年をもう一度繰り返して留年し、慶応義塾大学予科へ進学した時に文学科における文科改革(森鴎外や永井荷風が教授に就任)と出あったことが万太郎の運命を決めました。 小説家・劇作家・俳人・江戸文化他多彩。1963年74歳で亡くなりました。 皆さん久保田万太郎についてはよくご存知と思いますので経歴は大分省略しました。 |
|
|||||
| 鎌倉路石蕗に日の差す切通し | 菊地智 |
鎌倉には亀ケ谷坂・朝比奈・化粧坂などの切通しがありますが、いずれも暗く日が差す切通しに石蕗の花が咲いていたのを発見した作者に拍手を贈りたいと思います。 |
|
| アメ横の渦巻く人や年用意 | 飯塚武岳 |
12月になりますとアメ横の風景はテレビで屡中継されますが、年末は早朝から人が渦巻いており、吃驚させられます。年末の情景を上手に詠まれています。 | |
| 遠来の孫を抱きて柚子湯かな | 志摩光月 |
| 一般的に孫の句は甘いといわれていますので出来るだけ採らないつもりでしたが、この句には実感があり頂きました。 | |
| 凍てついた闇を切り裂く鐘の音 | 志摩光月 |
この鐘は徐夜の鐘でしょうか。凍てついた闇夜を切り裂くようにして、響く鐘の音に臨場感があります。 |
|