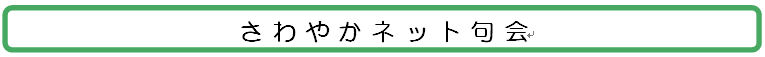|
岡田克子選
特選 横浜の海とショパンと春の雲(たま四不像)
山下公園から穏やかな海を見るのが好きです。句全体に癒しを感じました。
ショパンのワルツのせいでしょうか。季語がふんわりと幸せにしてくれました。
平成の想ひ出乗せて春が行く(ただの凡庸)
小渕さんが「平成であります」とついこの間に聞いて様に思います。
アット言う間に平成も30年4か月で終わります。嬉しいことも悲しいこともありました。この句 の様に春風が平成の想い出を乗せていきます。
これも別れの句。
菜の花や園児の帽子見えかくれ(志摩光月)
菜の花畑に遠足の景が浮びます。菜の花の丈と園児の背の丈が
どっこいどっこいなんですね。 下五が良かった。
空青き菜の花の海に飛び込む(野路風露)
空は青いし菜の花畑は黄色一色できれいだし、おもわず海のようだ
と飛び込んだ心象句。作品が青春しています。
人波の川面に映る花見かな(志摩光月)
内容は簡単ですが、大岡川沿いの花見時はまさしくこの様な感じです。 素直な句です。
今月の一言
助詞力をアップする
「で」=原因、結果となる、なるべく使わない方が良い。
「は」=取り出したひとつのたとえ「空は茜色」とか。
「を」=時間、空間を現わす。
「に」=きづき、場所。
「へ」=動きの方向、句に動きが出る。
苺パフェ平らげ匙を舐める舌(川瀬峙埜)
(千草雨音)とても美味しい苺パフェだったのでしょう!「匙を舐める舌」に子供の表情が目に浮かびます。
山吹や平成の日々しめにけり(志摩光月)
(ただの凡庸)山吹の花ことばを調べたところ「気品・崇高」でした。平成が終わることを上手に詠んだと築きました。
草餅のかわく仏間で眼鏡とる(岡田克子)
(たま四不像)毎日の繰り返しである生活を句にするのはなかなか難しい。その点、食べ物を季語にすると季節感が良く出る。この句はそういう意味でも面白いと感じた。「草餅のかわく」で季節感がでて、それが「仏間」という特別の場所、「眼鏡とる」で作者の登場により現実味が伝わる。「かわく草餅」に「仏間」そしてなぜか「眼鏡をとる」、この意外性の連続が余韻となり物語的想像が浮かぶ句であった。
蕗の薹天を窺い顔を出し(飯塚武岳)
(翁山歩存)春が近づき蕗の薹が芽生える雰囲気をうまく表現していると思いました。
のどけさや妻の小言もよく響き(真野愚雪)
(境木権太)いつもの妻の小言もうららかな春の陽気の中ではのどかに響きます。幸せな家庭の日常を巧みに詠んでいます。
ほくほくと土筆のならぶ畔の道(ただの凡庸)
(遊戯好楽)土筆の並ぶ様子を「ほくほくと」がなんとなく春の温かさを感じた。
痛みとて生くる証や春疾風 (名瀬庵雲水)
(森かつら)春疾風・・春先に吹く強い風の呼び名のひとつ・・勉強になりました。
痛みは暖かくなるにつれ和らぐと詠みました。
永平寺の僧の蹠(あしうら)春障子(岡田克子)
(菊池 智)只管打坐ひたすら座禅する僧静かな雰囲気の中障子を通し柔らかな春の訪れが描かれています。
笑み浮かべ古き雛や母の影(野路風露)
(舞岡柏葉)幼い日に両親が娘の幸多き人生を願い求めた雛のでしょう。小さかった頃気が付かなかった古き雛の笑みに母の面影を発見した喜びの情景が目に浮かびます
マスクしてマスクをを避(よ)ける診療所(翁山歩存)
(名瀬庵雲水)冬の季語ですが、滑稽さを感じます。自分も同じ事を無意識にしているかも。
病院や医院でなく診療所にしたところは、語呂も良く、味わいのある句 になったと思います。
菜の花や園児の帽子見えかくれ(志摩光月)
(小正日向)園児たちのはしゃぐ声が聞こえてくる黄色く染まる菜の花畑が見えるようです。
仮設所の軒端華やぐ吊るし雛(境木権太)
(飯塚武岳)被災地の仮設所で暮らす人々にも春は巡ってきます。吊るし雛が厳しい生活を癒し希望をもたらしてくれます。生きることへの逞しさ明るさが感じられます。
(野路風露)吊るし雛が元気を与えてくれると良 いですね。
碓氷とけて相模の風土記かな(たま四不像)
(川瀬峙埜)古い昔の歴史の謎が少しずつ氷が解けていくように分かっていくのはなんだかワクワクして清々しい春を迎えたような気分ですね。
空青き菜の花の海に飛び込む(野路風露)
(石 敬)景色への感動、気持ちの躍動が伝わる生き生きしたテンポのいい句ですね。ドーンと飛び込みたくなる一面の黄色い花畑、先日皆で行った南房総の情景です。
若鮎や前行く子らの長き脚 (千草雨音)
(志摩光月)季語の選択がよく、また 詠み手の心情を含め状況がよく見える秀句と思います。
ドイツミサ春の寒さをやさしくす(たま四不像)
(真野愚雪) しらべて意味を知る前に、先ず「ドイツミサ」という異教的な憧れを掻き立てるようなことばに引き付けられます。それが 凛とした「春の寒さ」と共鳴し合って清しく響きす。個人的な嗜好では「やさしゅうす」とよみたいです。
|